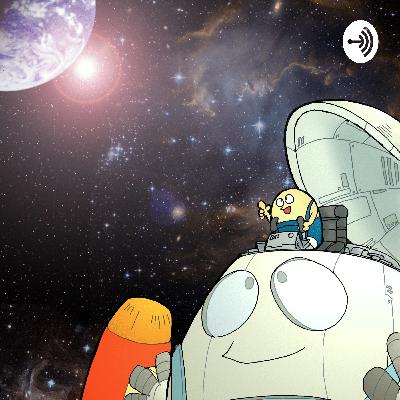Discover でき太くんの算数クラブ
でき太くんの算数クラブ

26 Episodes
Reverse
久しぶりにPodcastを再開しました。今回は学習の「習慣化」について話をしてみました。
今回は「みんなのお悩み相談室」ということで、会員のお母さまからお寄せいただいたご相談のメールを読ませていただきました。
きっと他にも多くの親御さんが、同じような悩みを抱えているのではないかと思います。
声かけしないと宿題もでき太くんも始めない、学校の準備もいつもギリギリまでできない、取りかかりが遅いなど。。。
こういった問題を解決するヒントが、今回のポッドキャストにはあるかもしれません。
今後のご参考になれば幸いです。
今回は「復習の大切さ」についてお話をさせていただきました。
復習を日々の学習に上手に取り入れていくと、学習効果をさらに高めていくことができます。
今回の内容は、でき太の学習だけでなく、他の教科にも応用できます。
ミスをするのはダメなこと。ミスをすることははずかしいこと。このように捉えている人は多いかもしれません。
でき太くんの算数クラブでは、ミスは「たからもの」だと考えています。
なぜミスは私たちにとって「たからもの」なのか。今回のポッドキャストでは、このことについてお話をさせていただきました。
今回はリスナーからうれしいコメントをいただきました。それと併せて、でき太の学習材の学習効果を最大限に引き出すポイントについてもお話をさせていただきました。
今回で2回目となりました「ひとりポッドキャスト」
前回に引き続き三沢が、日々考えていることについてお話をさせていただきました。
お時間のあるときにご聴取いただければと思います。
これまでのポッドキャストのほとんどは、ディスカッション形式の内容のものを配信させていただきました。
今回は新しい試みとして「ひとりポッドキャスト」をスタートします。今回は三沢が担当させていただきました。
どのような内容かは、聞いてからのお楽しみということで。
今回も前回に引き続き「場、環境」についてお話をさせていただきました。
子どもがやる気になる環境というのは、どうしたら作ることができるのでしょうか。
今回のポッドキャストを聞けば、そのポイントがしっかり理解できるはずです。
いつもご聴取くださり、ありがとうございます。
今回は、これまでお話してきた「家庭教育力」というテーマの核心部分について、皆さんにお届けしていきたいと思います。
子どもの「能力」、「性格」や「個性」などは、どのように形作られていくのでしょう。
生まれ持って決まっているものなのでしょうか。それとも、外部要因によって形作られていくものなのでしょうか。私たちは、外部要因としての「場」、「環境」が、子どもにはとても大きな影響力があると考えております。
今回は「場」、「環境」について、私たちがどのように考えているのかを、じっくりお話させていただきました。
前回に引き続き「禍を転じて福と為す」というテーマでお話させていただきます。
今回は小学校3年生の会員さんとそのお父さんのお話です。
休校中、家庭で学習を進める中での出来事です。
ぜひ、お聴きになってみてください。
毎日の生活の中では、自分にとって不都合なこと、思い通りにならないことが起きてきます。
このような時にどう対処していくかは、学校教育だけでは、子どもたちに伝えきれないテーマだと思います。
これは、ご家庭での実践なくして、子どもたちに伝えていくことはできないと思います。
苦しい状況を幸せな状況に変えることができる人は、「人生の達人」と言えるかもしれません。
我が子を「人生の達人」にするためには、「家庭教育力」が大きな役割を果たしています。
今回の外出自粛の中、想像力を使って豊かに生活している方がいます。
家の中にいる時間が長いことを活用して、楽しいひと時を送る良い例が見つかりましたので、ご紹介させていただきます。
https://youtu.be/qQnfwvmZmxg
勉強をイヤイヤシブシブ取り組む子どもたちがたくさんいます。
しかし、心の奥底では、子どもはだれでも「算数ができるようになりたい!」、「勉強ができるようになりたい!」と願っています。
この「願い」を実現する方法について、今回はお話をさせていただきました。お時間のあるときにご聴取いただければと思います。
「なぜ、勉強をするの?」「なぜ、学校で勉強をするの?」
この質問の「答え」は様々だと思います。
「それは義務教育だからです」という答えや、「将来受験で失敗しないため」というものもあるでしょう。
では、実際に日々勉強をしていく子どもたちは、どのような「答え」をもっていれば、主体的にやる気をもって勉強に臨むことができるのでしょうか。今回はこのことについてお話をしてみました。
子どもが興味、関心があること。好きなこと。
それを思う存分学習できる環境を整えることができれば、きっとそのお子さんの個性はどんどんみがかれていくと思います。
では、日常起きてくる「好きではないこと」「嫌いなこと」と、子どもたちは、どのように向き合っていけばよいのでしょうか。
今回のポッドキャストでは、その点について、じっくり話をしてみました。
今回は前回に引き続き「家庭教育力」をテーマに、トークセッションをしました。
前半部分では、前回のポッドキャストをご聴取いただいた上での感想や、noteでのコラムをお読みいただいた上での感想をご紹介させていただきました。みなさん今回の休校期間中に、今後のわが子の教育について考えさせられることが多くあったようで、前回のポッドキャストやnoteでのコラムがとても参考になったとおっしゃってくださいました。
今回のトークセッションでは、「家庭教育力」について、前回よりも少し深いテーマについてお話をさせていただきました。編集をしましたが、それでも少し長くなってしまいました。お時間があるときにご聴取いただければと思います。
先週末に「家庭教育力」というコラムを掲載しましたが、お読みになりましたでしょうか。
今回のポッドキャストでは、そのコラムの中で十分にお伝えできなかったことを、トークセッション形式でお伝えしようと思います。
今回の政府からの突然の休校要請で、多くの方が困惑されたかと思います。ただ、このことによって、私たちがこれから解決していかなければいけないテーマが浮かび上がってきました。このトークセッションで、解決策が提案できればと思っています。
学習の「学」という字は、「まねび」といって、「まねをする」という意味があります。
「でき太くんの算数」という学習材は、その「まねび」を実践すると、学習効果を最大限に引き出すことができるようになります。
今回は「まねび」の大切さについてお話しさせていただきました。
就学前、低学年の時期からでき太くんの算数クラブでは、お子さん自身で丸付けをするように学習指導させていただいています。
それは、学習に欠かせない「定着センサー」を身につけていただきたいと考えているためです。
今回はその「定着センサー」についてお話をさせていただきました。
でき太くんの算数クラブが考える本当の学習とは!?
この点をしっかりふまえて「でき太くん」を学習していくと、「でき太くん」の学習効果を最大限に引き出していくことができます。
前回の第7回と第8回は、どの回よりも優先的にご聴取いただければと思います。
今回は「でき太くんの算数」の学習効果を最大限に引き出すコツについてお話させていただきました。
日々の学習のご参考になれば幸いです。