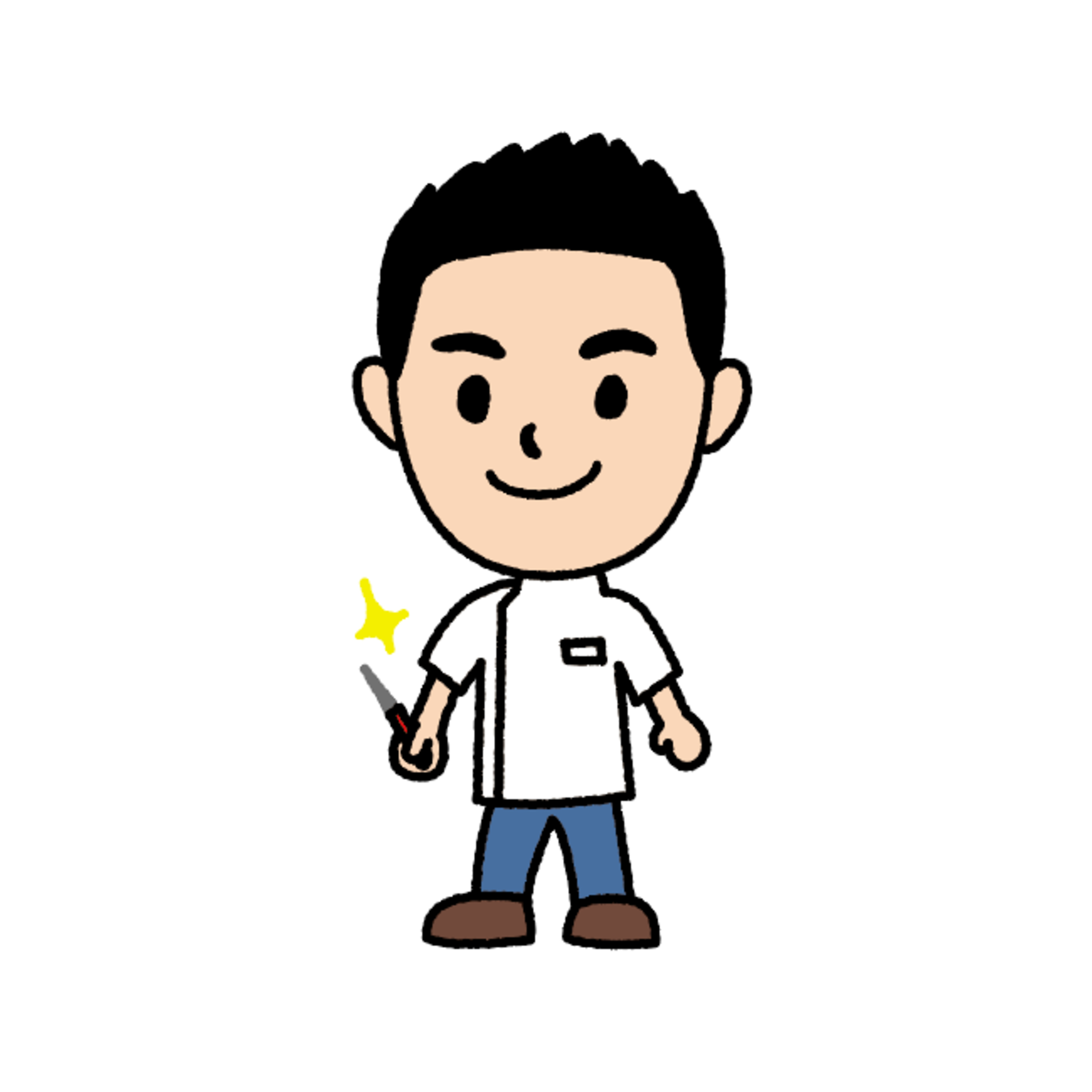Discover 松本コウイチの鍼灸健康講話
松本コウイチの鍼灸健康講話

79 Episodes
Reverse
誰かを怒ることも好きではないですが、怒られることも好きではありません。それでも世の中は怒りに満ちあふれています。いったい怒る人は何にそんなに怒ったいるのでしょうか。自分が怒りに対する認識を新たにすることができれば、怒りに対する不安も軽減されるのではないでしょうか。感情は決してすべて抑えればよいというものではありません。ただ、怒りに関してはそのエネルギーが強く、そして破壊的でさえあります。今回は怒ること、怒る人、そして自分が怒ったときにどのように受け止めるかということについてお話ししました。
悲しいことが一切なければ良いのに、それでも悲しいことが起きたりします。ふさぎ込むときがあります。怒りに震えることもあります。そのようなことが無いように心がけているのに。そのような理不尽さに見舞われることも人生では起こりうることです。だからこそ、私たちが必要なのは純粋な回復力です。つまり立ち直ることを覚えて進まなければなりません。それはそう簡単にできることではありません。しかしながら、私たちが悲しくて涙したときからずっと、今まで泣いているということはありません。ずっとふさぎ込んでいることもないでしょう。それは立ち直ったからにほかなりません。人生の貴重な時間をできるだけ喜びや笑顔で過ごすために「立ち直ること」を覚えておくことも大切な工夫かもしれないのです。
漢字は古人の思いや考えの宝庫です。 「叶う」という漢字は「きょう」とも読み協力の「協」の略体の字だといいます。そして力は耡(すき)を表します。 協という文字は「衆の同(とも)に和するなり」 と説文解字に説明があり「叶える」ためにはどうする必要があるのか古人の考えをうかがい知ることができるのです。はたして私たちは夢を叶えるにはどうしたらよいのでしょうか。古人の考えを参考に実現してみたいものです。
東洋医学は五行(ごぎょう)という木、火、土、金、水に分類する考え方があります。顔色についても同じように5つの色に分けて五臓六腑の影響を考えます。偏った色味はそれに対応する内臓の異変を疑います。ただし肌ツヤが良い場合はその限りではありません。肌ツヤが悪い場合はしっかり休養を取るなどチェックするポイントでもあります。
人が生きていられるのはおそらく死ぬことを忘れているから。「自分がいつか死ぬことを忘れるな」という意味の警句であるメメント・モリ。この言葉の大きさこそ「より良く生きるために」必要なエッセンスかもしれません。自分なりのメメント・モリを受け入れられた時、人間的に一歩前進するのではないかな、と思うのです。ただ、それはまだまだ先のことかもしれませんけれど。
私は日々、反省をすることがあります。なかでも気をつけていることがあります。それは「手をやすめること」です。自分のリズムが中断されるのを嫌がるという言い訳をしてしまいがちですが、おそらくそこには自分以外に注意を払う余裕がない状況なのかもしれません。
年齢が高齢でなくとも思い込みや勘違いというものはよくあります。(若い人は気にしないだけです)。今回は代表的な勘違いなパターンである認知バイアスについてご紹介します。人間として判断の誤りを起こしやすいパターンは存在します。その存在を知っていれば人間である限り情けない判断ミスは起こり得るのです。学者を目指すわけではないでしょうから今回は少しだけご紹介します。
山田方谷は幕末の陽明学者。安岡正篤先生も心酔したという人物です。その山田方谷も学ぶことの大切さや違いを認めることの重要性をエピソードのひとつとして残しています。私たちは自分の価値観を基準に物事を判断します。しかし、価値観はすべてに共通して正しいとは限らないでしょう。そんな謙虚さを忘れないように気を引き締めるエピソードでもあります。
幕末の儒学者である山田方谷は人のこころは鏡であると説いています。私たちは外界に求めるものが多いのですが、外界に映るものも結局は自分自身の鏡のようなものであるといいます。悪しき人には悪く見え、善良な人には善に見えるという極めて自然な道理を説いたエピソードです。
人間関係のなかでも家族の関係性にストレスを感じている人は多くいます。それは思春期の一過性のものではありません。なぜ近い関係なのに不快な思いで対立するのでしょうか。家族だからといってわかった気にならず相手を尊重することが大切だと考えます。その第一歩が「話しを聞こう」という提案です。
国民性なのか、県民性なのか、自己主張があまりできない人がいます。そうでなくとも相手の意向に従い過ぎて自分にストレスが集まってしまう人もいます。これは珍しいことではありません。自分の価値基準をしっかりと見直し、その達成のためには相手の要求を断る勇気もときに必要となるのです。
習慣というものは、自分自身を知らないうちに思いがけない環境に連れて行ってしまうものです。それが良い意味でも悪い意味でも共通します。今回は「1日1000歩多く動くという意識を習慣としてみたら」と提案しました。このような実践が習慣となったときに、どのような変化が起きるのでしょうか。理屈で知るよりも、ぜひ実践してみてください。
ウイルスについて深く知る必要はありません。とにかく「手を洗う」ことがウイルス対策の大きな柱だということを理解してください。そして、それを欠かさず実行してください。あまり言うと潔癖症を引き起こすかもしれませんが、それくらい手を洗うことは大切な予防効果があるのです。
体の調子は、いたるところで変化として現れます。なかでも舌の色や苔の量などは素人目に見ても日々の変化が観察しやすい部位でもあります。厳密に判断しないまでも、赤か白か、という目安だけでも知っておくとその後の対処が自分でできますので是非よく観察してみてください。
杉山検校は苦難の末に新しい技術を身につけイノベーションを発揮しました。彼の功績は鍼灸の技法のみならず、盲人、健常人に関わらず生き方それ自体がお手本です。まるで寓話か神話でもあるようなストーリーで後世に多くの希望の光を与えたことでしょう。文化伝統というものは、本当に数奇なエピソードの蓄積だといえます。
「気を持って気を整えるのは自分にある」と心の平和を実践するのは自分の心がけだと沢庵和尚は言っています。花鳥風月という言葉がありますが、花や鳥に心を移し、気持ちの豊かさを保つことこそ自分でできる気を整える方法だと教えてくれます。なかなか穏やかにいることが難しい現代。和尚のアドバイスに耳を傾ける必要もあるでしょう。
カフェインの健康作用について話題になることが多いですが、それはカフェインが優れているのではなく、研究対象として調査している人が多いからではないか?と穿った見方もできます。何事にも長所と短所があります。また度が過ぎれば何でも害悪になるので注意喚起しています。
コレステロールがそれほど問題視されなくなったのは、コレステロールの働きが徐々に解明されてきたため。それでも投薬治療が無くならないのは研究結果が現場レベルにまで至っていないのでしょう。血管を修復するために集まったコレステロールが誤解をされたために続く悲劇。多くの議論によってはっきりと結論が開示されると良いのですが。
コレステロールの歴史を見ていくと意外な事実にぶつかります。なんとアメリカではそれほど重要視されていない項目なのです。それでは、その事実は日本に伝わっているのかと言われれば現場レベルでは、いままで通り投薬によってコントロールすべきものという認識のようです。
アレルギー食品ではないのに、自分の体に合わないもの(消化・分解できないもの)が存在します。それは人によって違うので注意が必要です。あまり知られていませんが、食物不耐症というものはかなりの人にある、いわば体質のようなもの。食べ物に良し悪しがあるのではなく本人との相性もあるというのは見落とされがちな視点です。