Discover アートのミーム
アートのミーム
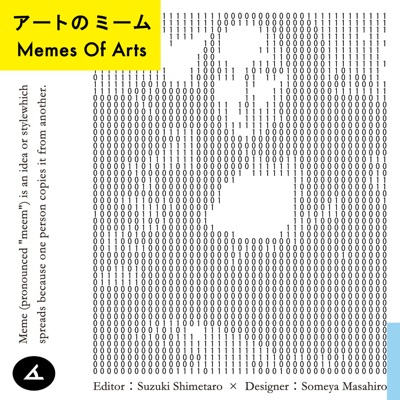
144 Episodes
Reverse
アートのミームを始めて1年目に配信した「鑑賞に役立つ西洋美術史」をリブートして、Ver2.0としてお送りします。7回目はネーデルラントを中心に発生した北方ルネサンスについて。イタリアルネサンスとは異なったバックボーンを持ち、ヤン・ファン・エイクが発展させた油絵の特性を活用して、細密で情報量が多い絵が生まれました。▼今回紹介したヘント祭壇画はこちら⇨https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/76957(JBPress:記事内に「アルノルフィーニ夫妻の肖像」の画像もあり)▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
アートのミームを始めて1年目に配信した「鑑賞に役立つ西洋美術史」をリブートして、Ver2.0としてお送りします。6回目はイタリアルネサンス以後に登場したマニエリスムについて。フィレンツェで最盛期を迎えたルネサンスは他の土地に伝播して、様式のフォロワーを生み出していきました。そうして生まれた表現が、マンネリズムの語源になった「マニエリスム」です。▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
アートのミームを始めて1年目に配信した「鑑賞に役立つ西洋美術史」をリブートして、Ver2.0としてお送りします。5回目はイタリアルネサンスの最盛期に活躍した芸術家と、その作品について。この時代には、マザッチオやボティチェリをはじめ、ダヴィンチ・ミケランジェロ・ラファエッロなど著名な作家が活躍して、今なお愛されるマスターピースを残していきました。▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
アートのミームを始めて1年目に配信した「鑑賞に役立つ西洋美術史」をリブートして、Ver2.0としてお送りします。4回目はイタリアルネサンスが発生した背景について。このムーブメントは、戦争・飢饉・疫病・他民族の襲来などヨーロッパの混乱や、貿易・商業の発展を背景に発生しました。新たな社会秩序が求められた時代に人々が参考にしたのが、古代ギリシアやローマの社会制度や学問です。この転換の中で、美術も人文的な表現を模索していきます。▼エピソードで紹介した作品はこちら・ジョット・ディ・ボンドーネ「マエスタ(荘厳の聖母)」⇨https://firenzeguide.net/giotto-maesta/・ジョット・ディ・ボンドーネ「ユダの接吻」⇨https://art-bible.hatenadiary.jp/entry/Kiss-of-Judas-Giotto▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
アートのミームを始めて1年目に配信した「鑑賞に役立つ西洋美術史」をリブートして、Ver2.0としてお送りします。3回目は中世ヨーロッパの建築について。壁画やステンドグラス、聖人像など様々な美術で彩られた教会建築。当時登場したロマネスク建築やゴシック建築について紹介します。▼エピソードで紹介した作品はこちらロマネスク建築・ピサ大聖堂⇨https://youtu.be/EagvR4RjzNE?si=18fbwp6klHccPqeU・マリア・ラーハ修道院聖堂⇨https://youtu.be/MCqgUc-SSvk?si=LyCydcdS6mO8dikI・サン・ゼーノ教会⇨https://youtu.be/wSJrQRjfxf8?si=iHkoPNhw5YKFhQjG&t=242ゴシック建築・アミアンのノートルダム大聖堂⇨https://youtu.be/UrA4G1tMqXc?si=RFtYi1ddTMIcnxqX・ケルン大聖堂⇨https://youtu.be/SMinfvvt3iw?si=nFfl79-0G-d6KwFH・パリのノートルダム大聖堂⇨https://youtu.be/DlzKj6_B0kA?si=xhscDjZWINCPAkXJ▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
アートのミームを始めて1年目に配信した「鑑賞に役立つ西洋美術史」をリブートして、Ver2.0としてお送りします。2回目はローマ帝国分裂後の中世ヨーロッパについて。約1000年に渡って続いたこの時代には、キリスト教をベースに、様々な民族の文化が混ざり合い、多様な表現が生まれました。▼エピソードで紹介した作品はこちら・アヤソフィアの聖母子像⇨https://turkish.jp/destinations/%E3%82%A2%E3%83%A4%E3%82%BD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A2/?srsltid=AfmBOooa6yyHzWO9iU6KFv1C1z2SQRvC0MFmTq84gE9dY8RXcBqWLh_d・ケルズの書 聖母子像⇨https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%81%AE%E6%9B%B8#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:KellsFol007vMadonnaChild_V2.jpg・サントクリメント協会 栄光のキリスト⇨https://www.hasegawadai2.com/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3/%E3%83%9C%E3%82%A4%E6%B8%93%E8%B0%B7%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%A3%E9%A2%A8%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%A7%98%E5%BC%8F%E6%95%99%E4%BC%9A%E7%BE%A4/▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
アートのミームを始めて1年目に配信した「鑑賞に役立つ西洋美術史」をリブートして、Ver2.0としてお送りします。初回は西洋美術の原点となる古代ギリシア・ローマ時代からスタートします。美学や画商、作家の生涯など、過去に配信してきた様々なシリーズを経て、内容のアップデートを行いました。▼エピソードで紹介した作品はこちら・クーロス像(メトロポリタン美術館)⇨https://www.metmuseum.org/ja/art/collection/search/253370・ミロのヴィーナス⇨https://www.louvre-m.com/collection-list/no-0010・エルギン・マーブル⇨https://artsandculture.google.com/streetview/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_h=3.656354574048102&sv_p=0.6446988133429699&sv_pid=NH7eJxyFuHq1IJvG6ti-jQ&sv_lid=3582009757710443819&sv_lng=-0.12842798447153425&sv_lat=51.51907909102465&sv_z=0.7982306681470359・ラオコーン像⇨https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/laocoonte.html・ベルヴェデーレのトルソ⇨https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/museo-pio-clementino/sala-delle-muse/torso-del-belvedere.html▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
映画版のタローマンを観てきたので、ネタバレありで感想を話します。後編は黒幕の正体と作中に散りばめられたオマージュについて。▼大長編 タローマン万博大爆発の公式HPはこちら⇨https://taroman-movie.asmik-ace.co.jp/▼アートのミームの岡本太郎回はこちら前編⇨https://open.spotify.com/episode/3BMEnELd6YZul97FY0onT7?si=ahKPQuOjSxa63nhLSzwP5Q後編⇨https://open.spotify.com/episode/4ByccfefpXmx7tD4n8YtSc?si=o5Co0mlhRpqboY2o4w17Aw▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
映画版のタローマンを観てきたので、ネタバレありで感想を話します。徹頭徹尾でたらめな作品でしたが、しっかりと大人のモヤモヤにも答えてくれる痛快な作品でした。▼大長編 タローマン万博大爆発の公式HPはこちら⇨https://taroman-movie.asmik-ace.co.jp/▼アートのミームの岡本太郎回はこちら前編⇨https://open.spotify.com/episode/3BMEnELd6YZul97FY0onT7?si=ahKPQuOjSxa63nhLSzwP5Q後編⇨https://open.spotify.com/episode/4ByccfefpXmx7tD4n8YtSc?si=o5Co0mlhRpqboY2o4w17Aw▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
2週に分けてフリートークで好きな映像作品を話します。今回は〆太郎が好きなストップモーションアニメ「Bead Game」について。ビーズをひとつひとつ動かしてコマ撮りを行い、生命の進化を表現した作品です。▼エピソードで紹介した作品はこちらBead Game (1977)⇨https://www.nfb.ca/film/bead_game/▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
2週に分けてフリートークで好きな映像作品を話します。今回は染谷さんが好きなイームズ夫妻の「Powers of Ten」について。極小から極大の世界を旅するサイエンティフィックな作品です。▼エピソードで紹介した作品はこちらPowers of Ten™ (1977)⇨https://youtu.be/0fKBhvDjuy0?si=vn7ofVvGhtAnPJXL▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
鎌倉時代を代表する仏師として活躍し、今なお人々を魅了する運慶。東京国立博物館で開催され、傑作とされる国宝「無著 ・世親菩薩立像」をはじめ、7軀の国宝仏が一堂に展示される運慶展に出かけてきました。▼本展のHPはこちら⇨https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2706▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
2025年7月18日から9月28日まで千葉県立美術館で開催している「高島野十郎展」に行ってきました。大正時代から昭和70年代にかけて活躍した画家で、ぬるりとして色っぽく、迫真的な画風が持ち味。個人的には田中一村と同じくらい人気が出てもおかしくない作家だと思いました。▼エピソードで紹介した作品はこちら絡子をかけたる自画像⇨https://virtualmuseum.fukuoka-kenbi.jp/yajuro/75/からすうり⇨https://fukuoka-kenbi.jp/blog/2019/1013_10946/蝋燭⇨https://fukuoka-kenbi.jp/reading/2013/0828_90/▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
染谷さんが「大人の自由研究」でゾートロープ(回転覗き絵)を作りました。目の錯覚に興味が出た染谷さんは、ゾートロープを魔改造して錯視の実験を始めます。その結果見えてきたものとは……。▼エピソードで紹介した「Flashed Face Distortion Effect」の動画はこちらhttps://youtu.be/wHX3tXi6bSg?si=M1SAie57fgF5MuEq▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリが著書「サピエンス全史」の中で提唱している「認知革命」と美術の関係性について話します。認知革命とは、「人類が高度な言語能力と抽象的な思考力をもとに、架空の物語や神話など、現実には存在しない概念を共有する能力を手に入れた」出来事です。これにより、人類は高度で大規模な社会を形成できるようになり、美術は抽象概念の共有に活用されていきました。今回は、2025年7月15日から10月26日まで国立近代美術館で開催されている「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」ともリンクした内容になっています。▼参考にさせていただいたYouTube「オカモトの歴史実況中継」サピエンス全史 #2 │認知革命 【じっくり解説】はこちらhttps://youtu.be/HjM7MjeREoU?si=EYr_GJ60V7OrzJCx▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
今回は、2025年7月15日から10月26日まで国立近代美術館で開催されている「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」の感想です。戦後80年の節目となる年に開催され、280点の豊富な作品や資料から、視覚的な表現が戦争とどのように関わってきたのかを考察する展覧会です。視覚的な表現は物語を強調して、人々はその物語を信じて行動していく。美術や写真の持つ、良くも悪くも大きな影響力を感じられる展示でした。▼本展のHPはこちらhttps://www.momat.go.jp/exhibitions/563▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
2025年7月16日〜9月17日まで、六本木の森アーツセンターギャラリーで開催している「トーベとムーミン展 ~とっておきのものを探しに~」を鑑賞してきました。アートのミームでも4回にわたりトーベ・ヤンソンの生涯を紹介してきましたが、彼女の画業の素晴らしさが分かる充実した展示内容でした。▼本展のHPはこちらhttps://tove-moomins.exhibit.jp/▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
少し長めのお休みをいただいて、戻ってきました。再び更新を続けていきます。引き続きアートのミームをよろしくお願いいたします。▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
アートのミームは少し長めの夏休みをいただきます。次回更新は8月11日の予定です。少し間が空いてしまいますが、再び更新していきますので、引き続きアートのミームをよろしくお願いいたします。▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!
今回はパナソニック汐留美術館で開催されていた「オディロン・ルドン ―光の夢、影の輝き」の感想を話します。ポスト印象派の時代に、象徴主義の画家として活躍したルドン。黒の時代から色彩の時代まで、生涯をなぞるように多彩な作品が展示されていました。▼オディロン・ルドン ―光の夢、影の輝きの公式サイトはこちら⇨https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/25/250412/▼お便りや感想は各プラットフォームのコメント欄にご記入ください▼ジングル音声:音読さん▼染谷昌宏のプロダクトレーベル「sugata」https://www.someya-shouten.jp/※美術ファンのゆるゆるトークですので、一部事実と異なる場合もあります。ご容赦ください!






