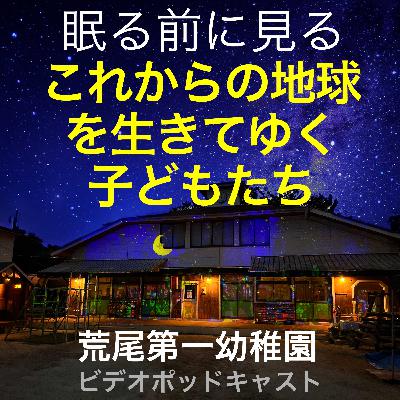Discover これからの地球を生きていく子どもたち【寝る前に見る動画】
これからの地球を生きていく子どもたち【寝る前に見る動画】

22 Episodes
Reverse
園庭に用意していた絵の具の環境に近づき、絵画が始まりました。
絵を描いている場面が発展していく様子を解説していますが、他の遊びやプロジェクト活動の広がりと深まりにも通じるものがあります。
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(幼稚園教育要領)
豊かな感性と表現
心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、意欲をもつようになる。
ロボット作りを頑張っている子どもたち。
表面上、今はそこまで大きな変化はありませんが1つ1つのエピソードを丁寧に見ていくと、こだわりを持って作っていく姿、言葉を使って伝えようとする、言葉で伝わらない時にはどうやって伝えるのかを考え直す姿など、子どもたちの成長を大きく感じることのできる場面でした。
作品を作ることが目的ではなく、作る過程が大切だと改めて感じさせられました。
・自立心
・思考力の芽生え
・言葉による伝え合い
幼児教育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
最近の工房の遊びの様子です。
物を置き、使えるようにすることで様々なことに気づき、少しずつ変わっていく遊び。
幼児教育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
自然物を使った「顔」。
スポイトを使って色を垂らす。
絵の具遊び。
土粘土の重さを量る。
天秤でバランスをとる。
年長組 ドッジボールでの育ちの場面。
年中組がドッジボールの参加することが増えてきました。そこでルールを丁寧に教えてくれたり、良いところを認めてくれる姿が見られます。年々、受け継がれている子ども達の育ちの姿を感じる場面です。
・健康な心と体
・自立心
・道徳性・規範意識の芽生え
・社会生活との関わり
・言葉による伝え合い
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」でみると、この5つを感じる場面でした。
針のついてない作業用の注射器を園庭の環境に置きました。年少組の子供たちは初めて扱うものです。水を入れようと思っても、なかなか思い通りになりません。ある子がスポイトで先から水を入れることに成功し、そこから水道で水を入れる方法に広がっていく過程です。
注射器を引いて吸引する方法は3歳児でも出来ないことではありませんが、少し力が必要です。これから身体が育って、その動作が簡単になった時、新しい思考が生まれていくのだと思います。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(6) 思考力の芽生え
ロボットを話せるようにすることができた年中組の子どもたちは、次に歩かせるようにしたいという思いを抱くようになりました。
どうやって歩かせるのかを考えると、車輪がいい‼︎とすぐにひらめき、園内を探すことにしました。車輪をどうやって足につけるのか…色々考えて今はガムテープになっています。
映画作りに入るまでには、まだまだやることがあると思っている様子で、今も毎日頑張って作っているところです。
幼児教育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
年長児、年中児、年少児 みんなが使う場所の環境構成についてです。
転がす、吊るす、揺れる、磁石、光と影と色、風と音、振動、風と絵の具
いろいろなモノに関わる環境を作っています。
そこから心が動き、気づき、考え工夫し、表現や学びにつながります。
モノはどう使うかの他に、どこに置いてあるのか、いつ置くのか、
という時間と場所も重要と思います。
幼児教育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
あやとりは粘り強く取り組む態度が必要です。
やり方がわからない時、友達に聞くことが必要になります。
練習して出来たことの積み重ねが自立心を育んでいきます。情報収集の力、思考力の芽生え、形への感覚、人とのつながり、たくさんの育ちの姿が見られます。
あやとりの遊びは、仲の良い友達以外とも関わる機会を作ります。友達の関係を作る大切な環境になります。缶蹴りやケイドロと同じように、遊び仲間と遊ぶ体験が子どもたちの世界を豊かにしていくと荒尾第一幼稚園では考えています。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
年中組リレーを始める時の様子です。この日はいつも走っているコースにケイドロの人たちがいたので、「ここではできないじゃん」と話していました。誰かがコースの提案をすると、その意見に対して懸念すること意見として伝えます。するとまた新しい提案が出ます。4歳児たちの会話のやりとりに、他者への配慮・関心・気遣い、思いやり等を感じました。
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
最近の年少組の様子です。
自分が想像したことを話すこと、友達が言っていることを聞いて、それを自分なりの言葉で表現することが楽しい時間だったのかなと思いました。
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(幼稚園教育要領)
(9) 言葉による伝え合い
先生や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。
最近の年中組の外遊びの様子です。今は泥団子作りやリレー、砂場での遊びを楽しんでいます。量りで『泥団子の体重をはかる』というのがクラスの中でも浸透していて、毎日行われています。自分たちで遊びを進める楽しさも感じているところで、年長組の真似をしながら、なんとか形になるようになってきました。
3日間に渡って形についての活動をしました。
形を探す、作る、デザインする。探す活動では、見方を変えることで新たな形が見えることを発見しました。そして子ども達は、自分達で形を作る面白さを感じていました。また、それを見て「〜みたい」とイメージしたことを言葉にしていた子ども達。抽象的な形だからこその会話だったように感じます。そしてそこが活動の集中へと繋がるポイントだったのかなと思います。
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
4歳児クラス年中組が、考えて、工夫し、協力して自分たちの思うロボット製作している様子です。
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
園庭に垂らした不織布が雨に濡れて、絵の具の痕跡が鮮やかに乗るようになりました。そこに三原色の色水スプレーも吹きかけます。やがて誰かが水たまりに絵の具を垂らすし、マーブリングのようになることを気がつきました。それから遊びが爆発的に楽しくなりました。
豊かな感性と表現
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
秋の自然を見つけ、季節の変化を感じることをねらいに葉っぱや枝、木の実を自分たちで拾いアートにしました。並べて貼ることで綺麗なものを作ったり、自分の中でお話を考えて作ったり、色々な姿が見られました。大きな絵を友達と一緒に描くということも楽しんでいて、いい時間を過ごせました。
自然との関わり・豊かな感性と表現
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
排水パイプを2つ繋げて、水を流す遊びを行っていました。パイプを繋げるために土で固める・深く掘った穴に水を溜めるなど、2人で協力し考えながら長い時間遊んでいました。砂場での遊びは、「深い学び」がたくさんあります!〈健康な心と体・自立心・協同性・思考力の芽生え・言葉による伝え合い〉
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
活動内容を写真で紹介する動画です。
北風と太陽のお話を聞いてからごっこ遊びをしました。「お話では太陽が勝つけど、今日はみんなの工夫次第では北風も勝てるかもしれない」というごっこ遊びにしました。友達と話しながら色々な動き、表現が見られました。その後、旅人が楽しく旅をできるようにみんなにサポートをお願いしました。太陽になったり風になったり川を作ったり忙しそうな子どもたちでした。
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
5歳児クラスが、4歳児クラス、3歳児クラスを招待してハロウィンイベントを開催しました。内容は仮装してiPadで写真を撮るコーナー。参加者が製作する「カバチャ作り」「モンスター(デカルコマニー)」のワークショップ。この日のために数日間、かけて小道具、内装など準備しました。各場所で年長組の責任感・自立心などの姿が見られました。
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
最近の年長組の様子を写真で紹介します。ドッジボールのコート作りの中で見らた「数量や図形の感覚」「思考力の芽生え」「協同性」「自立心」の姿です。
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。
最近の荒尾第一幼稚園を写真で紹介します。年少組の様子です。
テロップは、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」へ繋がるであろうものを表示しています。
子どもたちは遊びの中で学び、成長していきます。
幼児教育・保育は幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行います。