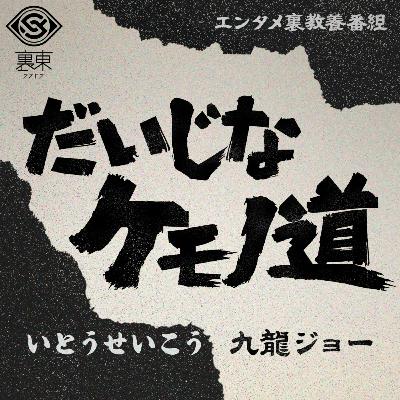Discover だいじなケモノ道
だいじなケモノ道

だいじなケモノ道
Author: ウラトウ
Subscribed: 67Played: 187Subscribe
Share
© ウラトウ
Description
■「だいじなケモノ道」
エンタメ道の裏側=ケモノ道を語り継いでいく、エンタメ裏教養番組『だいじなケモノ道』。いとうせいこうと九龍ジョーの二人がテレビ、舞台、音楽ライブなどのエンタメを支える裏方ゲストを迎え、時代を作った演出や革命を起こした技術など、いまだ明るみになっていない類まれなる仕事に光を当てていく。
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
エンタメ道の裏側=ケモノ道を語り継いでいく、エンタメ裏教養番組『だいじなケモノ道』。いとうせいこうと九龍ジョーの二人がテレビ、舞台、音楽ライブなどのエンタメを支える裏方ゲストを迎え、時代を作った演出や革命を起こした技術など、いまだ明るみになっていない類まれなる仕事に光を当てていく。
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
26 Episodes
Reverse
今回は特別編として『BRUTUS』No.994紙上にも掲載された鼎談の模様をお送りします。お相手はヒップホップユニット"Dos Monos"として活動しながら、ポッドキャスト番組『奇奇怪怪』を手がけるTaiTanさん。『だいじなケモノ道』のヘビーリスナーであるという彼の指名で実現した、『奇奇怪怪』の書籍第2弾発売を記念する現代の“おしゃべり”談議です。情報過多が進み、ランキングの機能しないこれからの時代のカルチャーにおいて、最も重要な役割を担う「編集」。それを"一つ一つ細かくピンセットで摘むような手つきできちんとさばいている"『奇奇怪怪』と、これまで"エンタメの裏方"についてマニアックに掘り下げてきた『だいじなケモノ道』という、共通する視座をもつ両番組の鼎談ということで、話題は「言語」の起源や「しゃべり」の情報性、「タイパ時代の〇〇」のような流行のスローガンへ安易に回収されない、ポッドキャストそのものの役割にまで深まっていき....
※本記事は『BRUTUS』のWebページでも公開されております。ぜひご一読ください!
https://brutus.jp/podcast_discussion/
写真:Jun Nakagawa
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
テレビというメディアの重大な構成要素である「音声」に関する考察を深めていった結果、話題は"どうしたら発言が使われるか"、ひいては"どうしたら売れるのか"という演者側の技術論まで発展。清水さんによると、実は撮影現場でタレントを"一番よく見ている"のは「音声さん」ではないかということで、特に"ながら視聴"されるようになったテレビで売れていきたい若手が意識するべきポイントを紹介してくださったことをきっかけに、「芸人講座」のような展開に。シーズン1最終回にして、いとうせいこうが当番組で「テレビの技術論」をやりたかった理由の核心へ触れます。エンタメの話題は尽きないなか、シーズン2の構想も飛び出すが....
※シーズン1は今回で一旦区切りとなります。またぜひ、「ケモノ道でお会いしましょう」!
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・00:47【クイズプレゼンバラエティQさま!!】
2004年からテレビ朝日系列で放送されている、さまぁ〜ず司会のクイズバラエティ番組。
・01:30【ガンマイク】
指向性が鋭く、少し離れた場所でもマイクが向いている方向の音をしっかり拾うことができる音声収録機材。
・03:19【Qさま!!いきなりチキンレース】
番組初期に放送されていたロケコーナー。芸人が高さ10mのジャンプ台から、プールに飛び込むまでどれくらい時間が掛かるかを競う企画。
・04:27【主導権を握る人】
前回#23の15:53〜19:40のトークを参照
・07:03【ブーム】
ポールの先端にガンマイクを取り付けて音声収録を行う方法。
・15:32【オフコメ】
オフコメントのこと。アナウンサーやレポーターが画面に登場しないで、声だけが聞こえる状態。
テレビ朝日の技術職として、数々の有名バラエティ番組、「朝まで生テレビ」「報道ステーション」などの報道番組に携わってこられた清水さんをお招きし、テレビというメディアを"音声"の面から支えてきた裏方について掘り下げていきます。実際にテレビに出演する側である二人も、"何十年も一緒に仕事をしてきた"身近な存在でありながら「音声さん」の実態をほとんど分かっていなかったとのこと。番組や出演者のキャラクターを生かしながら、"プロとして恥ずかしいことにならないようにする"職人仕事の繊細さに二人は終始驚かされ、話は"どうしたら音声をオンエアで使ってもらえるか"というような出演者側の技術論にまで発展していきます。さらに「だいじなケモノ道」の配信をご覧になった清水さんによれば、当番組のマイクのつけ方も最適ではないようで....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・06:43【ミキサー】
ミキサーという機材を使い、現場で出演者の声、VTRの音など、音量のレベルを調整する作業。
・06:47【サブ】
副調整室。テレビ、ラジオなどの放送局でスタジオに設けられた音声や映像などを調整するための操作室をいう。略語で「サブ」と呼ばれる。
・06:49【福元昭彦】
テレビ朝日制作技術センターに所属。「虎ノ門」「いきなり!黄金伝説」などのスイッチャーを担当。当番組にもゲスト出演した。
・07:03【ブーム】
ポールの先端にガンマイクを取り付けて音声収録を行う方法
・07:16【無線の技術】
ワイヤレスマイクを使用する際、周波数を設定し、空中を飛び交う電波を利用するので無線の知識が必要となる。
・13:26【サオ】
ブームのポール部分のこと。
・19:30【虎の門】
2001年から2008年までテレビ朝日で生放送されていた深夜のバラエテイ番組。いとうせいこうが定期的にMCを務め、「うんちく王決定戦」や「しりとり竜王戦」などの企画が人気を博した。
・24:52【ゲイン】
ミキサーに入力される音の信号の大きさを調整するもの。
今回は"九龍ジョーがいとうせいこうにどうしても話を聞きたかった"人物、景山民夫について。晩年の不穏な状況もあり今では言及されることが少なくなったものの、『シャボン玉ホリデー』『11PM』『クイズダービー』といった数々の名番組を手掛け、作家としてテレビの歴史を作ってきた人物である景山の知られざる足跡を二人で辿ります。ジャンル横断的に各所へ首を突っ込み、若い才能を発掘しながら次世代へ多大な影響を与えてきた景山の功績は世間の評価以上に大きく、"自身もフックアップされた一人"であると言ういとうによれば、彼は"日本カルチャー界のものすごい台風の目"であり、"「テレビ」というメディアの別の可能性を考えるうえで準拠すべき点"でさえあったとのこと。テレビがかつての勢いを失い、昭和の偉人たちも次々とこの世を去っていくなか、もし景山のような人物がいたとしたら「日本のカルチャー」はどんな姿になっていたのか....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・00:55【景山民夫】
1947年-1998年 放送作家として「11PM」「クイズダービー」「タモリ倶楽部」など数多くの番組を担当。その後、文筆業に進出し、小説家として1988年「遠い海から来たCOO」で直木賞を受賞。
・01:15【宮永正隆】
音楽評論家、プロデューサー。いとうせいこうの早稲田大学時代の同級生。大学卒業後、集英社に入社し「ちびまる子ちゃん」の編集を担当した。
・01:50【ノーライフキング】
1988年出版された、いとうせいこうによる一作目の小説作品。
・02:01【虎口からの脱出】
1986年出版された、景山民夫による満州事変をモチーフにした冒険活劇小説。
・04:09【桑原茂一】
プロデュースカンパニー「株式会社クラブキング」代表取締役。1975年、小林克也、伊武雅刀とユニット「スネークマンショー」を開始。1982年原宿に開店した伝説のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」の代表を務める。他にも「コム・デ・ギャルソン」のショーの選曲を担当するなど活動は多岐に渡る。
・04:16【宮沢章夫】
1956-2022年 劇作家、演出家、作家。1985年、シティボーイズ、竹中直人、いとうせいこうらとユニット「ラジカル・ガジベリベンバ・システム」を結成し活動。その後、劇団「遊園地再生事業団」を主宰し、1992年に発表した「ヒネミ」で岸田國士戯曲賞を受賞。2016年から早稲田大学文学学術院教授を務めた。
・04:37【シティボーイズ】
大竹まこと、きたろう、斉木しげるによるコントユニット。1979年劇団「表現劇場」のメンバーだった3人で結成。
・04:40【竹中直人】
俳優、映画監督。宮沢章夫と多摩美術大学の同級生。竹中がシティボーイズに宮沢を紹介したことで、ラジカルの活動につながっていった。
・04:42【中村ゆうじ】
俳優、タレント。1980年代後半にシティボーイズ、いとうせいこうらと演劇ユニット「ラジカル・ガジベリベンバ・システム」を結成。
・04:47【ピテカントロプス・エレクトス】
1982年原宿に開店した伝説のクラブ。坂本龍一やデヴィッド・バーンなどのアーティストがライブを行った。ファッション、音楽、芸能関係者が集まり最先端の文化交流の場だった。
・07:13【青島幸男】
1932-2006年 作家、作詞家、放送作家、タレントなど様々な分野で活躍。1995年から1999年まで東京都知事を務めた。
・07:42【高田文夫】
1948年生まれ 放送作家、タレント。放送作家として「オレたちひょうきん族」「夜のヒットスタジオ」「ビートたけしのオールナイトニッポン」など数多くの番組を担当。その後、落語家「立川藤志楼」として真打に昇進。ラジオパーソナリティとしても活躍。
・09:11【遠い海から来たQOO】
1988年出版された、景山民夫による海洋冒険小説で直木賞受賞作品。
・10:27【藤原ヒロシ】
プロデユーサー、ミュージシャン。1983年クラブDJとして活動開始。1985年高木完とヒップホップグループ「タイニー・パンクス」を結成。デビューアルバム「建設的」にいとうせいこうが参加した。
・15:45【ロビー・ロバートソン】
10代半ばで後にボブ・ディランのバックバンドとなるホークスに加入。ホークスは1968年ザ・バンドと改名し、1994年ロックの殿堂入りした。
ザ・バンド解散後は映画音楽を手がけマーティン・スコセッシ監督作品を数多く担当した。
・16:54【小黒一三】
1950年生まれ 編集者。マガジンハウスで雑誌「ブルータス」などの編集を担当。その後、独立し雑誌「ソトコト」を創刊した。景山民夫の武蔵中学・高校時代の後輩で、影山にエッセイを依頼し作家デビューのきっかけを作った。
・18:03【大根仁】
1968年生まれ 演出家、映画監督。バラエティ番組のディレクターからキャリアをスタートし、映画「モテキ」ドラマ「エルピス-希望、あるいは災い-」などを監督。ポップカルチャーに造詣が深い。
今回は「ビッグ3」の一角とも言われる巨人・タモリについて。デビューから半世紀にも及ぶこれまでの彼の歴史を、テレビや芸能界自体の変遷と重ね合わせながら、自身もその後継者の一人と目されてきた立場であるいとうせいこうと九龍ジョーが改めて考察していきます。ある意味で"釈迦"の生涯にさえ準えられる極端な転身により、"夜"のアングラ芸人から一躍"昼"の顔になったタモリ。彼は「笑っていいとも」でどんな"笑い"をし、どう振る舞ってきたか。そして「いいとも」以後の令和の時代に、もし彼のような役割を担える人物がいるとしたら、それは誰か。最後にいとうはこれから「テレビ的なもの」が残っていく可能性として、"朝"という時間帯を挙げ....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・02:37【赤塚不二夫】
1935-2008年 漫画家。代表作「天才バカボン」「おそ松くん」「ひみつのアッコちゃん」など。タモリはデビュー前、1975年ごろ新宿の酒場などで宴会芸を披露していたところを赤塚にスカウトされ、赤塚の自宅に居候していた。
・02:35【山下洋輔】
1942年生まれ ジャズピアニスト。1972年、山下がコンサート後打ち上げしていた、福岡のホテルの部屋にタモリが乱入し、芸を披露したことから交流が始まる。この出会いが、後にタモリが芸能界デビューするきっかけとなった。
・03:25【タモリライフ研究会】
いとうせいこうが早稲田大学在学中に所属していたサークル。
・03:47【空飛ぶモンティ・パイソン】
イギリスの伝説的なコメディグループ、モンティパイソンによるテレビ番組。日本では1976年から東京12チャンネル(現テレビ東京)で吹替版が放送された。その際、番組のおまけコーナーにタモリが出演、実質的なデビューだと言われている。
・04:06【藤村有弘】
1934-1982年 「インチキ外国語」の芸を得意とした喜劇人。
・04:55【宮永正隆】
音楽評論家、プロデューサー。いとうせいこうの早稲田大学時代の同級生。大学卒業後、集英社に入社し「ちびまる子ちゃん」の編集を担当した。
・05:26【青島幸男】
1932-2006年 作家、作詞家、放送作家、タレントなど様々な分野で活躍。1995年から1999年まで東京都知事を務めた。
・05:35【大橋巨泉】
1934-2016年 音楽評論家、放送作家としてキャリアをスタート。1960〜80年代、司会者として「11PM」「クイズダービー」など多くの人気番組に携わった。
・05:38【前田武彦】
1929年-2011年 タレント、司会者、放送作家。放送作家として「シャボン玉ホリデー」を立ち上げ1960年代ごろからタレント活動が本業となり「夜のヒットスタジオ」の司会を務めた。
・07:01【景山民夫】
1947年-1998年 放送作家として「11PM」「クイズダービー」
「タモリ倶楽部」など数多くの番組を担当。その後、文筆業に進出し、
小説家として1988年「遠い海から来たCOO」で直木賞を受賞。
・07:25【ばらえてい テレビファソラシド】
NHK総合テレビで1979年から1982年まで放送、タモリがレギュラー出演していたバラエティ番組。タレントだけでなく学者や教授がゲスト出演する知的エンタテインメント番組として評判になった。
・07:42【今夜は最高!】
日本テレビで1981年から1989年まで放送されていた、タモリが司会のトーク・コントバラエティ番組。
・07:45【高平哲郎】
1947年生まれ 放送作家、編集者、評論家。タモリとデビュー前から交流が深く、放送作家として「今夜は最高!」「笑っていいとも!」などを担当。
・08:57【向田邦子賞】
優れたテレビドラマの脚本作家に与えられる賞。バカリズムは「架空OL日記」で2017年度受賞。
・10:32【スター千一夜】
フジテレビ系列で、フジテレビの開局日である1959年3月1日から
1981年9月25日まで約22年半放送されていたトーク番組。
・11:37【宇多丸】
1965年生まれ ラッパー、ラジオDJ、ライターで。ヒップホップグループ「ライムスター」のMC。
・11:39【アフター6ジャンクション】
2018年からTBSラジオで平日よる6時から放送されている番組。最新カルチャーの紹介や分析、注目アーティストのスタジオライブなどの企画を盛り込んだ「文化的情報娯楽番組」。略称である「アトロク」は、いとうせいこうの提案によるもの。
・13:40【タモリのオールナイトニッポン】
1976年から1983年までニッポン放送で放送されていた、タモリがパーソナリティのラジオ番組。いとうせいこうは早稲田大学在学中にADを務めていた。
・16:11【極楽TV】
景山民夫によるテレビ番組をテーマにしたエッセイ集。
報道番組のフロア統括もされている福岡さんによると、常に予想外の出来事に対応しなければならず、些細な不体裁が大ごとになる報道は、バラエティーとは比べ物にならないほどの慎重さやその場での瞬発力が求められるとのこと。放送の前から、"カメラに映らない" "現場にいる人間でさえ気づかない"、最善の準備をしている「裏方」の繊細な仕事に終始二人はうならされます。そして後半では、福岡さんが自ら"原点"と語る、「完璧なカンペ」に至るききっかけとなったある「失敗」を巡るエピソードに。新人時代に初めてフロアを担当した新春特番中、ある大物タレントを前に緊張して臨んでいた福岡さんのカンペが、すさまじい突風によって吹き飛ばされてしまい....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・02:31【サブ】
副調整室。テレビ、ラジオなどの放送局でスタジオに設けられた音声や映像などを調整するための操作室をいう。略語で「サブ」と呼ばれる。
・04:11【TK】
タイムキーパーの略称。テレビやラジオの番組制作において、時間の進行を管理する仕事。
・10:34【フリーカンペ】
台本の進行以外に、その場の展開に応じて、出演者に手書きで指示、提案をするカンペのこと。
1993 年に入社された制作会社でADを担当後、フリーとなり、数々の人気番組へディレクターとして携わってこられて御年54 歳。現在は『くりぃむクイズ ミラクル9』『櫻井・有吉 THE 夜会』などのバラエティや、報道番組でのフロア統括をされている福岡さん。何年も一緒に生放送をしてきたいとうせいこうによると、福岡さんのカンペ操作は「完璧」であり、これまで一度も失敗がないとのこと。無数の要素をふまえて一文字単位でカンペを調整をしたり、サブの指示の及ばない箇所をフォローしたりと、出演者に最も近い「現場監督」の繊細な職人仕事を紐解いていきます。後半では、福岡さんが収録現場に持参してくださった"ディレクター業務についてまとめた資料"のあまりに行き届いた内容から、二人は「いかに出演者の生殺与奪がフロアディレクターに握られているか」という結論にいたり....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・01:57【虎の門】
2001年から2008年までテレビ朝日で生放送されていた。深夜のバラエテイ番組。いとうせいこうが定期的にMCを務め、「うんちく王決定戦」や「しりとり竜王戦」などの企画が人気を博した。
・03:45【サブ】
副調整室。テレビ、ラジオなどの放送局でスタジオに設けられた音声や映像などを調整するための操作室をいう。略語で「サブ」と呼ばれる。
・11:04【TK】
タイムキーパーの略称。テレビやラジオの番組制作において、時間の進行を管理する仕事。
・11:20【尺調】
決められた放送時間に合わせるために、編集や生放送の現場で調整を行うこと。
・13:58【フリーカンペ】
台本の進行以外に、その場の展開に応じて、出演者に手書きで指示、提案をするカンペのこと。
・14:00【佐久間宣行】
テレビプロデユーサー。「ゴッドタン」や「あちこちオードリー」などを手掛ける。フロアでカンペを出す姿が放送されることも。
・14:05【藤井智久】
テレビ朝日に所属。プロデユーサーとして「虎の門」「シルシルミシル」「くりぃむナントカ」「マツコ&有吉の怒り新党」などを手掛けた。
・14:05【朝まで生どっち】
「虎の門」で放送されていた、いとうせいこう司会の討論コーナー。「ワールドカップVS Fカップ 興奮するのはどっち?」「天狗VSカッパ 生まれ変わるならどっち?」などをテーマに、意見を戦わせ、視聴者によるモバイル投票の数で決着する。
・18:40【周富徳】
料理人。テレビ東京系「浅草橋ヤング洋品店」に出演しブレイク。料理人の枠を越えて、タレント活動を展開した。
・21:47【福元昭彦】
テレビ朝日制作技術センターに所属。「虎ノ門」「いきなり!黄金伝説」などのスイッチャーを担当。当番組の#6~#8にもゲスト出演していただいた。
今回はテレビや演劇、文芸などの世界におけるキーパーソン「中島らも」について。各所で才能をフックアップしてきた彼の、知られざる足跡を二人で辿っていきます。シティボーイズやいとうせいこうを大阪の芸能界へ呼び寄せた人物でもある中島は、実はダウンタウンが『夢で逢えたら』より前に東京の特番に出演した際の、番組ホストであったとのこと。偶然番組に立ち会っていたいとうは、その時観た40年近くも前になる初期ダウンタウンのコントの光景を今でも覚えており、その記憶から、彼らの中にある"誰も指摘してこなかった"中島らもの影響を感じとるようで.....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・00:28【中島らも】
作家、コピーライター、ミュージシャン。1952年生まれ、2004年死去、享年52歳。1991年刊行、小説「今夜、すべてのバー」で吉川英治文学新人賞を受賞。「笑殺集団リリパットアーミー」を結成し、演劇活動も行った。
・00:33【今夜、笑いの数を数えましょう】
2019年講談社より刊行。いとうせいこうが、宮沢章夫ら「笑い」の世界の第一線で活躍中の6名と、その本質について語り明かす対談集。
・00:52【末井昭】
編集者、作家。元白夜書房取締役編集局長。2014年「自殺」で講談社エッセイ賞を受賞。
・00:55【何がおかしいー笑いの評論とコント・対談集】
2006年、白夜書房から刊行。末井昭による編集。「論座」に連載していた笑いの評論「笑う門には」より全原稿を掲載。上岡龍太郎との対談や、未放送のラジオ音声CDを収録している。
・02:03【笑殺集団リリパットアーミー】
1986年、中島らも、わかぎゑふにより旗揚げされた劇団。初代メンバーは、松尾貴史、ひさうちみちお、鮫肌文殊など。
・04:03【モンティパイソン】
イギリスのコメディグループ。1969年「空飛ぶモンティ・パイソン」がイギリスで放送開始。ナンセンスでブラックな笑いで人気を博した。
・04:46【啓蒙かまぼこ新聞】
1980年代に雑誌「宝島」で連載されていた、中島らも制作による「カネテツデリカフーズ」のシリーズ広告。広告らしからぬ破天荒な内容で、若い世代を中心に話題を集めた。
・05:12【笹野高史】
俳優。1984年シティボーイズ・ショー「コズミックダンスへの招待」の東京公演にゲスト出演。
・09:33【桂吉朝】
落語家。笑殺集団リリパットアーミーの公演「釣天童子」などに出演。
・10:50【藤山寛美】
戦後昭和の上方喜劇界を代表する喜劇役者。松竹新喜劇のスターとして活躍した。
・11:12【小林信彦】
小説家、評論家、コラムニスト。1973年「日本の喜劇人」で芸術奨励新人賞を受賞。映画や喜劇人に関する著作多数。
・12:34【モリタタダシ】
雑誌、書籍などで執筆、編集を手がける。「今夜、笑いの数を数えましょう」の構成を担当。
今回は、演劇とコントにおける「笑い」の違いというテーマについて。テレビコント番組が廃れ、演劇を観る人も劇団数も減少傾向にあるなか、それぞれの形式はどのように変化し、どのようにクロスオーバーしてきたか。シティボーイズや宮沢章夫など、業界の歴史を作ってきた大人物たちの"もはや神話に近い"エピソードの数々から、彼らと実際に活動をともにしてきたいとうと九龍の二人で、その変遷を辿ります。「面白いものが生まれそうな予感はある」世界のこれからについて、注目すべきポイントとは....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・02:07【渋谷コントセンター】
渋谷のユーロライブで定期的に開催しているコント公演企画の総称。演劇とコントが競演する「テアトロコント」や企画公演を行う。
・08:28【宮沢章夫】
劇作家、演出家、作家。1956年生まれ、2022年死去 享年65歳。1985年、シティボーイズ、竹中直人、いとうせいこうらとユニット「ラジカル・ガジベリベンバ・システム」を結成し活動。その後、劇団「遊園地再生事業団」を主宰し、1992年に発表した「ヒネミ」で岸田國士戯曲賞を受賞。2016年から早稲田大学文学学術院教授を務めた。
・08:38【今夜、笑いの数を数えましょう】
2019年講談社より刊行。いとうせいこうが、宮沢章夫ら「笑い」の世界の第一線で活躍中の6名と、その本質について語り明かす対談集。
・08:52【遊園地再生事業団】
宮沢章夫が主宰の劇団。1990年、作品ごとに俳優を集め演劇を上演する劇団として旗揚げした。
・08:59【ラジカル・ガジベリベンバ・システム】
宮沢章夫、シティボーイズ、竹中直人、中村有志、いとうせいこうらによって結成されたユニット。1985年から1989年まで活動した。観劇していた俳優、芸人、ミュージシャン、クリエイターに大きな影響を与えた。
・09:10【竹中直人】
俳優、映画監督。宮沢章夫と多摩美術大学の同級生。竹中がシティボーイズに宮沢を紹介したことで、ラジカルの活動につながっていった。
・09:26【シティボーイズ】
大竹まこと、きたろう、斉木しげるによるコントユニット。1979年劇団「表現劇場」のメンバーだった3人で結成。
・10:13【明日のアー】
「デイリーポータルZ」など、WEBメディアでライターを務める大北栄人が主宰する劇団。
・10:52【三木聡】
放送作家、映画監督、劇作家、舞台演出家。放送作家として「ダウンタウンのごっつええ感じ」「トリビアの泉」などを担当。「亀は意外と速く泳ぐ」「インスタント沼」などで映画監督としても注目を集める。1990年代、シティボーイズライブの作・演出を務めた。
・11:22【ドラマンス】
ラジカル・ガジベリベンバ・システムの前身となるユニット。桑原茂一、宮沢章夫、シティボーイズ、竹中直人、中村有志、いとうせいこう、松本小雪が参加。
・11:24【桑原茂一】
プロデュースカンパニー「株式会社クラブキング」代表取締役。1975年、小林克也、伊武雅刀とユニット「スネークマンショー」を開始。1982年原宿に開店した伝説のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」の代表を務める。他にも「コム・デ・ギャルソン」のショーの選曲を担当するなど活動は多岐に渡る。
・13:02【キッチュ!夜マゲドンの奇蹟】
文化放送で1990年から1992年まで放送されたラジオ番組。松尾貴史がパーソナリティを務めた。
・13:06【ふせえり】
俳優。ラジカル・ガジベリベンバ・システムの後期に参加。「シティボーイズライブ」にも客演経験がある。夫は放送作家、映画監督の三木聡。
・16:33【つかこうへい】
劇作家、演出家、小説家。1948年生まれ、2010年死去 享年62歳。1974年「熱海殺人事件」で岸田國士戯曲賞を当時最年少の25歳で受賞。1982年小説「蒲田行進曲」で直木賞受賞。
・17:29【モンティパイソン】
イギリスのコメディグループ。1969年「空飛ぶモンティ・パイソン」がイギリスで放送開始。ナンセンスでブラックな笑いで人気を博した。
・17:56【ルイス・ブニュエル】
スペイン出身でのちにメキシコに帰化した映画監督・脚本家。シュルレアリスム作品で注目を集めた。
・21:22【井出靖】
音楽プロデューサー、DJ、レーベルオーナー。1980年代、講談社を退社したいとうせいこうと「エンパイアスネークビルディング」を設立。2005年にインディーズレーベル「Grand Gallery」を立ち上げ、ショップ運営も行う。
・23:19【スチャダラパー】
ラジカル・ガジベリベンバ・システムが1986年に上演した「スチャダラ」がグループ名の由来。
・23:25【藤原ヒロシ】
プロデユーサー、ミュージシャン。1983年クラブDJとして活動開始。1985年高木完とヒップホップグループ「タイニー・パンクス」を結成。デビューアルバム「建設的」にいとうせいこうが参加した。
・24:46【砂漠監視隊】
1989年12月にラフォーレ原宿で上演されたラジカル・ガジベリベンバ・システムの最終公演。
・26:43【やついいちろう】
芸人、お笑いコンビ「エレキコミック」で活動。宮沢章夫が主宰する「遊園地再生事業団」の舞台に出演。
・27:02【由利徹】
1950年代半ばからお笑いユニット「脱線トリオ」で活動。解散後は、喜劇役者、コメディアンとして人気を博した。
・27:31【Aマッソ】
宮沢章夫はAマッソを高く評価しており、メンバーの加納愛子と親交があった。
・29:48【十三代目市川團十郎白猿】
2013年「はなさかじいさん」を元に、宮沢章夫が新作歌舞伎の脚本を担当。
・32:28【SAYONARAシティボーイズ】
文化放送で放送中のラジオ番組で、シティボーイズがラジオコントを披露している。
テレビ局の美術デザイナーとして、順調にキャリアを重ねられていった邨山さん。「まつもtoなかい」などの注目番組や「東京2020パラリンピック」という本来のジャンル外の巨大なイベントのデザイン業務に関わられた経験を通して、"テレビのよさ"や"まだテレビにできること"を実感されたとのこと。そして業界全体が衰退していくといわれているなかで、その現場の当事者の口から語られる"テレビというメディアの可能性"に、実際にテレビへ出演する側でもある二人も思わず共感を覚えます。最後には、当番組の趣旨にも関わるテーマである「テレビとYouTubeの違い」について、美術という観点から考察が導き出され.....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・03:23【スターアイランド】
絶景のロケーションで行われる「伝統花火」と「最先端テクノロジー」がシンクロした、未来型花火エンターテインメント。
・06:02【きのーご】
バラエティ番組「ピカルの定理」で大吾(千鳥)が演じたコントキャラクター。今回のゲスト邨山さんが案を出し、デザインを担当した。
・06:20【ロンドンオリンピック】
「トレインスポッティング」などで知られる映画監督のダニー・ボイルが、開会式の芸術監督を務めた。
「SMAP×SMAP」などのバラエティー番組も担当されるようになった邨山さんは、"かっこいいだけでは駄目"な文化に戸惑いながらも実績を重ねられ、「ピカルの定理」では、アニメ制作の経歴を生かしてデザイナーでありながらキャラクター発案まで携わるように。話は"なぜ日本のテレビセットがどんどん派手で豪華なものへ進化していったのか"に関する考察へ発展していきます。実際にそうした現場の「裏方」であった邨山さんによると、それは"ザッピング対策によるものではないか"とのこと。日本人は画面の内容ではなく"明るさ"に目が留まりやすい傾向にあり、業界では視聴者を引きつけるために「画面温度が低い」という用語まで用いられるようで、ある種の強迫観念的に付け足しをしていった結果として、使いもしないテニスラケットや、龍のオブジェといった意味不明な造作物が配置された、他のどの国とも異なる独自のセットが形作られたらしく.....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・01:31【板谷栄司】
「FNS歌謡祭」「僕らの音楽」「SMAP×SMAP」を始め、数々の音楽番組の演出、プロデュースを担当。2022年フジテレビを退社し書道家に転身。
・14:12【マジックミラー号】
アダルトビデオ撮影用の移動スタジオ。トラックの荷台が一面マジックミラーで囲われており、外からは鏡に見えるが、中から見ると外が丸見えになっている。
・17:29【ピカルの定理】
2010年から2013年までフジテレビ放送されていたバラエティ番組。ピース、モンスターエンジン、ハライチ、平成ノブシコブシ・渡辺直美・千鳥などの芸人が出演していた。
2006年フジテレビ入社、美術デザイナーとして「僕らの音楽」「SMAP×SMAP」などの音楽番組やバラエティ番組を担当され、近年では"アートディレクター"の立場として「東京2020パラリンピック閉会式」の企画にも携わられて現在42歳。テレビというメディアを視覚的な面から支えてきた「裏方」の、特殊な仕事を掘り下げていきます。学生時代は、彫刻とアニメについて学んでいたという邨山さん。興味本位で参加した就職説明会で、"想像力次第でどんなものでも作り上げられること"に感銘を受けて飛び込んだテレビの世界では、そうした経験が生きてくるものの、"変わった人ばかり"のディレクターたちの演出を汲みながら、現場での予想外の事態にも対応した「オリジナルなものづくり」を常にしなくてはならず、"異常な瞬発力"が鍛えられていくようで.....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・02:13【僕らの音楽】
フジテレビで2004年から2014年まで放送されていた音楽番組。
・02:47【妹尾河童】
1930年生まれ、グラフィックデザイナー・舞台美術家・エッセイスト・小説家。1958年フジテレビ開局と同時に入社、「MUSIC FAIR」や「夜のヒットスタジオ」などの美術デザインを担当。1980年退社しフリーとなる。
・02:58【越野幸栄】
舞台・美術デザイナー、現在イギリス在住。「FNS歌謡祭」「HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP」「僕らの音楽」など音楽番組を中心に美術デザインを担当。
・02:58【「僕らの音楽」のディレクター】板谷栄司
「FNS歌謡祭」「僕らの音楽」「SMAP×SMAP」を始め、数々の音楽番組の演出、プロデュースを担当。2022年フジテレビを退社し書道家に転身。
今回は出版文化とその「裏方」である編集者について。太田出版元社長であり伝説の編集者 高瀬幸途。氏の関係者たちの証言をまとめた私家版の話題から、高瀬氏の3年間の空白期間、ビートたけしとの出会いと関係、その後の驚きの転身まで。そして菊池寛や蔦屋重三郎、見城徹などの大物出版人たちにまつわる数々の逸話から、売上が激減していくなか"紙の本は本当になくなるのか"を考えます。「人と人が出会いさえすれば、そのはずみで、本は生まれていくものなのではないか」---------- 最後は、講談社社員だったいとうせいこうしか知り得ない、昭和の芸能史に残る"フライデー編集部襲撃事件"の歴史的証言まで飛び出し.....
🐗二人が話していた高瀬幸途氏に関する本
『タカセがいた 異能の出版人 高瀬幸途 追想』(発行 中里雅子 編集 向井徹)
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・01:57【高瀬幸途(たかせ よしみち)】
1948年生まれ、2019年死去 享年71歳。編集者としてビートたけし、哲学者・柄谷行人らの著書を手がけ、太田出版の社長を務めた。
・04:02【野間清治】
1878年生まれ。講談社創業者であり、元報知新聞社社長。「雑誌王」と呼ばれ、昭和前期の出版界を牽引した。
・04:04【斎藤十一】
1914年生まれ。昭和期の編集者で、「藝術新潮」や「「週刊新潮」を創刊。新潮社の専務取締役を務めた。
・04:08【菊池寛】
1888年生まれ。小説家、劇作家。実業家として文藝春秋社を興し、雑誌「文藝春秋」を創刊した。
・07:48【俺の同期】
いとうせいこうは1984年に大学卒業後、講談社に入社。雑誌「ホットドッグ・プレス」などの編集部を経て、1986年に退社。
・08:50【森昌行】
オフィス北野の元代表取締役社長。番組制作会社のディレクターとしてビートたけしと親交を深め、オフィス北野の設立に参加。北野武映画を自社で製作・配給するなど、映画プロデューサーとして活動。
・09:26【雑誌「本人」】
2006年、太田出版より松尾スズキがスーパーバイザーを務める季刊誌として創刊。
・12:13【蔦屋重三郎】
江戸時代後期の出版人。洒落本、狂歌本、錦絵などを多数出版。喜多川歌麿、葛飾北斎、東洲斎写楽などの才能を見出した。
・12:34【山東京伝】
江戸時代後期の浮世絵師、戯作者。
・12:47【吉原細見】
江戸に存在した吉原遊廓についての案内書。店ごとに遊女の名前が記されていた。
・14:39【柄谷行人】
1941年生まれ。哲学者、文学者、文芸批評家。 “哲学のノーベル賞”を目指してアメリカの研究機関が創設した「バーグルエン哲学・文化賞」を2023年アジアで初めて受賞。
・14:45【宮崎学】
1945年生まれ。ノンフィクション作家、小説家。暴力団の組長を父に持ち、自伝的な著作「突破者」でデビュー。以降、暴力団や社会問題を扱った著作を多数発表した。
・15:04【深作欣二】
1930年生まれ。「仁義なき戦い」シリーズで知られる映画監督。太田出版より刊行された小説「バトル・ロワイアル」映画化の監督を務めた。
・15:08【大西巨人】
1916年生まれ。小説家、評論家。従軍経験をもとにした代表作「神聖喜劇」は25年の歳月をかけ執筆された長編で、“戦後文学の金字塔”と評されている。
・15:08【荒井晴彦】
1947年生まれ。脚本家、映画監督。映画「遠雷」「Wの悲劇」「リボルバー」などの脚本を担当。日本アカデミー賞優秀脚本賞、読売文学賞戯曲・シナリオ賞など受賞多数。
・16:39【新谷学】
1964年生まれ。「週刊文春」元編集長。編集長就任後、同誌がスクープを連発させたため、「文春砲」という言葉が流行語大賞にノミネートされるまでになった。
・17:08【見城徹】
1950年生まれ。株式会社幻冬舎代表取締役社長。1975年に角川書店に入社し、編集者として数々のベストセラーを手がける。高瀬と親交が深く、著書「編集者という病」を太田出版から発行した。
・21:54【今すぐ知りたい日本の電力 明日はこっちだ】
2023年3月に刊行された、いとうせいこうの編著作。「再生可能エネルギー」に関わっている方々へのインタビュー集。本に寄せられたメッセージをWEBの特設ページで紹介し、随時更新を行っている。
自由の利くネット配信とは異なり、"1秒=〇円"で成り立つ緊迫感のあるテレビの世界。そのなかで番組の時間管理をするタイムキーパーにとっては、むしろ"何が起こるか分からないということも含めて、ルーティーン(平常運転)であり、綺麗に終わりすぎてもつまらない"とのこと。CMなどの確実性の求められる部分やコンプライアンスとの狭間で、テレビの醍醐味でもある「ヒリヒリ感」「(石炭でいう)ガラ」をいかに残すか。なかば失われつつある、希少な職人仕事の実像に迫ります。デジタル化と機械化が進む時代は、テレビ撮影現場をどう変えるか.....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・01:37【スリラー】
1983年に発表されたマイケル・ジャクソンの楽曲。約14分にわたる大作のミュージックビデオが世界的にも有名。楽曲の収録された同名のスタジオ盤は累計売上約7000万枚と推定され、「歴史上最も売れたアルバム」とされている。
ほとんど給料ももらえない厳しい徒弟制度的な世界で、タイムキーパーのキャリアを始められた橋本さん。番組進行の重責を負いながらCMの管理や放送の"時間割り"をしなくてはならない、非常にストレスフルな業務で磨かれた身体感覚は「ほとんどアスリートに近い」、一般の人とはやや異なるものであるとのこと。なかでも予定調和の通用しないボクシングなどのスポーツ中継や、映像の合成が必要なCGセットを用いた番組では、事故が起きないようにいつも凄まじく気を張り詰めて臨んできたようで....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・07:38【着信御礼!ケータイ大喜利】
2005年からNHKで生放送された視聴者投稿の大喜利番組。スタジオの背景はCGで作成、合成されていた。
フリーランスの"タイムキーパー"として、「お笑いマンガ道場」「 チューボーですよ!」などのバラエティー、 ボクシング世界戦などのスポーツ中継、音楽番組のライブ中継などに携わってこられて、現在いとうせいこうと同じ御年62歳。 テレビ番組の撮影を「時間割り」や「テンポ感」から成り立たせる作り手として、ディレクターのすぐ隣りで"V出しの絶対権限を握る"、もはやディレクションに近い関与の仕方や、番組制作の最後の工程で発揮される特異なスタンスを掘り下げていきます。いとうは音楽専門の衛星放送「スペースシャワーTV」の開局時から親交があったものの、橋本さんがどういった業務をされているのか、実は長きに渡りなかなか分からなかったとのことで....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・01:43【お笑いマンガ道場】
1976年から18年に渡り放送された中京テレビ製作のマンガ大喜利番組。鈴木義司などの漫画家や車だん吉、川島なお美などのタレントが出演した。
・09:34【サブコン】
副調整室。テレビ、ラジオなどの放送局でスタジオに設けられた音声や映像などを調整するための操作室をいう。略語で「サブコン」や「サブ」と呼ばれる。
・11:11【Qシート】
テレビやラジオ番組において、どのタイミングで提供クレジットが入り、CMや各コーナーへ行くのかなどの指示が記載された一覧表。
・16:05【チューボーですよ!】
1994年からTBSで放送された、堺正章が司会の料理バラエティ番組。
・17:24【ノンリニア編集】
テープを使用せず、ハードディスクなどに映像を取り込み編集する方法。リニア編集に比べ、編集箇所を自由に選択でき、即座に追加・削除・修正・並べ替えなどを行うことができる利点をもつ。
・20:13【紙のやつだった】
1990年代中頃まで、テロップは手書きや写植で紙に印字されたものを使用していた。
今回はテレビの世界における「芸人」の立ち位置について、業界黎明期から現代までの変遷を分析していきます。それまでの常識を覆しチャリティー番組の司会をいち早く引き受けた萩本欽一、上方の笑いを牽引していた絶頂期に突如芸能界を引退した上岡龍太郎ら、巨星たちが果たしてきた役割とは? そしてフリオチといった文脈がどんどん簡略化され、"TikTok化"していくテレビというメディアは、どういった未来を導くのか....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
※番組内の用語注釈
・02:33【中村ゆうじ】
俳優、タレント。1980年代後半にシティボーイズ、いとうせいこうらと演劇ユニット「ラジカル・ガジベリベンバ・システム」を結成。先鋭的な舞台で、演劇界、お笑い界を席巻した。
・03:31【トニー谷】
1917年生まれ、銀座出身の舞台芸人。毒舌な芸風でラジオ、テレビの司会で人気を博した。
・04:20【大橋巨泉】
1934年生まれ。音楽評論家、放送作家としてキャリアをスタート。1960〜80年代、司会者として「11PM」「クイズダービー」など多くの人気番組に携わった。
・06:37【上岡龍太郎】
1942年生まれ。元漫才師、元タレント。「探偵ナイトスクープ」「鶴瓶上岡パペポTV」など司会者として活躍。2000年に芸能界を引退した。
・07:53【横山パンチ】
上岡龍太郎の旧芸名。1959年にトリオ芸人「漫才トリオ」として大阪でデビュー。
・08:30【EXテレビ】
1990年から放送された深夜番組。大阪版の司会は上岡龍太郎、島田紳助が務めた。「低俗の限界を探る」など数々の実験的な企画を放送。
・08:32【パペポ】
1987年から放送された読売テレビ製作の「鶴瓶上岡パペポTV」笑福亭鶴瓶と上岡龍太郎の2人が、台本・打合せなしで、トークを行う番組。
・09:00【開運!なんでも鑑定団】
1994年からテレビ東京で放送中のバラエティ番組。EXテレビで放送した「家宝鑑定ショー」をルーツとしている。
・14:19【虎の門】
2001年からテレビ朝日で生放送された深夜番組。いとうせいこうが定期的にMCを務め、「うんちく王決定戦」や「しりとり竜王戦」などの企画が人気を博した。
・14:25【たほいや】
1993年からフジテレビで放送された辞書を使用して行うゲーム番組。編集者の川勝正幸やデッツ松田、作詞家の森雪之丞など多くの文化人が出演していた。
・16:16【青島幸男】
1932年生まれ。作家、作詞家、放送作家、タレントなど様々な分野で活躍。1995年から1999年まで東京都知事を務めた。
・17:33【宇川直宏】
現代美術家、VJ、文筆家など。ライブストリーミングスタジオ兼チャンネル「DOMMUNE」の代表を務める。
・19:29【シルシルミシル】
2008年からテレビ朝日で放送、くりぃむしちゅーが司会を務めたバラエティ番組。様々な分野の検証や飲食チェーンや食品メーカーの特集企画を行った。
バラエティーの舞台裏を中心に掘り下げてきた#6#7の話を受け、今回はそうした"テレビ撮影技術の真髄"であるスポーツ中継にまつわる秘話が語られます。素早く飛んでいくボールを正確に映さなくてはならない野球中継、多い時では70~80台ものカメラを要するゴルフ中継、ルールや選手の特徴まで把握しないと成立しないサッカー中継。どれも結局は"スイッチャー"が取り仕切り、編集し、ディレクションしているということで、いとうと九龍の二人は「テレビを本当の意味で裏回ししているのはスイッチャーである」という結論に至る。そして後半では、今年定年を迎えられる業界の大ベテランである福元さんへ、番組趣旨にも関わる「YouTubeに対してテレビとはどういう存在か」という質問をぶつけ....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
協力:Amazon Music Studio Tokyo
※番組内の用語注釈
・08:39【ノンリニア】
テープを使用せず、ハードディスクなどに映像を取り込み編集する方法。リニア編集に比べ、編集箇所を自由に選択でき、即座に追加・削除・修正・並べ替えなどを行うことができる利点をもつ。
・10:56【ユニ】
スポーツの国際大会などで、日本の放送局が独自にカメラを入れ撮影した映像。中継車で国際映像と切り替えて、日本に向けて衛生回線で本社に送る。
テレ朝系列で2004年から放送されている、民放で最も高視聴率の報道番組「報道ステーション」でもスイッチャーを担当されていた福元さん。当番組でキャスター古舘伊知郎がみせていた、"テレビ芸の極致"ともいうべき視聴者を引き付ける特異なテクニックや振る舞いは、現場のスタッフだった福元さんにとっても非常に印象に残っているとのこと。「報ステ」「朝生」などの伝説的な番組の数々にまつわる技術的な裏話から、"すべての芸人が参考とするべき"撮影スタッフの視点が次々に語られていきます。後半では、いとうせいこうがテレ朝の技術マンたちに脈々と引き継がれてきた特有の"イズム"を感じるという、最近のバラエティー番組にまで話題が発展し....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
協力:Amazon Music Studio Tokyo
※番組内の用語注釈
・06:08【半分くらいあげる】
バラエテイ番組などにおいて、音声スタッフがミキサーでリアクションをしたり、話をしそうな演者のレベルを最大ではなく半分くらい上げている状態。
・06:39【あたまがけ】
音声のレベルが上がっていないため、コメントの最初が視聴者に聞こえていない状態。
・08:57【報道ステーション】
2004年からテレビ朝日をはじめANN系列で生放送している報道番組。番組開始から2016年まで古舘伊知郎がキャスターを担当した。
・11:06【フリ原】
ニュース番組において、キャスターがVTRへ繋ぐ、ふるためのきっかけコメントが書かれた原稿。
・12:09【久米宏】
「報道ステーション」の前番組である「ニュースステーション」でキャスターを担当。
・15:36【ワーク】
カメラでズームインやズームアウトなどの動きをつけること。
・17:05【メモリー】
ワイプの位置や大きさなどを記憶させる装置。
テレビ朝日技術局に所属し、「いきなり!黄金伝説。」などのバラエティー、「ニュースステーション」などの報道番組、スポーツ中継などに携わってこられて現在御年59歳。前回登場いただいた関口さんのお弟子さんにあたり、技術職のなかでも"スイッチャー"という、裏側でカメラの割り振りを決める業務を担当されてきた福元さんは、いとうせいこうにとって"テレビの世界を支える、重要な下部構造の存在"に気づかせてくれた人物であるとのこと。書籍『職人ワザ!』でも彼を取り上げているいとうと九龍が、作り手と視聴者の両方の視点を組み合わせるスイッチャーの「どういう画を選ぶか」「生放送をどう成り立たせるか」、特殊な思考を掘り下げていきます。いとうはバラエティー番組でMCをしていた際、スイッチャーだった福元さんから、まるで"銃口を突きつけるような"スイッチングによって、なかば無理やりギャグを引っ張り出されたことがあるようで....
■番組概要
毎週木曜日 最新話配信
出演:いとうせいこう、九龍ジョー
作家:竹村武司
ディレクター:中内竜也
プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
協力:Amazon Music Studio Tokyo
※番組内の用語注釈
・01:17【虎の門】
2001年から2008年までテレビ朝日で生放送されていた深夜のバラエテイ番組。いとうせいこうが定期的にM Cを務め、「うんちく王決定戦」や「しりとり竜王戦」などの企画が人気を博した。
・01:27【職人ワザ!】
2005年に新潮社から発売された、いとうせいこうの著書。扇子づくり、江戸文字からスポーツ刈りの達人まで、様々な職人の「ワザの秘密」を伝えるルポルタージュ。今回のゲスト、福元さんもスイッチャーとして紹介されている。
・02:45【師匠の関口】
第1回のゲスト、元テレビ朝日のカメラマン・関口光男さん。
・02:56【サブ】
副調整室。テレビ、ラジオなどの放送局でスタジオに設けられた音声や映像などを調整するための操作室をいう。略語で「サブ」と呼ばれる。
・04:30【朝まで生どっち】
「虎の門」で放送されていた、いとうせいこう司会の討論コーナー。「ワールドカップVS Fカップ 興奮するのはどっち?」「天狗VSカッパ 生まれ変わるならどっち?」などをテーマに、意見を戦わせ、視聴者によるモバイル投票の数で決着する。
・07:07【井筒さん】
映画監督・井筒和幸さん。「虎の門」では、映画を自腹で鑑賞し、評論する「こちトラ自腹じゃ!」のコーナーを担当。
・07:14【デカカメ】
スタジオ収録で主に用いられる大型のカメラ
・07:59【T D】
テクニカルディレクター。技術スタッフをまとめる現場責任者で、スイッチャーと兼務することが多い。