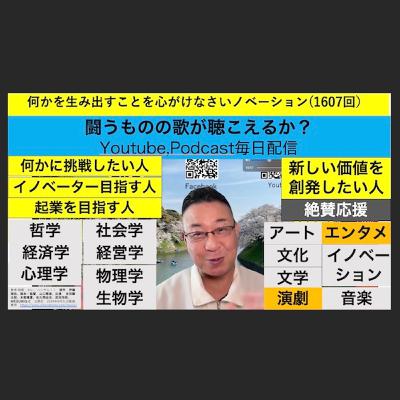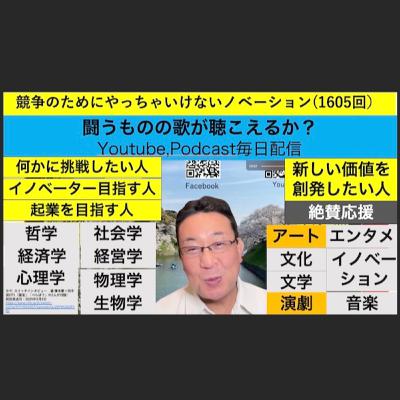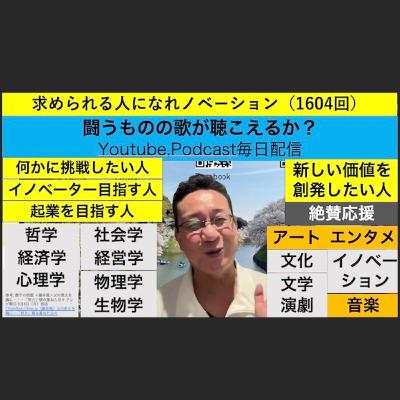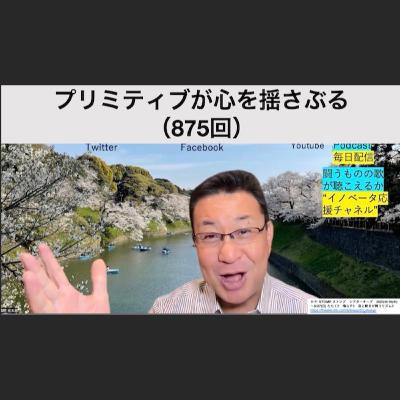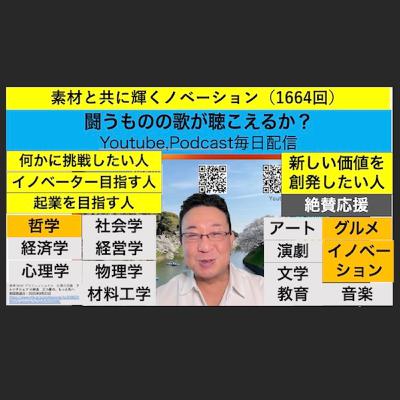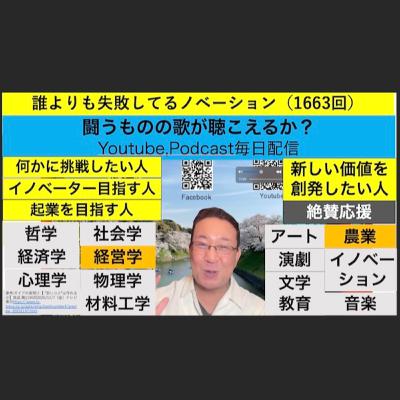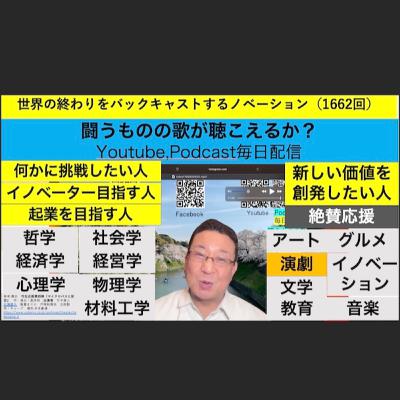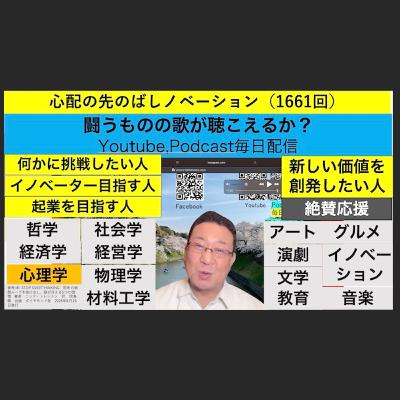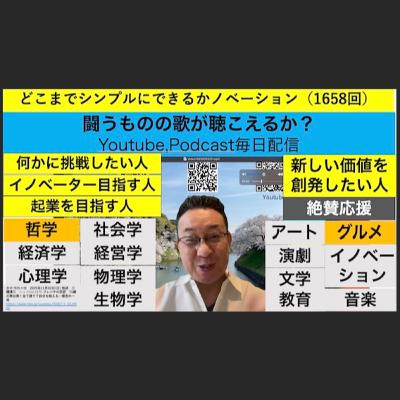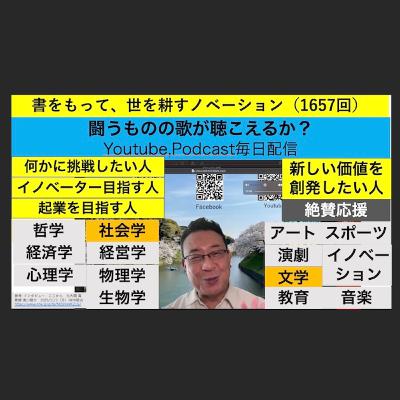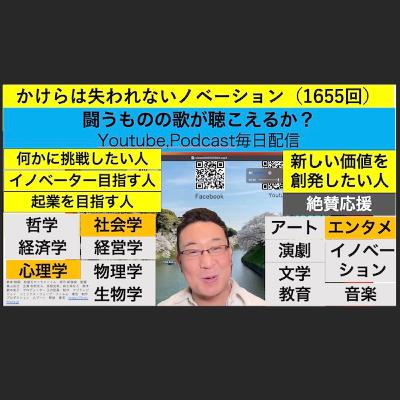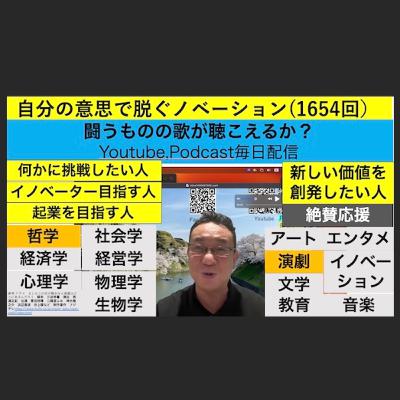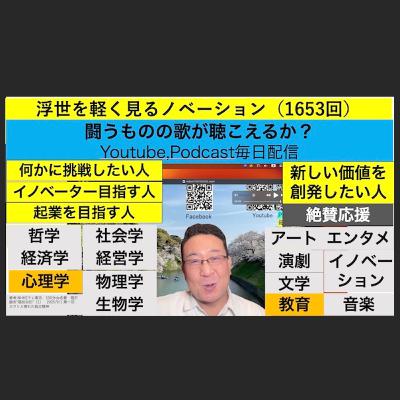界面を創るノベーション(1665回)
Description
安宅和人さんの書籍:"風の谷」という希望 残すに値する未来をつくる"に感動し、また自分で考えさせられました
"そもそも人の少ない疎空間において文化・価値創造を実現するためには、この「異質の共存と偶発的な相互作用」という原理を都市以上に意識的に設計に組み込む必要がある。
それは単なる物理的な空間設計だけでなく、人々の活動や交流のパターンも含めた、総合的な「界面」の設計となる。
このような異質との出会いは、一時的な接触では真の価値を生まない。それは時間をかけて熟成され、土地に根付いていく必要がある。
この界面の設計と出会いを積極的に仕掛けていくこと、これこそが疎空間における文化・価値創造の核心だ。"
ここから私は思いました
1、異質の共存
自分軸と他人軸
2、偶発的な相互作用
心理的安全性
3、界面という仕組み
セーフティネット
1、異質の共存
田舎育ちの私は、地方などの疎空間こそがこれからの風の谷という名の希望になってほしいと、思いながらも、何もできていない自分に歯痒さを感じています
都会に出て、イノベーション活動をこれまでやって来て、本当に思うのは、シュンペーターの言うように異質なものが混ぜ合わさることで、新結合が起きて、新しい価値が生まれるなあということです
都会には異質なものが沢山集まっているので、やろうと思えば、異質が共存する世界は作りやすいと思うのですが、疎空間にどうやって異質を共存させられるのか?
一つ思ったのは、私が企業でいつも行なっているやり方として、個人の内面的な情熱の源に焦点を当てれば、自ずと、個人個人はめちゃくちゃ個性のある多様性と言えるのではないかと言うことです
会社の中でイノベーション活動をすると、同一の環境下なので面白いアイディアが出てこないと嘆かれるのですが、それは、会社という他人軸だけが出てる状態で、自分軸を自然に隠しちゃってるから、ということをよく思います
同じように、自分軸に焦点を当てることができれば、きっと疎空間にいる方々自身がそもそも多様性の共存になってるということも言えるのでは?と思いました
2、偶発的な相互作用
これはまさにセレンディピティのことを言われているかなあと思いました。交流会やマッチングイベントなど、さまざまな仕掛けづくりもあると思いますが
私が思ったのは、1でお話しした自分軸の分人を、出すことがなかなか難しいのではないか、ということです。
どうしても交流会などに行くと、他人軸の分人中心になってしまい、また多様性が失われてしまうこもともあるのかなと
ということは、なんとか自分軸をさらけ出せるような、プロジェクトアルキメデスではないですが、心理的安全性を担保させてくれる仕掛けづくりこそが大切なのではないかと思いました
3、界面という仕組み
それらの相互作用を活性化させるのが界面という仕組みということに、これまた嵌合してしまったのですが
そこには、きっと、自分の自分軸に気づき、それを心理的安全性のもとで思い切って出し切った後には、きっと新しい気づきや付加価値が生まれてくると思ってます
その先に、何度でも挑戦しても、万が一失敗しても、救われて新たに挑戦できるBプラン、Cプランがある、そんな何度でも挑戦できるプラットフォームづくりが大切になるのではないかと思いました
今私が進めているStartup Emergence Ecosystemもそのような仕組みを目指していますが、そういう機能が、界面というものに、機能的に配備されている、そんなことになれば、風の谷の少しでもおうえんになれば、と思って考えさせられました
というとで、一言で言うと
界面を創るノベーション
そんな話をしています^ ^
参考:本: 「風の谷」という希望 残すに値する未来をつくる 電子版 発行日 2025年7月30日 著者 安宅和人 発行所 英治出版株式会社
動画で観たい方はこちら