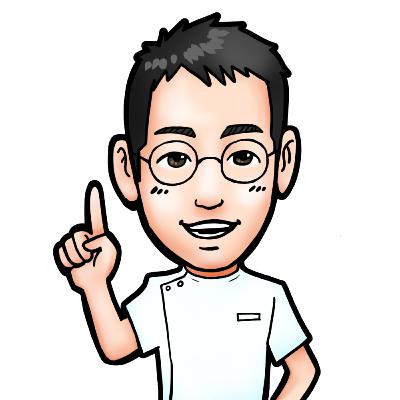Discover 内科医たけおの『心身健康ラジオ』
内科医たけおの『心身健康ラジオ』
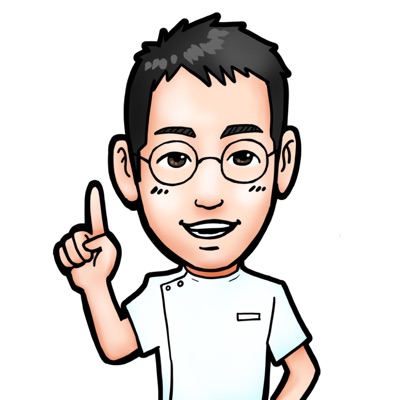
内科医たけおの『心身健康ラジオ』
Author: 内科医たけお@たけお内科クリニック からだと心の診療所 院長
Subscribed: 6Played: 368Subscribe
Share
© 内科医たけお@たけお内科クリニック からだと心の診療所 院長
Description
《毎朝5時30分生配信&5時50分更新!》
SNS総フォロワー62000名超の臨床17年目の現役医師&クリニック院長がお送りする番組です(^^)
この番組では、内科医たけおが診察室の裏側で、医療に関するちよっと役に立つ話をゆる〜く語ります😊
生配信では、公開生収録の他、皆様からのご質問やリクエストにお応えしています😄
ぜひ👍イイネ!💭コメント
↪️お知り合いへのシェア!
宜しくお願いします\(^o^)/
👇フルバージョンはStand.fmで配信中♪
https://stand.fm/channels/5f50dfa36a9e5b17f795785b
👇たけお内科クリニック からだと心の診療所(オンライン診療可)
https://www.body-mind-clinic.com/
👇各メディアへのリンクはこちら
https://linktr.ee/naikaitakeo
※配信する内容は個人の見解であり、所属機関や所属団体、学会などを代表するものではありません。
文字起こしはこちら
https://listen.style/p/naikaitakeo?jZN6Y38h
SNS総フォロワー62000名超の臨床17年目の現役医師&クリニック院長がお送りする番組です(^^)
この番組では、内科医たけおが診察室の裏側で、医療に関するちよっと役に立つ話をゆる〜く語ります😊
生配信では、公開生収録の他、皆様からのご質問やリクエストにお応えしています😄
ぜひ👍イイネ!💭コメント
↪️お知り合いへのシェア!
宜しくお願いします\(^o^)/
👇フルバージョンはStand.fmで配信中♪
https://stand.fm/channels/5f50dfa36a9e5b17f795785b
👇たけお内科クリニック からだと心の診療所(オンライン診療可)
https://www.body-mind-clinic.com/
👇各メディアへのリンクはこちら
https://linktr.ee/naikaitakeo
※配信する内容は個人の見解であり、所属機関や所属団体、学会などを代表するものではありません。
文字起こしはこちら
https://listen.style/p/naikaitakeo?jZN6Y38h
807 Episodes
Reverse
■本日の興味シンシン論文Depression and Advance Care Planning Among Japanese Patients Undergoing Hemodialysis: Japanese Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study (J-DOPPS)血液透析を受けている日本人患者のうつ病とアドバンス・ケア・プランニング:日本人透析アウトカムおよび実践パターン研究(J-DOPPS)Kidney Med. 2025 Dec 12;8(2):101210.https://www.kidneymedicinejournal.org/article/S2590-0595(25)00246-8/pdfこの放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)今回の放送では、雑誌『Kidney Medicine』に掲載された、日本の血液透析患者を対象とした「うつ症状とアドバンス・ケア・プランニング(ACP)」に関する最新の研究論文が紹介されました。たけお先生の専門領域である「サイコネフロロジー(心理腎臓学)」と「緩和ケア」の両方にまたがる、非常に興味深いテーマです。### 1. 研究の背景とデータこの研究は、日本における血液透析患者の大規模データである「J-DOPPS」を用いて行われました。論文のタイトルは『Depression and Advance Care Planning among Japanese Patients Undergoing Hemodialysis』です。### 2. 驚きの現状:高い抑うつ率研究の結果、透析患者の現状として以下の数値が明らかになりました。* **ACPの話し合い実施率**: 約26〜28%(約4人に1人)。たけお先生の肌感覚としては、実際はもっと少ない可能性も示唆されました。* **抑うつ症状の該当率**: 45%(CES-Dという指標で10点以上)。特に抑うつ率に関しては、国際平均の約20%や過去の国内データ(約10%)と比較しても極めて高く、「2人に1人がうつ傾向にある」という衝撃的な結果でした。### 3. 解析結果:うつとACPの相関本研究では、一時点を切り取った「横断研究」と、時間を追った「縦断研究」の両方が行われました。* **横断研究の結果**: 抑うつ症状がある患者は、ない患者に比べて**1.2倍有意にACPの話し合いを行っている**という正の相関が見られました。* **縦断研究の結果**: しかし、1年後にACPの話し合いが増えるかどうかについては、統計学的な有意差は見られませんでした。### 4. 研究の限界と考察たけお先生は、この研究の限界として以下の3点を指摘しました。1. **自己記入式アンケートの限界**: 精神科医の診察ではなく、あくまで患者自身の回答に基づいた評価であること。2. **対象の限定性**: 血液透析患者のみが対象であり、腹膜透析や腎移植、保存的腎臓療法(CKM)の患者は含まれていないこと。3. **ACPの定義**: どこまでの内容を「ACPの話し合い」と見なすか、用語の定義が曖昧であること。### 結論「うつ」と「今後の人生会議(ACP)」という、一見結びつかなそうな要素に関連性を見出した点は非常にユニークであり、今後の講演等でも活用したい内容であると締めくくられました。
■本日の興味シンシン雑誌Medical Practice 2026年2月号(43巻2号)緩和医療緩和ケアまるごとUpdatehttps://www.bunkodo.co.jp/magazine/UCNH86C6M6.htmlこの放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)## 『Medical Practice』2026年2月号:緩和ケアの最前線をアップデート今回の放送で内科医たけお氏は、文光堂から出版された内科総合誌**『Medical Practice』2026年2月号**を紹介しました。特集テーマは「**緩和ケア まるごとアップデート**」であり、たけお氏自身も慢性腎不全の緩和ケアについて分担執筆を担当しています。### 特集の構成と豪華な執筆陣本号の編集は、国立がん研究センターの里見絵理子先生が手掛けています。巻頭では、里見先生とたけお氏の大学の先輩でもある清水研先生(サイコオンコロジー)による、患者の心のケアに焦点を当てた対談が収録されています。また、日本緩和医療学会の理事長である木澤義之先生による今後の展望や、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の第一人者である森先生の論考、さらに宮下先生による「望ましい死」に関する研究など、日本の緩和医療におけるトップランナーたちの知見が集約されています。### 「がんに限らない」緩和ケアの広がり放送の中でたけお氏が強調したのは、**緩和ケアはがん患者だけのものではない**という点です。本誌のセミナーセクションでは、以下の疾患領域における緩和ケアが網羅されています。* **がん**(石木先生)* **心不全**(大石醒悟先生)* **慢性呼吸不全**(萩本先生)* **慢性腎不全**(内科医たけお氏担当)* **認知症**(小川朝生先生)特に非がん疾患における緩和ケアは、近年保険診療のトピックにもなっており、老年医学とも親和性が高く、非常に重要な領域であると述べられています。### 最新トピックとベストプラクティス最新の治療や支援技術についても触れられており、オピオイド誘発性便秘(浜野淳先生)や、モバイルを活用した意思決定支援(藤森麻衣子先生)といった時代を反映した内容が盛り込まれています。さらに、痛み、呼吸困難、せん妄、スピリチュアルペインといった各症状に対する具体的な緩和手法も、各専門家によって詳細に解説されています。### まとめ医療従事者、特に緩和医療に携わる方々にとって、知識を丸ごとアップデートできる一冊として推奨されています。価格は2,970円で、内科全般を扱う医師にとっても非常に有益な内容です。
■本日の興味シンシン番組病院ラジオ埼玉県立がんセンター編配信期限2月18日(水)午前9:14https://www.web.nhk/tv/an/hospital-radio/pl/series-tep-4LP7MJWPN9/ep/VVR1W271P2この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)今回は、NHKの人気番組『病院ラジオ(埼玉県立がんセンター編)』を視聴して感じた、がん診療のエッセンスについて語られました。📻 放送の要約:がん診療における3つの重要な視点ピアサポート(患者同士の支え合い)の力同じ病を抱える患者同士が「先輩・後輩」のように励まし合う姿が印象的に描かれていました。医療従事者には決して踏み込めない、当事者同士だからこそ分かち合える心の支えは、治療において非常に大きな役割を果たします。仕事と治療の両立かつては「がんなら治療に専念すべき」という風潮もありましたが、現在は治療しながら働くことが一般的になりつつあります。仕事への意欲がある場合、それを継続できる環境を整えることが、患者さんの生活の質(QOL)を守ることに繋がります。ACP(アドバンス・ケア・プランニング)と主体的な参加「旅行に行きたい」といった個人の希望を医師に伝え、治療と並行してやりたいことをどう叶えるかを話し合うことが大切です。医師に任せきりにするのではなく、患者自身が「どう生きたいか」を伝えることで、より納得感のある治療計画を立てることができます。💡 たけお先生からの補足緩和ケアの重要性: 治療と並行して、痛みや辛さを和らげる「緩和ケア」を初期から取り入れることの価値についても改めて言及されました。チーム医療の活用: 医師に直接言いづらい希望があれば、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師など、医療チームの誰かにポロッと伝えてみることが、より良いサポートを受けるコツです。番組は今週の水曜日(2月18日頃)まで配信されているそうなので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。興味シンシン☝
■本日のリクエストいつもありがとうございます。2月14日は「セカンドオピニオンを考える日」でもあるそうです。過去にセカンドオピニオンについて放送されていた回があったかと思いますが、振り返りも兼ねて、改めて取り上げていただけたら嬉しいです。・セカンドオピニオンとコンサルテーションの違い・どのような場面でセカンドオピニオンを利用するのが適切かなどについてお話を伺えたらと思います。「大切な人にチョコ🍫」も素敵ですが、「自分や身内の命を守るために立ち止まって考える日」という視点も多くの方に届いたらいいなと感じています。ご検討よろしくお願いします🦢2025年2月2日の放送のセカンドオピニオンについての質問回答回↓↓↓https://stand.fm/episodes/679e8ab564fd6ec0ecef4976★たけお3号(Gem)★https://gemini.google.com/gem/1EZ2jkepBz6cPfxtcrA6Xi6XZEPyGMYRW?usp=sharing是非活用後の感想教えて下さい!この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)2月14日の「セカンドオピニオンを考える日」に合わせ、患者さんと医師のより良い関係性について解説しました。セカンドオピニオンとコンサルテーションの違いまず混同されやすい2つの言葉を整理します。コンサルテーション: 専門職同士(医師から他の専門医など)の相談を指します。文章による正式なものから、チャット等でのフランクな相談まで形態は様々です。セカンドオピニオン: 患者さん自身が、主治医以外の医師に意見を求めることです。これには主治医が作成する「診療情報提供書(紹介状)」が必須であり、現在の治療状況を正確に伝える必要があります。セカンドオピニオンを受ける際のポイント重要なのは、セカンドオピニオンの前に**「ファーストオピニオン(主治医の意見)」を正しく把握すること**です。主治医がどう考え、なぜその診断・治療を選んだのかを理解していないと、他院へ行っても混乱を招き、時間と労力が無駄になってしまう可能性があります。どのような場面で利用すべきか?主に以下の2つのケースが考えられます。診断が確定しないとき: ただし、なぜ診断が難しいのかを主治医にまず確認することが先決です。安易に他へ行くと、かえって診断名に振り回されるリスクもあります。治療の選択肢が複数あるとき: 医療は「アートとサイエンス」の側面があり、正解が一つとは限りません。ガイドラインを軸にしつつも、医師によって判断が分かれる場合に他者の意見を聞くのは有効です。新たなツール「たけお3.0」の誕生主治医に何を聞けばいいか分からない、セカンドオピニオンに行くべきか迷うといった方のために、GoogleのGeminiを活用したAIツール**「たけお3.0」**を開発しました。専門用語を避け、緊急性の判断や標準的な治療方針の解説、主治医とのコミュニケーションをサポートします。自分や大切な人の命を守るために立ち止まって考える、そんなきっかけになれば幸いです。
今週もたくさんのコメントありがとうございました! 以下の宿題提出お願いします!(質問も大歓迎です←マジ大事!! コメント返しは質問を優先 的に取り上げますが、全ての質問に回答できない可能性があるこ とはご了承ください。また 【質問】と入れておいていただけると見 逃しが少ないです)ぜひとも使っていただきたい「たけお2号」 内科医たけお (2号) に興味シンシンに聞いてみよう https://chatgpt.com/g/g-680191c357a48191b476839e3368d6c2-nei-ke-yi-takeo-2hao-nixing-wei-sinsinniwen-itemiyou《宿題》 今週の一番良かった放送の数字を出来れば理由と共に記 入ください!例) 1134この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集し ています! こちらのフォームから是非! (匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C _MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね」」を、感想・コメント は#心身健康ラジオをつけて、Threads、インスタ Storiesなどで お寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部《AI要約》 誤字はご容赦!## **「内科医たけおの新身健康ラジオ」振り返りまとめ(第1457回〜1462回)**今回の放送では、2月初旬の振り返りと、リスナーからのコメントへの回答を中心に、健康習慣、専門的な医学知識、最新の医療ニュースまで多岐にわたるトピックが扱われました。### **1. 健康の鍵「一無、二少、三多」とウェルビーイング**2月の「全国生活習慣病予防月間」にちなみ、健康の基本である**「一無(無煙)、二少(少食・少酒)、三多(多動・多休・多接)」**が紹介されました。* **多動(体を動かす):** 特に今年は「多動」がテーマであり、リスナーからは「何事もほどほどが良い」といった声や、運動と休息のメリハリの重要性が指摘されました。* **多接(多くの接点):** 社会的なつながりが認知症予防や病気のリスク軽減に寄与するという「健康の社会的決定要因」についても触れ、ウェルビーイングの視点からその重要性が再確認されました。### **2. 腎臓病学と医師国家試験クイズ**専門領域である腎臓に関する話題では、NHKの番組「腎臓が寿命を決める」への反響が最も大きかったことが報告されました。* **国家試験チャレンジ:** 慢性腎臓病(CKD)に関するクイズでは、**「3ヶ月以上の持続」**という診断定義や、IgA腎症の寛解状態における基準の解釈など、専門的な解説が行われました。* **AIの台頭:** 知識問題においてAIが98%の正解率を出す現状に対し、これからの医師のあり方についても考察がなされました。### **3. 男性更年期(LOH症候群)とホルモンの変化**リスナーからの質問に基づき、男性更年期障害について深掘りされました。* 女性は閉経に伴いホルモンが急激に低下するのに対し、男性は緩やかに低下するため自覚しにくいという特徴があります。* 診断の難しさや、漢方薬(「命の母」に対する「命の父」の不在など)の活用、産業医としてのメンタル・フィジカル両面からのアプローチの重要性が語られました。### **4. AI活用と最新医療ニュース**「ちきりんAI」を1ヶ月使い込んだ評価として、ロジカルな回答の質は高いものの、専門的な医療相談における限界(65点評価)が示されました。また、最新ニュースとして以下の4点が紹介されました。* **名称変更:** 「摂食障害」から「摂食症」への名称変更の動き(受診のハードルを下げる期待)。* **心不全検査:** 保険適用で安価(約400円)に受けられる**NT-proBNP検査**の有用性。* **医薬品流通:** 一部医薬品の供給不安定問題への懸念。* **AIによる手術説明:** 医療現場でのAI活用事例。
【今週の興味シンシン医療ニュース】 ・「摂食障害」は「摂食症」に・AIアプリで手術説明⁉️・血液検査で分かる「心不全」・これで抗菌薬の安定供給なるか?https://note.com/naikaitakeo/n/n016822027662この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)内科医たけお先生による、今週の興味津々医療ニュース4本の解説です。### 1. 「摂食障害」から「摂食症」へ:名称変更の意義日本摂食障害学会が、疾患名を**「摂食症」**へと変更しました。* **理由**: 「障害」という言葉が「治らない」という固定観念を与え、偏見や誤解を招く恐れがあるためです。* **背景**: 近年、精神疾患の呼称は「パニック障害」が「パニック症」に変わるなど、回復の可能性を強調する方向へシフトしており、今回の変更もその流れを汲んだものです。たけお先生も、この変更が医療機関への受診ハードルを下げる良い流れになると評価しています。### 2. AIアプリ「あなたの手術手帳」:医師の負担軽減へ名古屋市立大学などが、AIを活用して手術内容を説明するアプリを開発しました。* **目的**: 同じ説明を何度も繰り返す外科医の負担を減らす「タスクシフト」が狙いです。* **たけお先生の視点**: 実際にアプリを試したところ、最新のAIと比較すると自然さにはまだ改善の余地があるものの、方向性は非常に良いと述べています。今後は、単なる動画再生に留まらず、AIならではの「個人に個別化された説明」への進化に期待を寄せています。### 3. 認知度わずか3%:心不全の血液検査心不全のリスクを早期に発見できる血液検査(NT-proBNPなど)の重要性が語られました。* **課題**: 多くの人が「心臓の検査といえば心電図」と考えがちですが、心電図だけでは心機能を十分に評価できません。* **事実**: この有効な血液検査の認知度はわずか**3%**と極めて低く、たけお先生も驚きを示しています。保険適用もされているため、自覚症状がなくてもリスク把握のために受けることが推奨されています。### 4. 抗菌薬の「中国依存」からの脱却と安定供給厚労省が、抗菌薬の原料備蓄を行う製薬企業への支援を決定しました。* **現状**: 抗菌薬の原料は中国などの特定国に依存しており、国際情勢によって供給が不安定になるリスクを長年抱えています。* **展望**: 予算を投じて国内での生産・備蓄体制を整備し、どんな情勢下でも安定して抗菌薬を供給できる体制づくりを目指します。医療現場の切実な課題であるだけに、たけお先生も強く賛同しています。
ちきりんAIhttps://events.diamond.jp/event/15426たけお2号https://chatgpt.com/g/g-680191c357a48191b476839e3368d6c2-nei-ke-yi-takeo-2hao-nixing-wei-sinsinniwen-itemiyouこの放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)---## 『ちきりんAI』1ヶ月徹底レビュー:たけお先生の視点今回の放送では、**たけお内科クリニック**のたけお先生が、1月上旬から提供されている**「ちきりんAI」**を約1ヶ月間使い倒した感想を、医学とはほぼ関係のない「超雑談回」として語っています。### ちきりんAIの概要社会派ブロガー・ちきりん氏の膨大なデータ(書籍、ブログ、Voicyなど)を学習させた、3ヶ月期間限定のLINE用AIプログラムです。たけお先生は自ら購入して検証を行いました。### たけお先生による採点:**65点**先生の現時点での評価は「及第点」である65点です。他のAIも使いこなす専門的な視点から、以下のポイントが挙げられました。* **向いていること**: 意思決定のサポートや思考の整理など、「ちきりん氏らしい思考プロセス」を借りる作業。* **向いていないこと**: クリエイティブなネタ出し(ラフターヨガのネタなど)や要約作業。これらはChatGPTやGeminiの方が適しているとのことです。---### 指摘された具体的な課題1. **回答が長すぎる**:単純な問いに対しても詳細なポイント解説が付随し、簡潔さに欠ける点があります。2. **ビジネス用語の多用**:「メリデメ」「プロトタイプで回す」といった特有の用語が多く、中学生への分かりやすさという点では変換が必要になります。3. **UI/UXの制約(LINEの限界)**:話題の切り替えが難しく、前のコンテキストを引きずってしまう傾向があります。4. **マルチモーダル非対応**:画像や音声入力に対応しておらず、LINEの利点を活かしきれていない点に今後の期待を寄せました。---### 自作GPT「たけお2号」との比較先生が作成した医療相談用AI**「たけお2号」**と比較すると、医療・健康相談においては「たけお2号」に軍配が上がると分析しています。ちきりんAIは前提条件の確認なしに長文回答を返すため、専門領域の相談には工夫が必要だとの見解です。### 結論:一次情報の価値最終的に先生は、AIには代替できない**ちきりん氏本人の「一次情報(実体験)」の強さ**を再認識したと結んでいます。---**【今朝の心身じゃんけん】**結果は**「チョキ」**でした。皆様にとって幸せな一日になりますように。そんじゃーね。
■本日のご質問男性の更年期障害について質問です。該当する世代の男性が様々な身体症状に悩まされた時、客観的には「これ、心身症ですから☝️」と思っても、ストレスと向き合いたくないのか(自称)更年期障害を主張する人が時折います。そして結局は心身症にたどり着くのですが、たまに見切り発射でホルモン治療を受け、症状が悪化してしまう人もいます😭長くなりましたが、🐼は男性の更年期障害の方に会ったことがありません。たけお先生はちゃんと診断基準を満たす方に遭遇したことはありますか?●資料男性の性腺機能低下症ガイドライン 2022https://jspe.umin.jp/medical/files/guide20230217.pdfLOH症候群(加齢男性・性腺機能低下症)診療の手引きhttps://www.urol.or.jp/lib/files/other/guideline/44_loh.pdfこの放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)内科医たけお先生は、産業保健スタッフのパンダ🐼さんからの質問に対し、**男性更年期障害(LOH症候群:加齢男性性腺機能低下症候群)**について、自身の経験を交えながら詳しく解説しています。---### **1. 正式名称と診断の現状*** **正式名称**: 男性更年期は通称であり、医学的には「**加齢男性性腺機能低下症候群(LOH症候群)**」と呼ばれます。* **診断の難しさ**: テストステロン(男性ホルモン)値だけで判断するのではなく、身体症状、精神症状、性機能関連の症状を総合的に評価する**AMSスコア**などが用いられます。* **数値と症状の乖離**: ホルモン数値が正常範囲内であっても、症状がある場合はLOH症候群と診断され、治療の対象となることがあります。### **2. 治療の考え方:多角的なアプローチ**たけお先生は、薬物療法だけに頼らない**「総合的な治療」**の重要性を強調しています。* **薬物療法**: 男性ホルモン補充療法が第一選択となることが多いですが、これだけで全てが解決するわけではありません。* **生活習慣の改善**: 適切な食事や睡眠など、土台となる生活習慣の見直しが不可欠です。* **心理・運動療法**: 必要に応じて心理療法や運動療法を組み合わせることが推奨されています。### **3. 社会的認知と周囲の理解*** **認知度の低さ**: 女性の更年期障害に比べ、男性更年期はまだ社会的な理解が進んでいない現状があります。* **「見えない」つらさ**: 多くの心身症と同様、周囲から症状が見えにくいため、本人の苦しみが理解されにくいという課題があります。* **ガイドラインの更新**: 2022年には日本泌尿器科学会などから最新のガイドライン(診療の手引き)が発行されており、医療従事者側も知識のアップデートが必要です。
■本日の医師国家試験クイズ慢性腎臓病で正しいのはどれか。a 喫煙は発症に関連しない。 b 年齢は発症に関連しない。 c 尿蛋白陽性が診断に必須である。 d 初期から自覚症状が現れることが多い。 e 心血管疾患発症のリスクファクターである。この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)ご提示いただいた音声ファイル「内科医たけおの心身健康ラジオ」の内容を、約1000文字で要約しました。---## 「内科医たけおの心身健康ラジオ」放送要約本放送では、パーソナリティを務める**たけお内科クリニック・心身の診療所**の院長であり、腎臓専門医でもある**たけお氏**が、先日実施された**第120回医師国家試験**の問題を引用し、慢性腎臓病(CKD)に関する解説と、最新のAI技術が医学教育に与える影響について語っています。### 医師国家試験クイズ:慢性腎臓病(CKD)について番組の中盤では、リスナーと共に医師国家試験のB問題(必修問題)にチャレンジする企画が行われました。問題の内容は「**慢性腎臓病(CKD)について正しいものはどれか**」というもので、以下の選択肢が示されました。* **A:喫煙は発症に関連しない**(不正解:喫煙は発症に関連する)。* **B:年齢は発症に関連しない**(不正解:加齢に伴い腎機能は低下するため関連する)。* **C:尿蛋白陽性が診断に必須である**(不正解:eGFRが60未満であれば、尿蛋白がなくてもCKDと診断される場合がある)。* **D:初期から自覚症状が現れることが多い**(不正解:初期はほぼ無症状であり、進行したステージG5(eGFR 15未満)でも症状が出ないことが多い)。* **E:心血管疾患発症のリスクファクターである**(**正解**:CKD自体が心筋梗塞や脳卒中などのリスクを高めることがガイドライン等でも示されている)。たけお氏は腎臓専門医の視点から、尿蛋白の有無がCKDの悪化スピードに関係することや、検診による早期発見の重要性を強調しています。### 医学界におけるAIの驚異的な進化放送の後半では、ある予備校が**ChatGPT、Claude、Gemini**といった主要な生成AIに今回の医師国家試験を解かせた結果について触れています。* **AIの正答率**:各AIともに**95%から98%**という驚異的な正答率を記録しました。* **人間との比較**:通常の合格ライン(必修8割、その他6割)を大幅に上回っており、知識量においてはもはや人間がAIに太刀打ちできないレベルに達していると分析しています。* **今後の展望**:AIの進化を実感しつつ、これからの医療における人間の役割についても考えさせられる内容となっています。### お知らせとエンディング本日夜のYouTubeライブでは、AIを活用しながら、腎臓病、心身医学、緩和ケアに関連する医師国家試験の問題をさらに深掘りして解説する予定です。
■本日の資料全国生活習慣病予防月間https://seikatsusyukanbyo.com/monthly/この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)## 放送の概要:2月は「全国生活習慣病予防月間」「竹お内科の心身健康ラジオ」の2026年2月8日の放送回では、心身医学専門医である**内科医たけお氏**が、毎年2月の**「全国生活習慣病予防月間」**にちなんだ健康習慣について解説しています。日本生活習慣病予防協会(JPALD)が提唱する健康標語**「一無、二少、三多(いちむ・にしょう・さんた)」**を軸に、今年度のテーマである「多動」や、現代的なウェルビーイングの視点を取り入れた内容となっています。---## 健康標語「一無、二少、三多」の詳細生活習慣病を防ぐための指針として、以下の3つのポイントが挙げられています。### 1. 一無(いちむ):無煙・禁煙の勧め* **タバコを吸わないこと**:万病の元であり、がん予防などの観点からも「百害あって一利なし」として、禁煙が最も重要視されています。### 2. 二少(にしょう):少食・少酒* **少食(食少)**:腹八分目を心がけ、食べ過ぎによる肥満や健康被害を防ぐことが大切です。* **少酒(酒少)**:アルコールは控えめに。飲めない人は無理に飲まず、飲む人も節酒や断酒を検討することが推奨されます。### 3. 三多(さんた):多動・多休・多接今回の放送で特に重点的に語られたのが、この「三多」です。* **多動(たどう)**:今よりプラス10分、体を多く動かすこと。「2本の足は2人の医者」というヒポクラテスの格言を引用し、歩くことが整形外科的疾患、がん、心血管疾患、そしてメンタルヘルスの改善に有効であると説いています。* **多休(たきゅう)**:しっかり休養すること。単なる睡眠だけでなく、心と体をリフレッシュさせる休息全般を指します。* **多接(たせつ)**:多くの人、事、物に接すること。社会的なつながりを持つことは、医学的なエビデンスからもウェルビーイング(幸福)に直結するとされています。---## 2026年のテーマ「多動」と実践方法2026年度のキャンペーンスローガンは**「幸せは足元から 多く動いて健康実感」**です。特にデスクワークが多い現代人にとって、座りっぱなしの時間を減らし、こまめに動くことは健康維持に不可欠です。協会の公式サイトでは、以下のコンテンツが公開されていることが紹介されました。* **変身ハッピーボディ!あなたを変える10の体操**:約10本のショート動画で具体的な運動方法を学べます。* **啓発用リーフレット**:メールアドレスの登録で入手可能で、職場などでの掲示が推奨されています。
今週もたくさんのコメントありがとうございました! 以下の宿題提出お願いします!(質問も大歓迎です←マジ大事!! コメント返しは質問を優先 的に取り上げますが、全ての質問に回答できない可能性があるこ とはご了承ください。また 【質問】と入れておいていただけると見 逃しが少ないです)ぜひとも使っていただきたい「たけお2号」 内科医たけお (2号) に興味シンシンに聞いてみよう https://chatgpt.com/g/g-680191c357a48191b476839e3368d6c2 -nei-ke-yi-takeo-2hao-nixing-wei-sinsinniwen-itemiyou《宿題》 今週の一番良かった放送の数字を出来れば理由と共に記 入ください!例) 1134この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集し ています! こちらのフォームから是非! (匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C _MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね」」を、感想・コメント は#心身健康ラジオをつけて、Threads、インスタ Storiesなどで お寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部《AI要約》 誤字はご容赦!## 内科医たけおの身心健康ラジオ:今週の振り返りまとめ内科医たけお先生による「身心健康ラジオ」の2026年2月6日放送回では、先週金曜日から昨日まで(第1451回〜第1456回)の放送内容をリスナーのコメントと共に振り返りました。---### **今週の人気回ランキング**リスナーの集計によると、今週最も反響が大きかったのは以下の回でした。1. **第1448回「クレアチニンの話」**:検診項目の重要性について。2. **第1447回「しびれの話」**:日常的な症状への関心の高さが伺えます。### **腎臓の健康と最新の研究**今週は特に**腎臓**に焦点を当てた内容が豊富でした。* **腎臓が寿命を決める**:NHKの番組『人体の不思議』を引用し、腎臓の重要性を再認識。* **慢性腎臓病(CKD)のACP**:最新論文を基に、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)における多職種連携やピアサポートの意義を解説しました。### **AI活用とモバイルファーマシー**専門外の分野にもAI(NotebookLMなど)を駆使して切り込む、たけお先生らしい試みも紹介されました。* **モバイルファーマシー**:災害時などに活躍する移動薬局について、AIを活用して調査・解説。* **AIとの対話**:リスナーとのやり取りでもAI要約の誤字(竹内たけお)を笑いに変えるなど、テクノロジーとの共生を体現しています。### **がん予防と医療ニュース**2月4日の「世界対がんデー」にちなんだ話題や、最新の医療トピックを網羅しました。* **がんを予防する5+1**:禁煙、節酒、食生活(減塩)、身体活動、体形、そして感染症(ピロリ菌など)対策の重要性を強調。* **5つの医療ニュース**:抗てんかん薬の運転、旅行会社の設立、がん手術の待機状況など、多岐にわたるニュースをピックアップしました。---### **リスナーとの対話:ACPとSDMの違い**放送の後半では、リスナーからの鋭い質問に対し、**ACP(将来の生き方の話し合い)**と**SDM(現在の治療法の共同決定)**の違いを、バナナやリンゴなどの例えを用いて分かりやすく補足しました。 医師だけでなく、看護師や心理士、さらには患者同士の「語りの場」が、より良い意思決定に繋がると語っています。
【今週の興味シンシン医療ニュース】 ・抗てんかん薬投与の運転の可否・医師が旅行会社を!・がんの手術が2ヶ月待ちが現実に・・・・これで臓器移植が進むか?https://note.com/naikaitakeo/n/n406e41537659この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)## **「竹内武夫の身心健康ラジオ」放送内容要約**今回の放送では、内科医・心療内科医である竹内武夫先生が、医療に関する5つの最新ニュースをピックアップして解説しています。### **1. 抗てんかん薬服用中の運転制限に関する緩和**厚生労働省の安全対策調査会にて、一部の抗てんかん薬の添付文書改訂が合意されました。* **対象薬剤**: カルバマゼピン、バルプロ酸ナトリウム、ラモトリギン、ラコサミド、レベチラセタムの5剤です。* **変更点**: これまでは「運転をさせないこと」と一律に禁止されていましたが、今後は「医師が患者の状態に応じて適否を判断する」形式に改められます。* **意義**: 欧米の基準に準じた動きであり、薬を適切に服用していれば運転が可能なケースも考慮されるようになります。ただし、副作用の眠気などには引き続き注意が必要です。### **2. 医師が立ち上げた「病気と旅」を繋ぐ旅行会社**大阪の泌尿器科医、伴絵里先生が代表を務める旅行会社「リタビ(Let's Tabi)」の挑戦が紹介されました。* **サービス内容**: 医師や看護師、介護士が同行し、医療的ケアが必要な人でも安心して旅行を楽しめる体制を整えています。* **背景**: 「病気があっても自由に旅をしたい」という切実な願いを叶えるための活動です。竹内先生も以前から面識のあるアクティブな先生による、全国的な普及が期待される取り組みです。### **3. 秋田県における深刻な外科医不足**外科医の不足により、がんの手術が2ヶ月待ちになるなど、地方の医療現場が限界に近い現状が報じられました。* **現状データ**: 秋田大学の初期研修医のうち、外科を志望したのは2024年度で45人中2人、2023年度は47人中4人と非常に少ない状況です。* **今後の展望**: 医師の偏在や診療科の偏りを解消するため、病院の集約化などが急務であると議論されています。### **4. 臓器移植に関する新たな動き**臓器移植を推進するための2つのニュースが取り上げられました。* **藤田医科大学の認可**: 日本臓器移植ネットワーク以外で初めて、藤田医科大学が臓器あっせん法人として厚生労働省から認可されました。* **診療報酬の加算**: ドナーコーディネーターの活動を評価し、脳死下での臓器提供に対する診療報酬を手厚くする方針が示されました。これにより、諸外国に比べて少ない日本の移植件数の向上が期待されています。---
■本日のご質問いつも配信ありがとうございます。リクエストをお願いいたします。2月4日は「世界対がんデー🌍」です。標準治療の大切さ、禁煙などの「予防」がどれだけリスクを下げるかという現実的なお話など、「世界対がんデー」をきっかけに正しい情報の重要性を伝えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします🦢リンク🔗UICC (国際対がん連合) 日本委員会 https://share.google/p4KVtX4WVhsY8HGI3Wikipediaより抜粋→国際対がん連合(UICC)は、世界100ヵ国以上の350を超える対がん組織からなるコンソーシアム(目的に達しようとする組織)で、2005年(平成17年)に世界がんキャンペーンを始めた。このキャンペーンでは、「子供には、煙草の煙のない環境を与える」「体を動かし、バランスの良い食事をし、肥満を避ける」「ウイルス性の肝臓がん、子宮頚がんには、ウイルスについて研究する」「日光を浴びすぎない」ことで、がんの40%は予防できると強調している。☆資料☆科学的根拠に基づくがん予防がんになるリスクを減らすために(がん情報サービス)https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.htmlこの放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)本日のラジオ放送では、2月4日の**「世界対がんデー」**をきっかけに、最新の正しい情報を知ることの重要性が語られました。国立がん研究センターが提唱する、科学的根拠に基づいた**「日本人のためのがん予防法(5+1)」**について、各項目を詳しく解説されています。---### 日本人のためのがん予防法:基本の5項目1. **タバコ:吸わない・避ける*** 肺がんだけでなく、食道、膵臓、胃、大腸など全身のがんに関わります。* 喫煙者は非喫煙者に比べ、がんのリスクが約**1.5倍**高まります。* 自分だけでなく、周囲の人のための受動喫煙対策も必須です。2. **お酒:飲まないのがベスト*** 肝細胞、食道、大腸がんなどのリスクになります。* 最近の研究トレンドでは、**「お酒は飲まないに越したことはない」**という認識が主流になっています。3. **食生活:塩分・野菜・温度に注意*** **減塩**: 日本人が多い塩分摂取を控えることで、胃がんや高血圧の予防に繋がります。* **野菜・果物**: 不足しないよう摂取することで、食道や肺などのがんリスクを下げます。* **温度**: 熱すぎる食べ物や飲み物は、食道がんのリスクを高めるため「冷ましてから」が鉄則です。4. **身体活動:座りすぎを防ぐ*** 体を動かす時間が長いほどリスクは下がります。* 特にデスクワークの人は、意識的に座っている時間を短くすることが大切です。5. **体重:適切なBMI(21〜25)の維持*** 太りすぎも痩せすぎもリスクを上げます。* で、**21から25**の範囲を保つのが理想的です。---### 「+1」の重要項目:感染症対策日本人のがんの原因として非常に重要なのが「ウイルス・細菌感染」です。* **肝炎ウイルス(B型・C型)**: 肝細胞がんの原因。* **ヘリコバクター・ピロリ**: 胃がんの原因。* **HPV(ヒトパピローマウイルス)**: 子宮頸がんの原因。* **HTLV-1**: 成人T細胞白血病リンパ腫の原因。これらはワクチンや除菌、適切な検査でリスクを大幅に下げることが可能です。---### まとめ:リスクを半減させるためにこれら「5+1」の習慣を実践することで、日本人の**がんのリスクはほぼ半減する**と言われています。まずは正しい情報源(がん情報サービスなど)に触れ、できることから取り組んでいきましょう。
■本日の論文Advance Care Planning Interventions for Adults With Chronic Kidney Disease: A Systematic Review慢性腎臓病の成人に対するアドバンス・ケア・プランニング介入:系統的レビューhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jorc.70046この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)---## 音声要約:慢性腎臓病(CKD)患者へのアドバンス・ケア・プランニング(ACP)内科医たけお氏による本放送では、2025年12月25日に学術誌「Journal of Renal Care」で発表された、慢性腎臓病(CKD)の成人患者に対するアドバンス・ケア・プランニング(ACP)介入に関する系統的レビュー論文が紹介されています。### ACP(人生会議)とはACPは、将来の医療やケアについて、本人、家族、医療者が事前に話し合うプロセスを指します。特に腎疾患においては、透析(血液・腹膜)や移植といった「腎代替療法」を選択するか、あるいはそれらを行わない「保存的腎臓療法」を選択するかなど、重要な意思決定が必要となるため、ACPの役割が非常に重要視されています。### ACP介入に不可欠な5つの要素本論文では、2024年9月までに出された27個の過去の研究を分析し、効果的なACP介入に必要な要素として以下の5点を挙げています。1. **医療従事者への教育**医療者がACPの概念を正しく理解するだけでなく、患者との対話における**コミュニケーション・スキル**を習得することが重要です。2. **対話の実施**専門家との直接的な対話が不可欠です。腎臓内科医だけでなく、看護師やソーシャルワーカーなど、**多職種**が関わることが推奨されています。3. **学習教材(エデュケーショナル・リソース)の提供**透析の仕組みや移植のメリット・デメリットなどが分かりやすく解説された冊子や資材を活用することで、患者の理解を深めます。4. **ピアサポーターによる支援**同じ病気を経験している患者同士のコミュニティでの対話は、医療者には打ち明けにくい悩みや不安を共有できる貴重な機会となります。5. **緩和ケアとの統合**ACPは緩和ケアの根幹をなすものであり、早期から緩和ケアの視点を取り入れることが、適切な意思決定支援につながります。### ACPを実施するメリットACPを行うことで、最終的な医療費(入院費用など)の抑制につながる可能性や、患者が望むケアを受けられる可能性が高まるなど、多くのメリットが示唆されています。---たけお先生は、この最新の知見を今後の講演活動などにも活かしていきたいと締めくくっています。
■本日のご質問いつも楽しく興味シンシンで聴かせていただいています☝️先日テレビで「モバイルファーマシー」について放送されており、災害時の集団感染や持病を持った方にとても役に立つ話をしていました。私は初めて「移動式の薬局」があることを知ったので衝撃でした。もっと詳しく知りたいと思いました。実際に私はみたことはありませんが、たけお先生は関わられたことがあるかどうか、便利な点と今後の課題についてお話いただきたいです。★タネ明かし★https://notebooklm.google.com/notebook/998fc501-e90b-4d7a-ba49-86a5380ef26fhttps://gemini.google.com/share/c588ec375c67この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)## **「内科医たけおの心身健康ラジオ」:モバイルファーマシーとAI活用の可能性**今回の放送では、リスナーからの質問をきっかけに、災害時に活躍する**「モバイルファーマシー(移動式薬局)」**の実態と、内科医たけお氏自身による**AIツールの活用術**について語られました。### **1. モバイルファーマシー(移動式薬局)の概要**モバイルファーマシーとは、キャンピングカーを改造し、調剤設備を整えた**「移動できる薬局」**のことです。災害発生時、現地の薬局が機能停止した際や、避難所での集団感染、持病を持つ方への対応において非常に重要な役割を果たします。* **主な機能**: 単なる薬の調剤にとどまらず、薬剤師が同行して避難所の**環境衛生アセスメント**(ノロウイルスなどの感染症対策や衛生状態のチェック)も行います。* **対応力**: 最大で約500種類の医薬品を搭載可能であり、急性期の疾患から、高血圧や糖尿病といった慢性疾患の継続治療まで幅広く対応できます。### **2. 災害時における実績とメリット**特に令和6年能登半島地震では、全国から**9台のモバイルファーマシー**が現地に派遣され、インフラが寸断された地域で活動しました。* **利点**: 薬を載せたまま被災地へ直接向かえるため、物流が不安定な状況下でも迅速に適切な処方を提供できる点が最大のメリットです。### **3. 現在の普及状況と今後の課題**モバイルファーマシーは現在、薬剤師会や大学病院などが所有しており、全国に**約20台**存在します。* **台数の問題**: 全国で20台という数が十分なのかという議論があります。* **平常時の活用**: 災害がない時期に「宝の持ち腐れ」にしないよう、へき地医療への派遣など、日常的な運用方法が模索されています。### **4. AI(NotebookLM)を駆使した情報発信**放送の終盤で、たけお氏は驚きの事実を明かしました。実は、今回のモバイルファーマシーに関する詳細な解説は、GoogleのAIツール**「NotebookLM」**を活用してリサーチ・構成されたものです。* **AI活用の意義**: 専門外の分野(災害医療など)であっても、AIを正しく活用することで短時間で質の高い情報をまとめ、アウトプットすることが可能です。* **2026年の目標**: たけお氏は今年の目標の一つに「AI活用」を掲げており、リスナーに対しても、日々の調べ物や業務にAIを取り入れることで、自身のスキルを拡張していく楽しさを伝えています。
■本日の興味シンシン番組3か月でマスターする人体(5)腎臓が寿命を決める!?配信期限2月4日(水)午後9:59https://www.web.nhk/tv/an/3month-jintai/pl/series-tep-Y5Y4KYM153/ep/6L9X116RK6この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)内科医たけお氏による「心身健康ラジオ」の放送内容を、約1000文字で要約しました。今回の放送では、たけお氏が「たけおセレクトTV」として、NHKの番組『3か月でマスターする人体』の第5回「腎臓が寿命を決める」を視聴した感想と、その推奨理由を語っています。---## 番組の概要と推奨の背景今回のラジオで紹介されたのは、2026年1月28日(水)に放送されたNHKの番組です。この回では、京都大学の柳田素子教授が解説を担当し、腎臓にスポットを当てた30分間の特集が組まれました。たけお氏は、この番組を「非常に良かった」と高く評価しており、特に一般の人々が腎臓の真の役割を知る上で価値があるとして、以下の3つのポイントを挙げています。### 1. NHKならではの圧倒的な映像美* **電子顕微鏡と高品質CG**: 番組前半では、腎臓の内部構造が最新のCGや電子顕微鏡の映像で詳細に映し出されました。* **可視化のメリット**: 一般的に腎臓があることは知られていても、その内部がどのようになっているかを視覚的に理解する機会は少ないため、NHKの予算をかけた緻密な映像は一見の価値があると述べています。### 2. 「尿を作る」だけではない多才な機能* **多様な役割の解説**: 腎臓の主な役割として「尿を作る」ことが挙げられますが、番組ではそれ以外の重要な働きも詳しく解説されました。* **腎性貧血**: 腎臓が悪くなると、血液中の酸素を運ぶヘモグロビンの生成を促すホルモンが出にくくなり、貧血(腎性貧血)を引き起こす仕組みが説明されました。* **生命維持のコントロール**: 血圧の調整、体内の酸とアルカリのバランス維持、電解質(ミネラル)の調整など、腎臓が全身の司令塔として機能している点が強調されています。* **臓器相関**: 心臓と腎臓が密接に関わる「心腎連関」や、腸と腎臓の関わりなど、他の臓器とのネットワークについても触れられました。### 3. 治療選択肢としての「移植」への言及* **腎代替療法の提示**: 腎臓が悪くなった際の治療法として、多くのメディアが「透析」のみを扱いがちですが、この番組では柳田教授が「移植と透析」という順序で、移植を強力な選択肢として提示したことをたけお氏は絶賛しています。* **多様な透析手法**: 透析の中でも、一般的な血液透析だけでなく、腹膜透析や在宅血液透析、夜間に行うオーバーナイト透析など、患者の生活の質(QOL)を重視した多様な選択肢があることを知る重要性が語られました。---## 視聴方法とエンディングこの番組は「NHKプラス」にて、2026年2月4日(水)の午後10時まで見逃し配信されています。たけお氏は、医療従事者であっても腎臓=血液透析という固定観念を持ちやすい現状を指摘し、この番組を通じてより広い視点を持ってほしいと締めくくりました。
今週もたくさんのコメントありがとうございました!以下の宿題提出お願いします!(質問も大歓迎です←マジ大事!! コメント返しは質問を優先的に取り上げますが、全ての質問に回答できない可能性があることはご了承ください。また【質問】と入れておいていただけると見逃しが少ないです)ぜひとも使っていただきたい「たけお2号」内科医たけお(2号)に興味シンシンに聞いてみよう☝ https://chatgpt.com/g/g-680191c357a48191b476839e3368d6c2-nei-ke-yi-takeo-2hao-nixing-wei-sinsinniwen-itemiyou《宿題》今週の一番良かった放送の数字を出来れば理由と共に記入ください!例)1134この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部《AI要約》誤字はご容赦!2026年6月施行予定の診療報酬改定により、腎不全の緩和ケアが加算対象となることが大きなトピックとして取り上げられました。これまで心不全や呼吸器疾患が先行していた緩和ケアの分野に、ようやく腎不全が加わることへの期待が語られています。ただし、現場の医師たちがどのように対応すべきかについては、まだ検討段階にあるとの現状も示されました。NHKの「トリセツショー」に関連したしびれ図鑑の紹介がありました。しびれの原因は脳、整形外科的疾患、内臓疾患など多岐にわたります。特に、女性や透析患者に多い「手根管症候群」についても触れられ、透析患者の場合はアミロイドの沈着が原因となることが解説されています。これまで法定健診の必須項目ではなかったクレアチニンが、ようやく項目に追加されることの意義が議論されました。また、最近の「メディカルダイエット」等で処方されるSGLT2阻害薬の影響により、糖尿病でない若年層に「尿糖陽性」が出るケースが増えており、臨床現場での混乱を招く可能性について注意喚起がなされています。6月から公認心理師による認知行動療法(CBT)が保険適用されることについて、そのハードルの高さと、一方で期待されるアプリによるCBTの有効性が語られました。技術面では、OpenAIの論文執筆特化型AI**「Prism」の試用感について、共同作業や翻訳の精度の高さが絶賛されています。さらに、へき地医療におけるオンライン診療**の活用形態(D2P with N:看護師が同席する形式)についても、その効率性と有効性が示唆されました。誤嚥性肺炎のニュースに関連し、医療的な食事調整と、患者や家族の生活の質(QOL)のバランスをいかに取るかという、終末期医療や在宅医療における深い課題についても言及されました。
【今週の興味シンシン医療ニュース】 ・「オンライン受診施設」創設へ!・AIで論文が!!・たった10分の運動で抗がん作用!?https://note.com/naikaitakeo/n/n10c6c29a0b2bこの放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)---## 内科医たけおの心身健康ラジオ:医療ニュース解説サマリー今回の放送では、最新の医療ニュース3本を中心に、AIツールや薬の不適切使用に関するトピックが解説されています。### 1. 僻地における「オンライン診療受診施設」の創設厚生労働省は、過疎地の公民館や郵便局などをオンライン診療の拠点として活用する方針を固めました。これは、デジタル機器の操作に不慣れな高齢者が、施設の職員によるサポートを受けながら受診できる環境を整えるものです。オンライン診療は接続までのハードルが非常に高いという現状があり、拠点を設けて高齢者が集まる形をとることで、接続トラブルの解消と医療の効率化を同時に図る狙いがあります。訪問看護師が同行する「D2P with N」などの手法に加え、こうした拠点が普及することで、地域医療のアクセスの向上が期待されています。### 2. OpenAIによる論文執筆支援ツール「Prism」の公開OpenAIが、科学論文を執筆するためのブラウザアプリ「Prism」を完全無料で公開しました。これはGoogleの「NotebookLM」に対抗するものと見られています。話者自身も、来年の臨床試験が予定されている「異種移植(ブタからヒトへの腎移植)」に伴う心理的影響に関する学会発表準備において、NotebookLMを積極的に活用しています。AIを用いた研究や執筆支援は今後ますます加速すると予測されており、OpenAIとGoogleの競争によって、研究者にとってより利便性の高い環境が整っていくことが強調されました。### 3. わずか10分の運動による抗がん作用の可能性ニューカッスル大学の研究により、10分間の激しい運動(エアロバイクなど)が、がん細胞の増殖を抑える生物学的変化を引き起こす可能性が示されました。運動後には免疫に関わるタンパク質「インターロイキン6(IL-6)」が増加し、1300以上の遺伝子活動に変化が見られたとのことです。階段の上り下りやバス停までの歩行といった日常的な短時間の活動が、がんリスクの軽減に寄与することを示唆する重要な知見です。### その他のトピック* **日本の誤嚥性肺炎診療:** 日経メディカルの記事を引用し、国内の診療において不足している視点について医療従事者への確認を促しています。* **糖尿病薬のダイエット目的利用:** SNSでのネガティブな投稿が急増しており、適正使用の徹底と規制の必要性について、個人の見解を含めて警鐘を鳴らしています。
■本日の資料※公認心理師の方は必読です!!認知行動療法における多職種連携マニュアルhttps://jact.jp/wp_site/wp-content/uploads/2023/03/%E3%80%90%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8%E3%80%91%E2%91%A1%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E8%A1%8C%E5%8B%95%E7%99%82%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A4%9A%E8%81%B7%E7%A8%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_0216.pdfこの放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)今回の放送では、2026年6月から施行される**診療報酬改定**における「公認心理師による認知行動療法(CBT)」の評価について、医師・公認心理師両方の視点からその意義と課題が詳しく解説されました。---### 1. 改定の歴史的背景と意義* **心理職の国家資格化**: 公認心理師は日本初の心理系国家資格として誕生して約10年。 これまでの民間資格(臨床心理士など)では困難だった「診療報酬の枠組み」への参入が、今回の改定でCBTという形で大きく前進しました。* **臨床現場でのメリット**: 診療報酬が付くことで、医療機関が心理師を雇用する経営的メリットが生まれます。 これにより、心理職が臨床現場でより専門性を発揮しやすくなることが期待されます。### 2. 臨床現場における「理想と現実」のギャップ期待が寄せられる一方で、放送ではNDBオープンデータなどの数値に基づいた冷静な現状分析も行われました。* **実施件数の低迷**: 医師によるCBTの実施件数は年間3万〜4万件と減少傾向にあります。 さらに、先行して認められていた「医師と看護師が共同で実施するCBT」は2020年度でわずか234件(医師単独の1/100以下)に留まっており、多職種連携によるCBTの実施が現実には極めて難しいことが浮き彫りになっています。* **高い運用ハードル**: 常勤要件や施設基準の厳しさに加え、CBTに要する時間的コストを考えると、医療機関が導入を躊躇する可能性も指摘されています。### 3. 公認心理師に求められる「新たなスキルセット」今後、公認心理師が医療現場で機能するためには、CBTの技法以外に以下の「医学的リテラシー」が不可欠であると強調されました。* **身体疾患の知識**: 患者は精神疾患だけでなく、糖尿病や慢性腎臓病(CKD)などの身体疾患を併発していることも多いため、それらへの配慮や知識が必要です。* **多職種連携の共通言語**: 医師、看護師、薬剤師と円滑に連携するために、処方薬や一般的な医学知識を身につけ、共通言語で対話できる能力が求められます。---### 今後の活動・勉強会の告知放送の最後には、1月31日に開催される勉強会**「医学の学び舎リバイバル(第16回)」**の告知が行われました。 公認心理師や心理系の学生、医療従事者を対象に、症例を通じてディスカッションを行い、多職種連携や医学的知識を深める場を提供されています。> **AIの視点**: 制度改定を単なる「朗報」とせず、過去のデータから現場の困難さを予測し、教育や連携の重要性を説く非常に実践的な内容でした。
■本日のご質問おはぱんでございます🐼先日の日本健診医学会で、演者さんに質問しそびれたことがあり、こちらに送ってみます。労働安全衛生法に基づき職域で行われる健康診断の検査項目に、いよいよクレアチニン検査が追加される日がきそう、と言う話がありました。以前より、「定期検診の尿検査において尿糖はいらないから、尿潜血を入れてくれぃっ☝️」って話をされていましたが、クレアチニンがあれば尿潜血はなくても大丈夫なのでしょうか?たけお先生のご意見をお聞きしたいです。この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!(匿名でも可能です) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは#心身健康ラジオ#たけおがお答えしますをつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!#医療 #健康 #スタエフ医療部■AI要約(誤字はご勘弁ください)## 健診項目の大転換:クレアチニン導入と腎機能の「可視化」労働安全衛生法に基づく定期健康診断において、腎機能の重要な指標である**クレアチニン**が検査項目に追加されることが決定しました。たけお先生は腎臓内科専門医の視点から、この変更の意義と今後の尿検査のあり方について解説しています。### 1. クレアチニン導入と **eGFR** のメリットこれまでの一般的な職域健診では「尿蛋白」のみが指標となることが多かったのですが、2027年度からはクレアチニンの測定が必須となる見込みです。* **eGFR(推算糸球体濾過量)の算出**: クレアチニンの値から、腎臓が現在どれくらい働いているかを数値化した **eGFR** を計算できるようになります。* **100点満点での理解**: たけお先生は **eGFR** を「100点満点のテスト」に例えています。* **赤点の基準**: **eGFR** が「60点」を切ると慢性腎臓病(CKD)の可能性があり、数値で示されることで、自覚症状がない段階でも患者が自分の状況を把握しやすくなります。### 2. 「尿糖」から「尿潜血」へのシフト提言先生は、現在の健診項目にある「尿糖」を廃止し、代わりに「尿潜血」を優先すべきだと主張しています。* **IgA腎症の早期発見**: 日本人の透析導入原因として多い「IgA腎症」を見つけるには、尿潜血が非常に重要な手がかりとなります。* **尿糖の診断価値の低下**: 血糖値は正常でも体質的に尿に糖が出る「腎性尿糖」があるため、尿糖検査は判定を複雑にさせる側面があります。* **精度の高い血液検査の普及**: 現在は血液検査で血糖値や **HbA1c** を直接測定できるため、あえて精度の低い尿糖で糖尿病を診断する意義が薄れています。* **最新治療薬(SGLT2阻害薬)の影響**: 糖尿病や心不全の治療に使われる **SGLT2阻害薬** は、あえて尿から糖を出す薬です。この薬を服用している場合、健診での尿糖陽性は診断上の意味をなさないという現状があります。---## 結論たけお先生にとって、クレアチニンのない健診は「ハンドルがない車」を運転するような不安な状態でした。今回の義務化により腎機能が明確に数値化されることは大きな前進ですが、現場の医師としてはさらに「尿糖よりも尿潜血」を重視すべきという、より実効性の高い健診のあり方を提言しています。