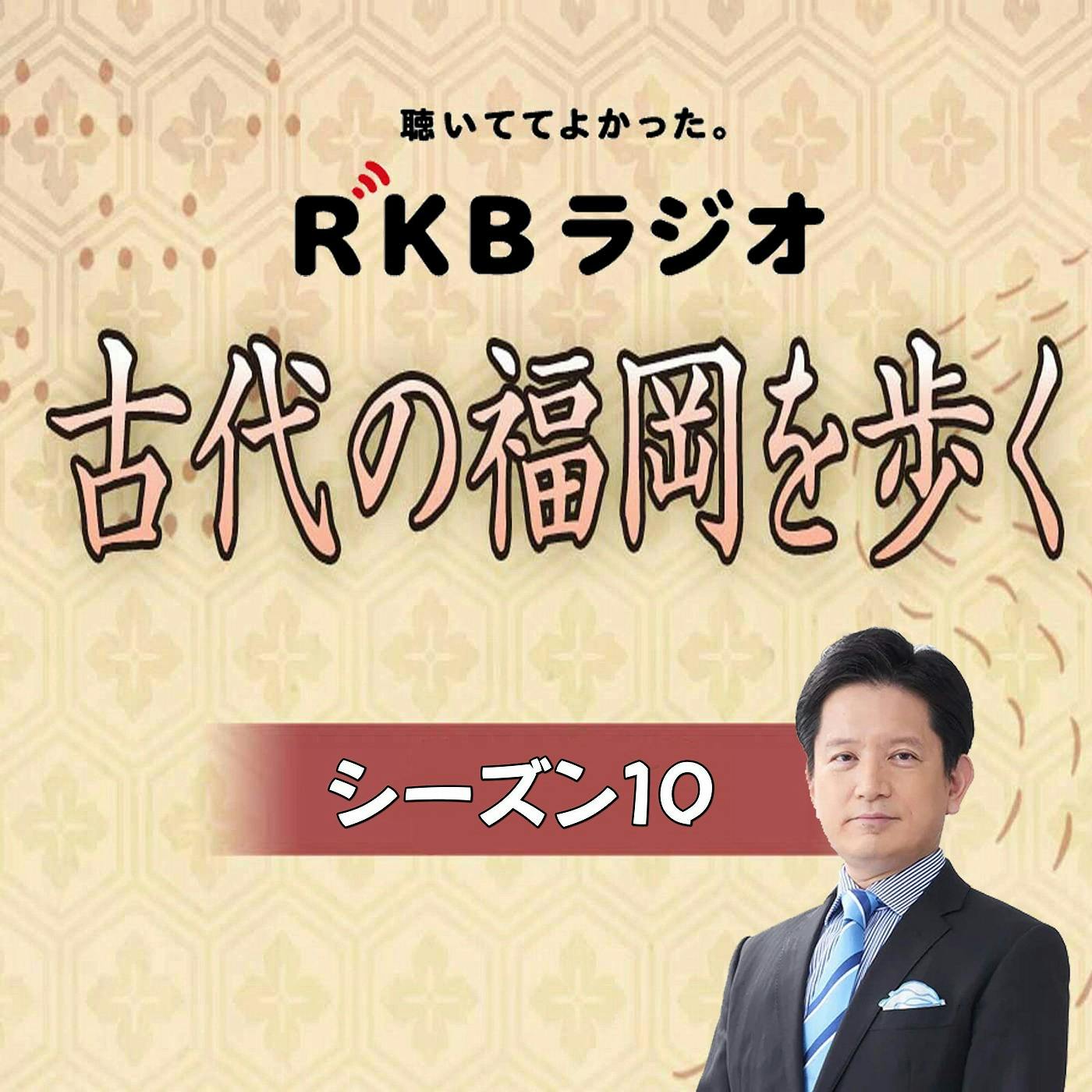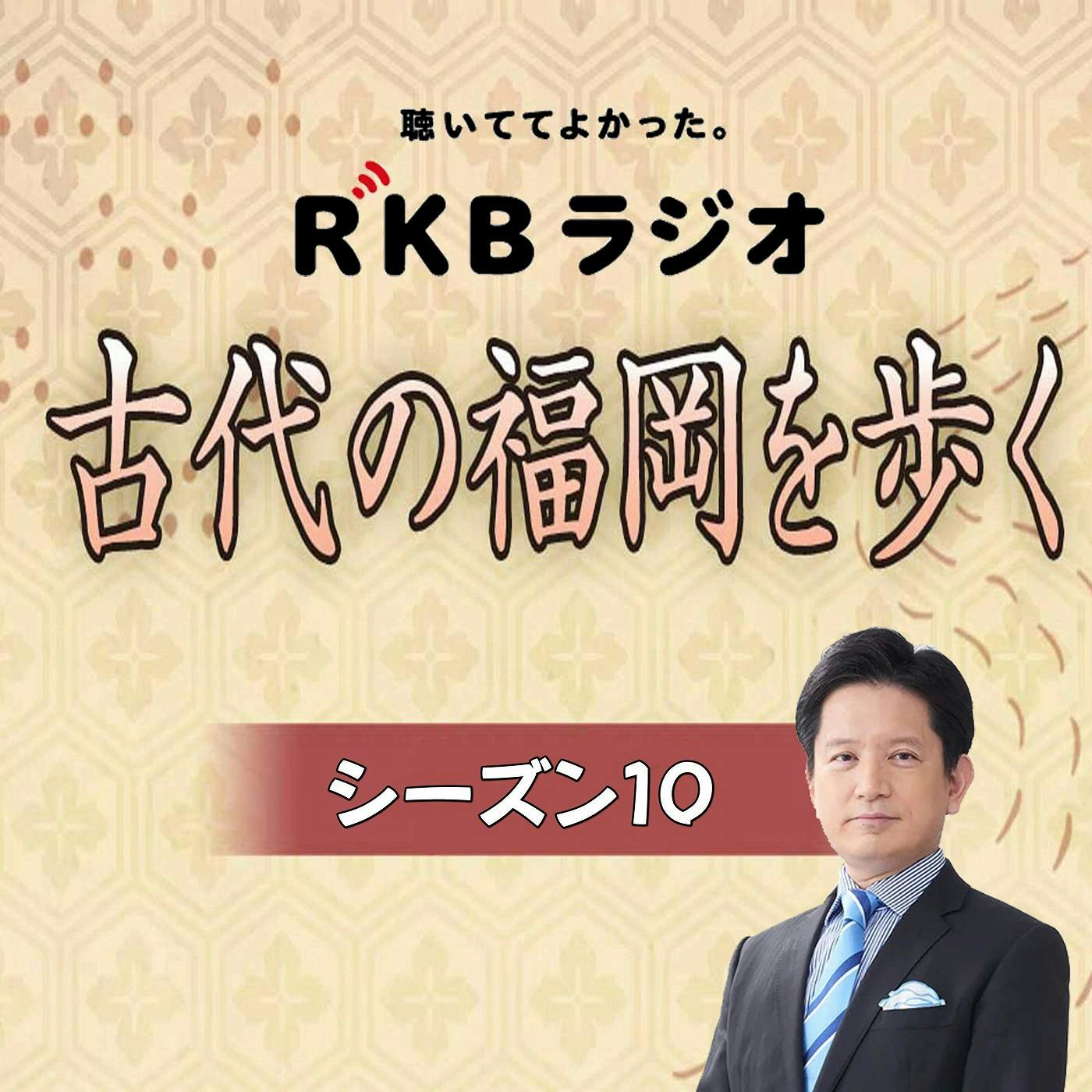Discover 古代の福岡を歩く
古代の福岡を歩く

271 Episodes
Reverse
春日市の須玖遺跡群からこの程一度に3面の小型鏡を作ることができる石製の鋳型の破片が出土しました。
こういった量産用の鋳型は全国でも初めてだということです。
展示会で見てきました。
出土した鋳型は約9センチ四方、厚さ4センチの板状のものです。
しかし、この鋳型で作られた鏡は現在のところ見つかっておらず、どのような使い方をされたのかも判明していないのだとか。
バッジみたいなものだった可能性もありかな?という見方もあるそうです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
浮嶽神社はJR福吉駅近くのまむし温泉から少し坂道を登ったところにあります。
この神社に保管してあるのが九州で最も古いとみられる仏像です。
仏像は如来立像、地蔵菩薩、伝・薬師如来像、そして阿弥陀如来像の4体です。
そして、海岸を東へ出て櫻井神社を歩きました。
ここの楼門や拝殿、本殿は重要文化財の指定をうけていて、実に見事なものでした。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
糸島の可也山のふもと、引津湾に面したところに、敷地面積150坪程の「万葉の里植物園」はあります。
ここには、万葉集に歌われた草花が植えてあります。
万葉集には4516首の歌が登場しますが、その中で草花が出てくるのが200ほどで、その中で糸島にある万葉集の草花は50首ほどだそうです。
引津湾には、大宰府の観世音寺創建の際、中国から仏像を運び、一時保管たしたという寺もあります。
万葉集の中に登場する花で一番多いのが萩、そして二番目が梅だそうで、どこか、大宰府との深いつながりも感じます。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
雷神社は神宮皇后が朝鮮半島に出兵する時、戦勝を祈願したところ。
神社は巨大な木が多く、中には樹齢1000年を超える木もありました。
その神社へ上がってくる途中にある雷山千如寺大悲王院の大楓の紅葉も仏像と同じようにすばらしいものがありました。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
石人山古墳の入り口近くにあるのが資料館。
入口に、近くにある弘化谷古墳の彩色壁画と彫刻文様の複製が展示してあります。
壁画は横2メートル、縦1メートル50センチ程のもので、大きな赤い円や、黒の三角形などの文様がたくさん描かれているのがわかります。
それに、全国的にも大変珍しい双脚輪状文という、塩を吹いた鯨を横にしたような、文様が描かれたいます。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
石人山古墳は、岩戸山古墳の近くにあり、筑紫の君磐井の祖父の代に当たる古墳で、墳丘の長さは120メートル程の前方後円墳です。
古墳の入り口には武装石人像が一体あり、後方にある石棺を守っているかのようです。
石棺は長さ3メートル程の家形石棺で、屋根に刻まれた装飾文様は見事なものです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
岩戸山古墳に隣接してるのが「八女市岩戸山歴史文化交流館、いわいの郷」といった
施設。
「筑後の国風土記・逸文」には岩戸山古墳には、150以上の石人・石馬像があったと記述されているのだそうです。
展示室には盾や刀といった武具や、猪、鶏といった動物などの石像が展示されています。
中でも、実物大の馬の像では、馬の背に「杏葉」といった飾り物が精巧に彫ってあるのは見ものです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
「磐井の乱」については様々に記したものがあります。
筑紫の君磐井は「古事記」「日本書紀」では物部氏と大伴氏によって殺されたとあり、一方「筑後の国の風土記・逸文」には、官軍に追われ豊前の国へ逃げたとあり、さらに、怒った官軍は岩戸山古墳の石人・石馬を壊したとあります。
磐井は殺されたのか、逃げたのか、解りません。。
磐井の乱についてはまだまだ未解明の謎の部分がたくさんあります。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
「古代の福岡を歩く」も11年目に入りました。
八女市の岩戸山古墳から今回はスタートします。
この古墳の墳丘は135メートル。巨大な前方後円墳です。
古墳に葬られているのは、現在のところ筑紫の君磐井だといわれています。
「磐井の乱」で知られる豪族です。
古墳に付属してある別区といわれる広場は石人石馬を飾ったところ。
ここから巨大な古墳の方へと歩いていきます
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
聴いててよかったRKBラジオ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
「神功皇后伝承を歩く」の著者、綾杉るなさんに話を聞いています。
遠賀郡芦屋町の岡湊神社には神功皇后の夫、仲哀天皇の伝承が残っています。
仲哀天皇の船が遠賀川の河口付近で動かなくなります。
案内人の熊鰐の忠告で大蔵主の命とつぶら姫を祀ると船がスムーズに動いたという伝承です。
芦屋は昔から海運で栄えた町。岡湊神社境内の大きな石灯籠は、芦屋や伊万里の商人が寄付したものだそうです。
今回が「シーズン10」の最終回です。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
「神功皇后伝承を歩く」の著者、綾杉るなさんに話を聞いていきます。
九州にいた熊襲が叛乱を起こしたと聞き、仲哀天皇とお后の神功皇后は山口県の豊浦の宮へやってきて、軍勢を整え、それぞれの船で香椎宮へ向かいます。
今回は北九州市戸畑区の飛幡八幡宮、若松区の恵比須神社、魚鳥池神社、貴船神社といった神社に伝わる仲哀天皇と神功皇后の伝説を聞きます。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
四王寺山の古代山城跡、坂本口跡に立つと、はるか遠くまで見渡せます。
四王寺山には景色がすばらしい、ビューポイントがいくつかあります。
その中の1つがここにあります。
遠くに背振山、九千部山、基山が望まれ、目を手前の方にやりますと、道真公が住まいとした榎社や朱雀大路もよく見えます。
ここから、さらに猫坂遺跡郡を見て終着点県民の森センターまで歩きました。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
四王寺山の一番高い所、大城山の山頂近くには毘沙門堂があります。
ここに宇美町の民俗文化財に指定された行事が残っています。
それは「毘沙門詣り」というもので、正月3日参拝の方がお堂の前に置かれたお賽銭を借りて帰り、その翌年、前の年に借りたお賽銭の倍額を返し、また新しいお賽銭を借りて返すという行事です。
このお詣りを繰り返すと一年間お金に不自由しないんだそうです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
古代の山城、大野城跡の宇美町側にあるのが、この遺跡最大の石垣だといわれる百間石垣です。
名前の通り全長180メートルある石垣です。
石垣としては内部にも石を積めた総石垣構造だとか。
また、石垣の下を流れる川からは門の礎石が見つかり、林道近くに城門があったのではないか、とも見られているそうです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
綾杉さんは、安曇族と関係の深い神社として、志賀の島の志賀海神社、大川市の風浪宮、それに福津市の宮地嶽神社をあげます。
その宮地嶽神社の話です。
現在の御祭神は、神功皇后、勝村大神、勝頼大神。
勝村、勝頼は磐井葛子の君の子供だそうです。母親は谷殿といわれ、何者かに襲われ暗殺されたといわれます。
綾杉さんの話はその二人の子供の話からさらに広がっていきます。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
20回目は安曇族の足跡について綾杉るなさん(神功皇后伝承を歩くの著者)に聞きます。
安曇族は、かつて信州・安曇野に百済仏を持ち込んだのでは、といわれます。
これについての綾杉さんの説です。
百済の聖明王の王子~余昌が命を狙われた時に、葛子の子供である鞍橋(くらじ)の君が助けます。
その時のお礼に贈られたのがその仏像ではなかったか、という説です。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
百間石垣のすぐ近くにあるのが短い石垣だけが残る小石垣です。
石垣の下には、かつてあった城門の跡が残っていました。
百間石垣の方へ歩いていきますと、途中目に入ってくるのが滝です。
「鮎返りの滝」と呼ばれる滝で、ここは昔から滝行で知られた場所だということでした。
それ程大きくはない滝ですが、滝の下へ行ってみますと、たくさんの石仏がありました。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
空海伝説が伝わる観音山大徳寺。観音山は高さが132メートルの山です。
空海が残したものとしては、山の中腹にある奥の院の大岩に手彫りの梵字があります。
また、本堂には空海(弘法大師)お手植えの松に書いた「夫れ仏法 遙かなるに非ず心中に即ち近し」という言葉が残されています。
※写真は梵字
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
那珂川市の中原というところに空海の伝説を伝える大徳寺があります。
空海は遣唐使として中国に渡った人で知られていますが、帰国後大宰府の観世音寺におよそ2年間程住んでいました。
この間、中原の大徳寺も訪ねてきています。
その際、空海はこの寺に残していったものが今もあります。
その大徳寺を歩きます。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices