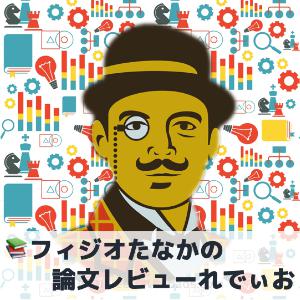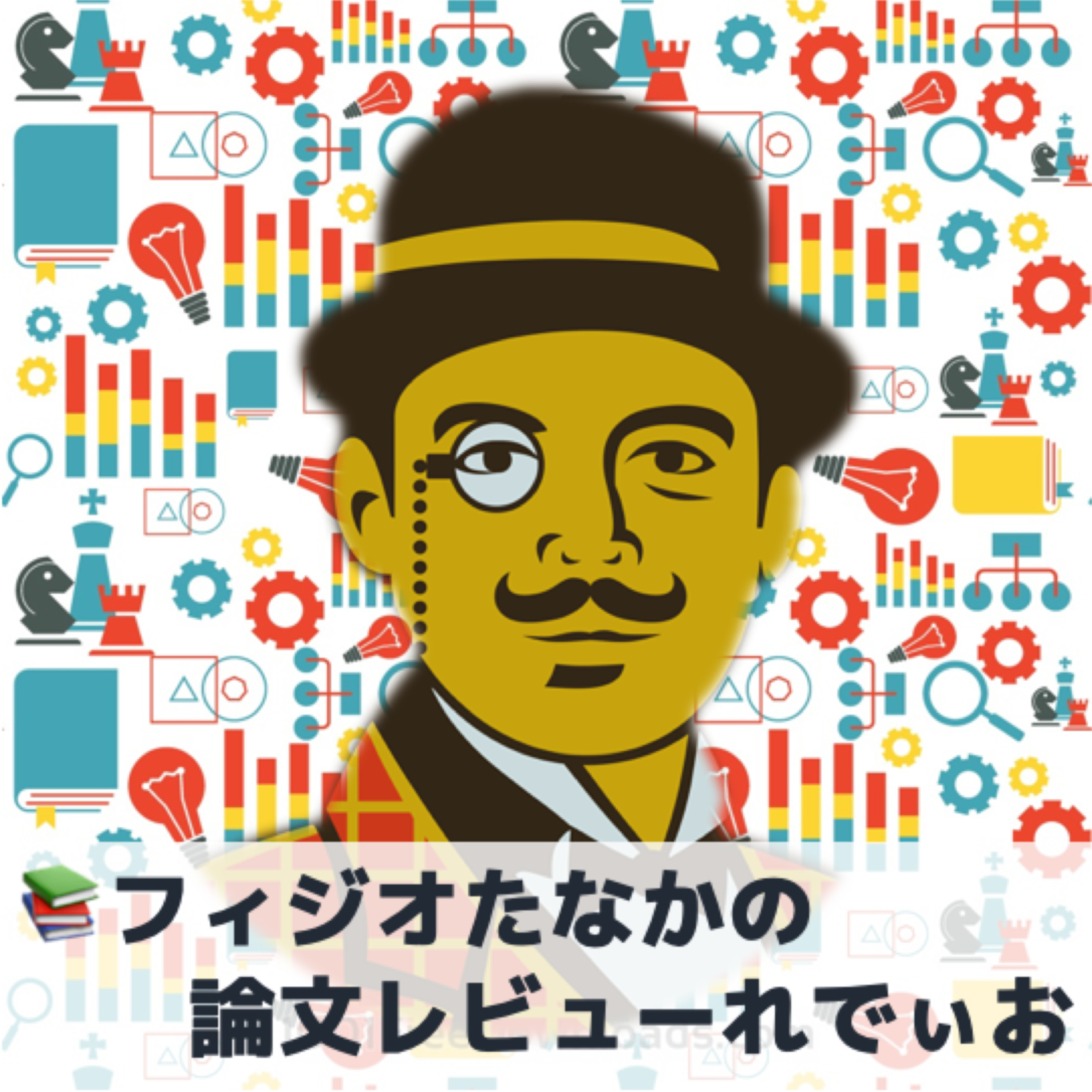Discover 欧州トレーナーのふたりごと
欧州トレーナーのふたりごと

欧州トレーナーのふたりごと
Author: Tatsuki Nakata
Subscribed: 2Played: 13Subscribe
Share
© Tatsuki Nakata
Description
オランダでプロサッカーチームのトレーナーをしている2人がテーマに沿って駄弁ります。
経歴
- 中田 樹
立命館大学スポーツ健康科学部卒業。大学卒業後、オランダに渡りフィジオセラピー(理学療法)の資格を取得。トレーナーとしてアマチュアチームを転々としたり、理学療法クリニックで働いたりを経て、現在はオランダ2部リーグのHelmond Sportでパフォーマンスコーチ兼フィジオとして活動中。
クラブ歴: PVC Utrecht (7部) →OJC Rosmalen (5部) →VV Hoogland (4部) →VV Hooglanderveen (7部) →Helmond sport (2部)
X: https://twitter.com/nakata_tatsuki
犬塚健太
首都大学東京(現:都立大学)、筑波大学大学院を卒業後渡蘭。バレーボールチーム1部、アマチュアサッカークラブを経てオランダサッカー1部のFC Volendamで活動中。保有資格は理学療法士(日本、オランダ)、日本スポーツ協会AT、鍼灸師(オランダ)。
クラブ歴:ASV de Dijk (5部) →VV Noordwijk (3部) →FC Volendam (1部)
経歴
- 中田 樹
立命館大学スポーツ健康科学部卒業。大学卒業後、オランダに渡りフィジオセラピー(理学療法)の資格を取得。トレーナーとしてアマチュアチームを転々としたり、理学療法クリニックで働いたりを経て、現在はオランダ2部リーグのHelmond Sportでパフォーマンスコーチ兼フィジオとして活動中。
クラブ歴: PVC Utrecht (7部) →OJC Rosmalen (5部) →VV Hoogland (4部) →VV Hooglanderveen (7部) →Helmond sport (2部)
X: https://twitter.com/nakata_tatsuki
犬塚健太
首都大学東京(現:都立大学)、筑波大学大学院を卒業後渡蘭。バレーボールチーム1部、アマチュアサッカークラブを経てオランダサッカー1部のFC Volendamで活動中。保有資格は理学療法士(日本、オランダ)、日本スポーツ協会AT、鍼灸師(オランダ)。
クラブ歴:ASV de Dijk (5部) →VV Noordwijk (3部) →FC Volendam (1部)
28 Episodes
Reverse
今回は一人でピリオダイゼーションに関する論文レビューです。
マイク買ったので音質いいはずです。
ハムストリング損傷はサッカーにおいて最も発症率の高い怪我。その評価について今回は語っていきます。
前編では発生直後のピッチ上での評価。
後編ではその後のピッチ外での評価について語っていきます。
ハムストリング損傷はサッカーにおいて最も発症率の高い怪我。その評価について今回は語っていきます。
前編では発生直後のピッチ上での評価。
後編ではその後のピッチ外での評価について語っていきます。
みなさん、はじめまして!たなかです。
毎週1個づつぐらい論文のレビューを当分やっていこうと思います。
チャンネル登録お願いします!
#論文レビュー #スポーツサイエンス #怪我予防
・参考文献
Weston, M. (2018). Training load monitoring in elite English soccer: a comparison of practices and perceptions between coaches and practitioners. Science and Medicine in Football, 2(3), 1–9. https://doi.org/10.1080/24733938.2018.1427883
みなさん、はじめまして!たなかです。
毎週1個づつぐらい論文のレビューを当分やっていこうと思います。
チャンネル登録お願いします!
#論文レビュー #スポーツサイエンス #怪我予防
・参考文献
Van Hooren, B., & Peake, J. M. (2018). Do We Need a Cool-Down After Exercise? A Narrative Review of the Psychophysiological Effects and the Effects on Performance, Injuries and the Long-Term Adaptive Response. Sports Medicine, 48(7), 1575–1595. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0916-2
Dupuy, O., Douzi, W., Theurot, D., Bosquet, L., & Dugué, B. (2018). An Evidence-Based Approach for Choosing Post-exercise Recovery Techniques to Reduce Markers of Muscle Damage, Soreness, Fatigue, and Inflammation: A Systematic Review With Meta-Analysis. Frontiers in Physiology, 9, 403. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00403
みなさん、はじめまして!たなかです。
毎週1個づつぐらい論文のレビューを当分やっていこうと思います。
チャンネル登録お願いします!
#論文レビュー #スポーツサイエンス #怪我予防
・参考文献
Brockett, C. L., Morgan, D. L., & Proske, U. W. E. (2004). Predicting hamstring strain injury in elite athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36(3), 379-387.
Clark, R., Bryant, A., Culgan, J. P., & Hartley, B. (2005). The effects of eccentric hamstring strength training on dynamic jumping performance and isokinetic strength parameters: a pilot study on the implications for the prevention of hamstring injuries. Physical Therapy in Sport, 6(2), 67-73.
Freckleton, G., & Pizzari, T. (2013). Risk factors for hamstring muscle strain injury in sport: A systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 47(6), 351–358. https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090664
みなさん、はじめまして!たなかです。
毎週1個づつぐらい論文のレビューを当分やっていこうと思います。
チャンネル登録お願いします!
#論文レビュー #スポーツサイエンス #怪我予防
・参考文献
Dupuy, O., Douzi, W., Theurot, D., Bosquet, L., & Dugué, B. (2018). An Evidence-Based Approach for Choosing Post-exercise Recovery Techniques to Reduce Markers of Muscle Damage, Soreness, Fatigue, and Inflammation: A Systematic Review With Meta-Analysis. Frontiers in Physiology, 9, 403. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00403
Van Hooren, B., & Peake, J. M. (2018). Do We Need a Cool-Down After Exercise? A Narrative Review of the Psychophysiological Effects and the Effects on Performance, Injuries and the Long-Term Adaptive Response. Sports Medicine, 48(7), 1575–1595. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0916-2
筋力や筋力のインバランスでハムストリングの肉離れのリスクが上がるとあれだけ噂されていましたが、
現状の科学では、それはないという風になっています。
自分は筋力がハムストリング損傷を起こすと信じて止まなかったの側の人間なので正直ショックです。
ですが、これが絶対なのか?というとまだ何か引っかかる節があるなぁというのが個人的な意見です。
みなさん、はじめまして!たなかです。
毎週1個づつぐらい論文のレビューを当分やっていこうと思います。
チャンネル登録お願いします!
#論文レビュー #スポーツサイエンス #怪我予防
・参考文献
Green, B., Bourne, M. N., & Pizzari, T. (2018). Isokinetic strength assessment offers limited predictive validity for detecting risk of future hamstring strain in sport: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 52(5), 329–336. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098101
統計って分かってるようで分かってないもんだと思うんですよね。
と言うわけで、統計の第一段階と言えるT検定とP値について解説していきました。
甘噛み感は有意にひどいです。
あと、途中からT検定がT値になってますが、それは帰無仮説です。
みなさん、はじめまして!たなかです。
毎週1個づつぐらい論文のレビューを当分やっていこうと思います。
チャンネル登録お願いします!
#論文レビュー #スポーツサイエンス #怪我予防
みなさん、はじめまして!たなかです。
毎週1個づつぐらい論文のレビューを当分やっていこうと思います。
チャンネル登録お願いします!
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC_Iqt2uSE4rBaHTG-UA5VIg
Twitter:
@nakata_tatsuki
#論文レビュー #スポーツサイエンス #怪我予防
・参考文献
みなさん、はじめまして!たなかです。
毎週1個づつぐらい論文のレビューを当分やっていこうと思います。
チャンネル登録お願いします!
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC_Iqt2uSE4rBaHTG-UA5VIg
Twitter:
@nakata_tatsuki
#論文レビュー #スポーツサイエンス #怪我予防
・参考文献
Freckleton, G., & Pizzari, T. (2013). Risk factors for hamstring muscle strain injury in sport: A systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 47(6), 351–358. https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090664
プロクラブでの1シーズン目を終えたのでシーズンを振り返りに続き、スケジールについて。
シーズンも終盤ということで、今シーズンを振り返ります。
テーピングのメリット&デメリット
リスクファクターの評価
足首捻挫シリーズ。
- メディカルリハからアスリハへの移行
- 練習復帰の基準
- リハステップの考え方
足首捻挫シリーズ。
ギプスによる固定をした場合のメリット&デメリット
固定後の予後
早期に運動療法を始めることのメリット&デメリット
Optimal loadとは
足首捻挫シリーズ。今回は受傷直後の対応どうするか。
- アイシングするか
- よく使われるクリームに意味はあるのか。
- コンプレッションの方法
(U字パッドを使うか、テープによるコンプレッションだけにするか。そのメリット&デメリット)
足首捻挫シリーズ。前回はオンフィールドでの評価でしたが、今回はその後のオフフィールドの評価。
エコーを使うのか、MRIは撮るのか、また、損傷具合の評価はどこまで大事なのか、など話していきます。
今回からは足首捻挫シリーズ。第一回は発症時に評価。