発達障害のコミュ力への苦手意識は「リズム感」がないことが原因?!
Description
導入音声
※今回の記事をどういう人に読んでもらいたいか。何を得られるかを5分以内で話している音声です。よかったら聞いてみてください。
今回は論文をとりあげます!
どうもNEIです。
前々からブログで触れよう触れようと思いながら、時だけが流れていった研究論文について今回は触れようと思います。その論文の主旨は以下のとおり。
船曳康子 人間・環境学研究科准教授、川崎真弘 筑波大学准教授、村井俊哉 医学研究科教授、山口陽子 理化学研究所チームリーダー、北城圭一 同連携ユニットリーダー/副チームリーダー、深尾憲二朗 帝塚山学院大学教授らの研究グループは、自閉スペクトラム症(社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害と、限定された反復する様式の行動、興味、活動を特徴とする、神経発達症の中の一群)者がコミュニケーションをとる上での困難には、他者が示すイレギュラーなリズムへの適応が困難であることが関係していることを、行動データと脳波データ解析により見出しました。今回見出された結果から、自閉スペクトラム症の二大特徴である、社会的コミュニケーションの障害とこだわり傾向の強さは、イレギュラーさに適応することの困難さにより統合的に説明できる可能性が拓かれました。
自閉症スペクトラム性障害の人たちの
「コミュニケーションへの苦手さ」
「こだわりの強さ」
という特性を
イレギュラーなリズムへの対応の困難さ
によって説明可能なのではないかということを実験によって確かめようとしたものです。これは僕の色んな発達障害の当事者を見てきた経験から言ってもかなり的を射た研究ではないかと思いました。
コミュニケーションへの苦手さは皆多かれ少なかれあるとは思いますが、その中でもコミュニケーションがそれなりに出来る人とまったく出来ない人がいます。
単純に障害の程度が重いか軽いかでもあるのかもしれませんが、それよりもその人が「音楽に携わってきたのかどうか」が結構関係しているように思います。
それを今回の研究が裏付けてくれたなっていう感じですね。
メラビアンの法則
メラビアンの法則というのをご存じでしょうか?
メラビアンの法則とは、1971年にアメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱した概念で、話し手が聞き手に与える影響を、研究と実験に基づいて数値化したものです。別名「3Vの法則」や「7・38・55ルール」と呼ばれる事もあります。
具体的には、話し手が聞き手に与える影響は「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」の3つから構成され、それぞれの情報の影響力は以下の割合であるというものです。
- 言語情報(Verbal)…7%
- 聴覚情報(Vocal)…38%
- 視覚情報(Visual)…55%
⇒メラビアンの法則とは? より引用
「聴覚情報」というのは言語ではなく、話し方や声のトーン、言葉と言葉の間隔などから得られる情報です。
「視覚情報」というのは外見・表情・ジェスチャー・目線など目から得られる情報のことですね。
僕たちは「コミュニケーションと言えば言葉でっしゃろ!」みたいに捉えがちですが、
言葉によるコミュニケーションは全体の7%しかないという考え方です。これ初めて知ったときはかなり意外でした。
コミュニケーションのうまい下手は「言語力」とはほぼ関係ない?!
このメラビアンヌの法則から言えることとして、
「コミュニケーション力がない」という問題は、「言語力」とは関係なくてそれよりも
見た目や目線、ジェスチャー、喋り方の抑揚・トーン・間などなど
が原因じゃないか?
ということです。
僕はナンパ師として一時期活動していたのでこのあたりは非常に実感として味わいました。
女の子に話しかけたときの反応は「言葉がうまい」とかよりも
「背筋が伸びてるか?」とか「早口にまくしたててないか?」とか「相手の目を見ているか?」とかの方がかなり影響が大きかったんですよね。ナンパをある程度出来るようになった人も口をそろえてこのあたりを指摘しています。
特に“間”と“抑揚”
で、今回の研究から言えることとして発達障害の人がコミュニケーションにおけるイレギュラーなリズムというやつを苦手としているということです。
コミュニケーションのどこにリズムが発生しうるのかといえば2つあります。①「会話の抑揚」と②「喋っているときと黙っているときのリズム=間」です。
それぞれについてみて行きましょう。
①会話の抑揚
発達障害の人の独特の喋り方として淡々と抑揚なく喋る、というのが見られます。
文章を話すとき、アクセントをどこに置くか。どこは小さい声でさらっと流して、どこを大きい声で強調するか、みたいなことを意識すると伝えたいことがより伝わり易くなります。
「今から準備してちょっと銀行に行ってくるわ。」
ということを話すとき、
「今から準備してちょっと銀行に言ってくるわ。」
と「準備して」で声を大きくするのと
「今から準備してちょっと銀行に言ってくるわ。」
と「銀行に」の部分で声を大にするのとでは大分伝わり方がちがいます。銀行に行くことを伝えたいのであれば、最悪「銀行」という部分だけ聞こえれば大丈夫ですよね。
しかし、発達障害のある人は話し方が単調です。どこにアクセントを置いているのかがわかりにくく、そうなると伝えたいことが伝わりにくくなってしまいます。
これは話し方の抑揚というリズムについて意識が働きにくいという特性が多少影響しているように思われます。
②会話の“間”
次にリズムが生まれるポイントが、会話の間です。
これは分かりやすいですね。
喋っているときと、空白の時間があるので当然そこにはリズムが生まれます。
よく発達障害の人で、
「いつ喋り出してよいかわからない」
ということを言う人がいますが、これは
相手が喋り出すタイミング、小休止するタイミングがわからない
ということではないでしょうか。
いざ喋ろうとしたら、相手も同時に喋り出してしまったとか
いつ会話が終わるのかわからないからずっと相槌しか打てないとか
そういう経験があるんじゃないでしょうか。
こういうのもイレギュラーなリズムとして見ることができると思います。
余談:集団での会話
発達障害の人の困りごとで、
・集団での会話がニガテ
というものがあります。
これも「イレギュラーなリズム」理論から考えると分かりやすいです。
次の図をご覧ください。
<figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_1805">
 <figcaption class="wp-caption-text">集団での会話</figcaption></figure>
<figcaption class="wp-caption-text">集団での会話</figcaption></figure>このように、
Aさんの「空白の取り方のリズム」と
Bさんの「空白の取り方のリズム」はちがいます。
会話の間が長い人と短い人がいますからね。
そのときイレギュラーなリズムに対応できない僕たちは
2人分のリズムに対応しないといけないわけです。
「一人でも厳しいのに2人って・・・」
ってなりますよね。
そうやって考えると、AさんBさんだけじゃなく、
さらにCさんDさんEさんと増えて集団になってくると
その難しさはウナギ登りですよね。
まとめ
今回は
「イレギュラーなリズムへの対応の困難さ」という論文を
とりあげ、
『メラビアンの法則』にも触れながら
コミュニケーションで大きな部分をしめているのは
「言語以外の間や抑揚、トーン、ジェスチャーなどである」
ということをお伝えし、
その中でも①抑揚、②間というのがリズムを伴うものであるため
発達障害の人は会話が苦手となるのではないか?
ということについて触れました。
コミュニケーションの苦手さというのは、発達障害の人の最も辛い特性であるというように思われがちですが、実はコミュニケーションが苦手なのではなくリズムを取るのが苦手なんだという風に捉えると
「自分はダメなんじゃないか」
という気持ちは少し和らいでくるのではないかと思い、今回の記事をしたためさせていただきました。
そんな風に「視点や考え方を変える」ことで自分の障害をただただダメなモノだという風に捉えてしまうことから抜け出すことができます。そのための視点や考え方を無料メルマガにて継続的に提供しておりますので、興味のある方はぜひコチラから登録してみてください。
52:15 07">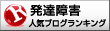
52:15 07">発達障害ランキング
※人気ブログランキングに参加しています。応援のバナークリックをよろしくお願いします。
それでは、今回は以上です。お読みいただきありがとうございました。













