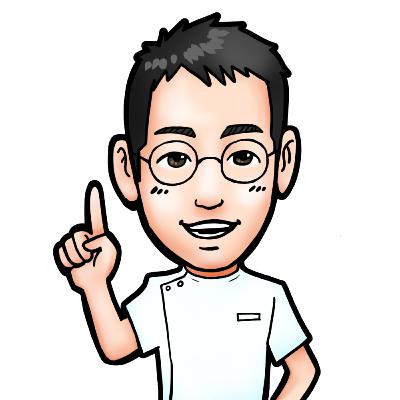《1345》不眠に対して睡眠薬💊は間違いです‼️
Description
チョイス@病気になったとき
「不眠症・むずむず脚症候群 治療情報」
https://www.nhk.jp/p/kenko-choice/ts/7JKJ2P6JVQ/episode/te/7M3NQMVM14/
この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!
(匿名でも可能です)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog
面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは
#心身健康ラジオ
#たけおがお答えします
をつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください!
#医療
#健康
#スタエフ医療部
■AI要約(誤字はご勘弁ください)
内科医たけお氏が、自身のイベント参加経験とNHKの番組『チョイス』の内容を元に「不眠症」について解説します。
**【不眠症の現状とリスク】**
たけお氏は、イベントで多くの人が睡眠に悩んでいることを再認識したと語ります。令和元年の調査では、20歳以上の約2割が何らかの不眠症状(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)を抱えているとされています。不眠を放置すると、高血圧や糖尿病といった生活習慣病のほか、心筋梗塞や認知症のリスクも高まるため、軽視はできません。
**【治療の第一歩は生活習慣の改善】**
不眠治療において最も重要なのは、薬に頼る前の「生活習慣の改善」です。病院を受診すると睡眠薬が処方されがちですが、その前に試すべきことがあります。
1. **睡眠日誌をつける**
不眠治療において「睡眠日誌なくして治療はできない」と言われるほど重要です。就寝時刻、起床時刻、睡眠の質などを記録することで、自身の睡眠パターンを客観的に把握できます。これにより、医師も正確な状態を理解しやすくなり、適切な治療方針を立てる助けとなります。記憶に頼らず記録することが大切です。
2. **寝室のルール**
寝床で眠れないままモンモンと過ごすのは逆効果です。眠れない時は一度寝室を出るなど、「寝る時以外は寝室にいない」というルールを徹底することが推奨されます。
3. **高齢者の注意点**
高齢になると長く眠る体力がなくなるため、無理に長時間寝ようとするとかえって不眠が悪化することがあります。国のガイドラインでも「寝床にいるのは8時間以内に」と推奨されています。
**【睡眠薬の種類と特徴】**
生活習慣を改善しても眠れない場合は、睡眠薬が選択肢となります。現在、主に3種類の薬が使われています。
1. **GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン系など)**
従来から使われている薬で切れ味は良いですが、依存性や耐性(薬が効きにくくなること)が問題となり、新規での使用は減少傾向にあります。
2. **メラトニン受容体作動薬**
自然な眠りを促すホルモンに作用する薬で、依存性のリスクが低いのが特徴です。
3. **オレキシン受容体拮抗薬**
脳を覚醒させる物質の働きを抑える新しいタイプの薬です。こちらも依存性が少なく、現在の主流となりつつあります。ただし、副作用として悪夢を見ることがあるため注意が必要です。
**【不眠の裏に隠れた病気】**
不眠の原因が、単なる不眠症ではなく別の病気である可能性も考慮すべきです。
* **むずむず脚症候群**
脚に不快な感覚が生じて眠れなくなる病気で、特に透析患者に多く見られます。睡眠薬だけでは改善しないため、専門的な治療が必要です。
* **睡眠時無呼吸症候群**
睡眠中に呼吸が止まることで眠りが浅くなります。この状態でベンゾジアゼピン系の睡眠薬を使用すると、症状が悪化する危険性があるため、不眠の原因を正確に見極めることが極めて重要です。
たけお氏は、安易に睡眠薬に頼るのではなく、まずは生活習慣を見直し、不眠が続く場合は専門医に相談して、背景にある病気も含めて適切な診断と治療を受けることの重要性を強調しました。