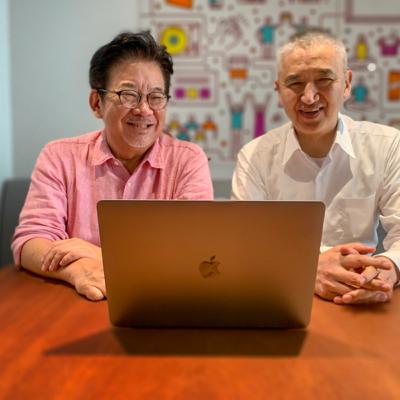Discover 組織ラジオ
いまのたかの
組織ラジオ
いまのたかの
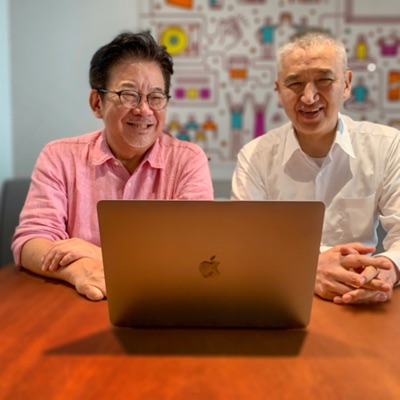
250 Episodes
Reverse
前回の個人の効力感に続き、今回は集団や組織が持つ効力感です。
具体的にはメンバーが「自分たちならできる!」「この仲間とならきっとやり遂げられる」と思っている状態です。
スポーツでも職場でも、チーム全体が効力感を持っている時には1+1が3にも4にもなるものです。
分解してみると、「自分たち」というチームを自分と同じように捉えているチームが作られていることが前提です。
自己効力感の高い個人が集まっただけでは組織効力感にはなりません。
そして「できる」と思えていること。
そのためには成功体験と、成功を振り返る自己教示、つまり自分たちを認め、褒めることが重要です。
この番組はSpotify for Podcastersのほか、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
組織改革コンサルタント歴25年の今野が辿り着いたのは“効力感”の重要性でした。
それを理論化し、実践で使えるメソッドにしたのが社名の由来でもあるGood & Moreです。
A・バンドゥーラ教授が提唱した自己効力感とは「自分ならできる」「きっとうまくいく」と信じることができる認知のことです。
その逆を考えてみれば「自分にはできない」「きっとうまくいかない」という認知になります。
高い目標を追い続ける企業組織において、そのどちらが組織を活性化し、強くし、成果を出すのかは自明のことでしょう。
そしてバンドゥーラ教授は、自己効力感には4つの要素があるとあるとしています。
個々人の自己効力感が高い組織を作るには、この4つの要素(達成経験・社会的説得・代理経験・生理的感情的状態)を備えることです。
その4要素とは具体的にはどんなことを指しているのでしょう。
今回は、個々人の“自己効力感”についてお話ししています。
次回は、“集団効力感(組織効力感)”について取り上げる予定です。
この番組はSpotify for Podcastersのほか、Podcast、Google Podcastでのお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」をクリック!
今野が“中の人”になった会社は社員数が約30人。
全社員が本業の現場の仕事をしながら、人事・総務・経理・広報の4つの委員会のひとつに所属して二刀流で活動しています。
現場でのお客さまや取引先と相対する視点と、管理部門での全社視点を同時に経験させているのです。
これは経営の疑似体験に他なりません。
小集団活動による組織の活性化だけでなく、個々人も経営としての高い視座を共有するようになり、個人も成長し組織も高いレベルに上がることになります。
30人だからこそできることでもありますが、将来会社が100人になり、300人になり、500人になった時、この30人が組織のさまざまな場所で中核になっていることは想像に難くありません。
アレンジ次第では大企業でも組織単位で実行可能な施策です。
この番組はSpotify for Podcasters のほか、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
ダブルバインドという言葉があります。日本語では二重束縛。矛盾した2つのメッセージに束縛されることです。
今日はそんな話から始まりましたが、いつもの通り、話は次々に展開していきました。
リーダーは朝令暮改になることを恐れず、今ここで正しいと思う判断をして指示を出さねばなりません。
その時に、判断の背景と理由も伝えないと、指示を聞いている側には一貫性が無いように映ることもあります。
さらに進めると、リーダーの判断の理由と背景には、そのリーダーの価値観や生き様が無意識のうちに投影されています。
そこまで理解しているか否かで受け止める側の認識がずいぶん違うものです。
これを打破するために今野が発案し効果をあげた手法も含めてお話ししています。
この番組はSpotify for Podcastersの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
今野があるクライアントの要請で“社内”取締役に就任することになりました。
起業して25年の今野にとって、25年ぶりに組織の「中の人」になったのです。
そこで今野が感じたことはエンプロイアビリティの重要性。そしてリクルートマネジメントソリューションズの超ロングセラー商品であるOBS(Organization Behavior Survey)とLDP(Leadership Development Program)における「対上司リーダーシップ」の重要性でした。
リーダーシップとは影響力のことです。組織において人は部下に対する影響力だけでなく上司に対する影響力を発揮することも組織にとって重要なことなのです。
長年コンサルタントをしてきたので十分に理解していたことなのですが、25年ぶりに組織の「中の人」になったからこそ感じた重要性。
それはきっと、今、組織の中でがんばっているみなさんの参考になると思います。
この番組はSpotify for Podcastersの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
身体の健康を保つには人間ドックや健康診断など定期検診による早期発見が肝要です。
組織は生き物。日々刻々変化しています。
自覚症状がないまま事業成長に不都合な病気が生まれ、悪化しているかもしれません。
これを防ぐためには身体と同様、定期メンテナンスをして予兆を見逃さず早期発見、早期治療をすることが大切です。
どんな経営戦略も事業戦略も、それを実行するのは組織。
組織の定期メンテナンスは、緊急ではないが重要な経営課題なのです。
手遅れにならないうちに組織の定期メンテナンスを毎年のカレンダーに入れておくことをお勧めします。
この番組はSpotify for Podcastersの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
経営から新たな指示が降りてくるとき、メンバーは経営の本気度を探っています。組織改革など大きな変化があるときは尚更です。
経営が本気だと思えばやりますが、いつの間にか立ち消えになるなら無駄なことはしたくないからです。
つまり、経営の本気度がメンバーに伝わらなければ組織は動きません。
本気度を伝えるために、経営者はどうすべきでしょう。
また中間管理職はどうすべきでしょう。
『組織ラジオ』はSpotify for Podcastersの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
バックナンバーは「いまのたかの」を検索!
新入社員が入社してもうすぐ3ヶ月。
育成の進捗はいかがですか?
専ら役員クラスのコーチをしている今野が珍しく新入社員のコーチをしています。
そこで気づいたことの中から3つの症候群を選んでお話ししました。
名付けて(その場で名付けたのですがw)
①「守破離の守」症候群
②「何でもかんでも学ぼう」症候群
③「素振り100回」症候群
髙野が振り返っても「あるある」です。
これらの症候群に陥らせいないために大切なことは「魚が欲しい人に、魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える」ことだと言ってもいいでしょう。
「成長」と「馴れ」は異なるものです。
初めは恐る恐るだったのに、遠慮なく魚をもらえるようになるのは「馴れ」。
環境や獲物が変わっても、自分の力で魚を釣れるようになるのが「成長」。
みなさんの周囲の新入社員は「成長」していますか?
この番組はSpotify for Podcastersのほか、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
バックナンバーは「いまのたかの」を検索!
前回取り上げた“マクナマラの誤謬”にはさまざまな反響をお寄せいただきました。
そのなかでリスナーの柴田教夫さんに教えていただいた「爆撃機の装甲」という話。
目の前にあるデータを鵜呑みにせず、見えないデータを見ることの重要性を説いた話です。
そんな折、高野はクライアントのCS(カスタマーサクセス)部門のマネージャーから相談を受けたのです。
経営から降りてきた「解約率1%」という目標に違和感を覚え、それに変わってこんな目標を考えているがどう思うかという相談でした。
それはまさにマクナマラの誤謬と爆撃機の装甲の話でした。
さっそく簡単な資料を作成して、CS部門のメンバーとセッションを行ってみると、目標を変えただけで見違えるように元気になり、アイデアが湧くのです。
その姿を見て高野は、28年前に自分がよく似た経験をしていたことを思い出しました。
マクナマラの誤謬と爆撃機の装甲。それは時を超え、場を超えて、いつどこでも起きることだったのです。
この番組はSpotify for Podcastersの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
来月でコンサル開業25周年を迎える今野の、最初のクライアントでの失敗談から話はスタート。
それはまさに“マクナマラの誤謬”でした。
奇しくも5月29日放送のNHK「映像の世紀 バタフライエフェクト」のテーマがベトナム戦争時の米国国防長官マクナマラの誤謬。
“マクナマラの誤謬”とは定量的な観察のみに基づいて決定を下し、定性的な観察を無視するために全体像を見失うことを言います。
企業においてもKPIの設定、評価項目の設定において定量的なものだけに偏っていたり、あるいは定性的な観察をしないために数字の意味が正しくなかったりすることがあります。
その結果、その定量目標は組織をミスリードします。
ベトナム戦争と同様、「KPIは達成しているのに戦争には敗けている」という恐ろしい結果を招きかねません。
みなさんの周囲に、気づかぬうちに存在する“マクナマラの誤謬”はありませんか?
この番組はSpotify for Podcastersのほか、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
6月に入り、新入社員に対して本格的なOJTを開始する会社も少なくないでしょう。
新入社員が一定の規模の人数になると人事部が直接育てることよりも現場のOJTの比重が重くなります。
だとすれば人事部の最も大切な仕事は「人を育てることができる人」を育てることだと言えます。
しかし多くの会社では、OJT担当者の選抜に際してどんな社員に適性があるのかを深めることなく選抜していないでしょうか。
また選抜したOJT担当者に、OJTとは何で、どうすることなのかを学ぶOJT担当者研修を実施している会社も少ないように思います。
今回はOJTとは何をすることで、どんな人にOJT 担当者としての適性があり、どんな人は不向きなのかを語り合いました。
人事部の方々だけでなく、組織で働くみなさんは多かれ少なかれOJTを担っているはずです。
みなさんのご参考になろのではないかと思います。
この番組はanchor for Podcastersの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
個々のメンバーが優秀であっても、集団で決すると間違っていたり、浅くなってしまっている結論に達することがあります。
それが起きる4つの要件とそれが起きる理由、そしてそれを防ぐ4つの対策があります。
元々は政治における集団浅慮の研究成果ですが、実は企業組織にも当てはまります。
特に若いベンチャー企業に起きそうな要件ですが、大企業でも伝統ある中小企業でも、また会社全体ではなく部署単位でもその要件の全部または一部が揃ってしまう危険があります。しかもそれは、自分たち自身では気づきにくいものです。
みなさんの組織にこの4つの要件がないか、点検してみてはいかがでしょう。
この番組はSpotify for Podcastersのほか、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
マネージャー向けの教育研修と既成概念ができている幾つかの教育プログラム。
それをあえて役員からメンバーまで行うことにした会社。これが大きな効果を生んだという話から始まりました。
例えばコーチングやファシリテーションは、管理職向けのスキルだとされてきました。
発想を変えて、メンバーにもコーチングやファシリテーションの教育機会を提供します。
するとコミュニケーションの質が格段に上がり、加えて効率的なコミュニケーションが行われるようになるのです。
企業規模などにより工夫は必要かと思いますが、検討してみてはいかがでしょうか。
この番組はSpotify for Podcastersのほか、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
GW明けに新型コロナが5類に移行されました。
この3年の間にリモートワークが定着するなど大きな変化がありました。また、その中で私たちも多くの気づき、学びがあり、創意工夫もしてきました。
さてこれまでは、多くの企業が「原則リモートワーク」「週1〜2日出社」など出社制限をしてきましたが、インフルエンザと同じ5類になった今、出社はどうするのでしょう?リモートワークを継続する、原則出社とする、元に戻す・・と方針の選択を迫られています。
これをチャンスと見て、コロナ前の働き方とこの3年間の学びを一度解体して、未来に向けて再構築してはいかがでしょう?
コロナ前が正しかったとも限りませんし、with コロナで学んだことも数多くあるからです。
そう考えると新型コロナの5類移行は、組織のアンラーニングと進化のチャンスなのではないでしょうか。
この番組はSpotify for Podcastersの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
新卒新入社員の初期研修が一段落する頃です。
ある会社の新人研修から話はスタート。
自分の頭で考え自分で決めるよう、よく工夫された新人研修です。
さらに他のある会社では、事実の羅列で終わってしまいがちな新人の日報に、学んだことをオリジナルのネーミングをして「法則」として記載させるようにしました。これによって経験の概念化が進み、学びが定着して応用が効くようになります。
新人研修に限ったことではなく、上司や先輩ももう一度、自分の経験を「法則」にしてみてはいかがですか?
この番組はanchorの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
組織に学ぶ風土を作ることはとても大切です。
そこで人事(教育研修担当)が、多くの社員に受講する意欲が湧き、受講者が増えることを狙って多種多様な科目を用意することを見受けます。
これ自体はとても良いことです。
個々の従業員が学ぶのは良いことなのですが、実はその集合である全社のパフォーマンスが上がっていない、場合によっては下がってしまうという、経済でいうところの「合成の誤謬」が起きる可能性があります。
これを防ぐには、経営や人事が行う教育インフラの設計や現場責任者による実行において、自主性は重んじながらも、タレントマネジメントと組み合わせて細やかに指導することではないでしょうか。そうすることによって社員も学んだことを活かせますし、活かせたことで学んだ価値を実感し、それが学ぶサイクルの動力になるでしょう。
みなさんの会社の教育システムは「合成の誤謬」に陥っていませんか?
この番組は、Spotifyの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
12年前の東日本大震災の際に、後に「釜石の奇跡」と呼ばれることになる、お手本とも言われる避難行動がありました。
しかしそれは「奇跡」ではなく、8年がかりの地道な教育訓練が生んだ、小中学生・消防団・地域住民らが一体となった避難行動だったのです。
企業も予期せぬ天災・人災に突然襲われます。しかしそのリスクを未然に防ぐ教育訓練、それが起きた時の対応などの準備は後回しにされがち。ことが起きてから慌てて対応し、再発防止策を打ち出すという姿がよく見られます。そして同じ過ちを繰り返すことも稀なことではありません。
コロナ禍という天災が引き起こした危機は去りつつあるようです。だからこそ、これを教訓に次の天災・人災への準備をしておきたいものです。
考えてみれば先人は「喉元過ぎれば熱さ忘れる」「備えあれば憂いなし」「転ばぬ先の杖」と諺に残してくれています。
それは震災を伝える碑文と同じ。読む人がそれを自分ごととして、風化させず、怠りなく、不断に準備することが大切です。
みなさんの会社は「奇跡」と呼ばれる「必然」のための準備をしていますか?
この番組はSpotify for Podcastersの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
新任者は移動先に張り切って赴任します。
張り切ることは良いことなのですが、自分の存在感を出そうとすると無意識のうちに前任者を否定してしまうことがあります。
前任者を否定することは、その部下としてともにがんばってきたメンバーの誇りも傷つけます。
存在感を出し、改革を進めようとしたのに協力が得られないというしっぺ返しを食うことになるのです。
しかもそれは往々にして顧客視点からもズレているため、顧客の支持も得られません。
今回は、今野の定宿のマネージャーが代わったことから話が始まり、高野の生々しい体験談に至りました。
異動の季節です。異動された方にも、異動を受け入れた方にもご参考になるのではないかと思います。
この番組はSpotify for Podcastersをはじめ、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
組織や仕事に感情を挟んではいけないと思っていませんか?
それは決して間違いではないのですが、感情なく仕事をすることは不可能です。
感情的になったり、感情を爆発させてしまうことは時には大切ですが、多くの場面ではチームにとってマイナスになります。
しかし、どんなに押し殺していても、どんなに合理的であっても、感情にまで視野を広げるとリアリティを持った真実が見えます。
メタ認知、自分を客観視することは重要ですが、その時に自分の感情と客観的に向き合ってみること。
少し時間が経って感情が落ち着いてきたら、その時の自分の感情とも向き合ってみる。
なぜそのような感情が起きたのかと考えてみる。
そこにはきっと、「自分が蔑ろにはできない何か」が隠れています。
この番組はSpotifyの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
『組織ラジオ』のバックナンバーは「いまのたかの」を検索!
米国の社会学者マーク・S・グラノヴェターは、家族や親友、同じ職場の仲間などのような強いネットワーク(強い紐帯、Strong Ties)に対して、ちょっとした知り合いや知人の知人といった弱いネットワーク(弱い紐帯、Weak Ties )があること、Strong Tiesは孤立しやすいためStrong Ties同士のブリッジとしてWeak Ties が重要な役割を果たすことを提唱しました。
企業組織が効率性を求めればそのネットワークは必然的にStrong Tiesになっていきます。Strong Tiesは効率的な半面、そのネットワーク内は同質性が高く、内部の知識や情報はメンバーにとって知っている情報ばかりになり、いわゆる蛸壺化を引き起こします。それに対してWeak Tiesは開放的で様々な経験値、異なる考え方、未知の情報が往来するため、新たな知識や気づきが生まれやすいと考えられます。こう考えると企業組織に「異状と変化への対応力」いわばイノベーション力を育むにはWeak Tiesが重要であると考えられます。
企業組織にWeak Tiesを付加するにはどんな仕掛けをすればいいのでしょう。実は以前からやってきた施策のいくつかはWeak Tiesを意図的に付加するために行っていたのだと言えます。そしてそれに気づくことができれば、今後新たな施策も考えることが容易になると思われます。
『組織ラジオ』はSpotifyの他、Podcast、Google Podcastでもお聴きいただけます。
バックナンバーは「いまのたかの」を検索!