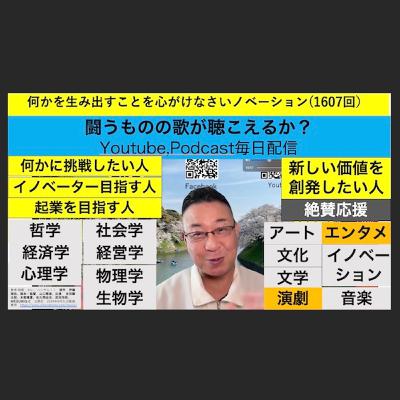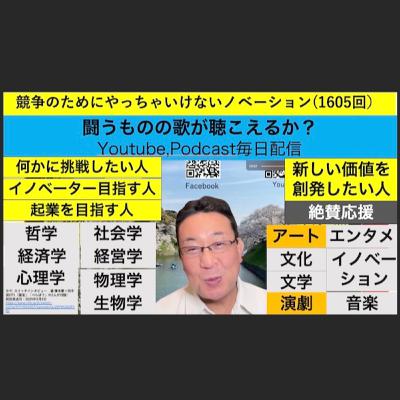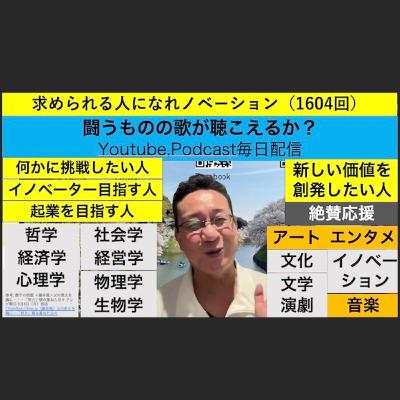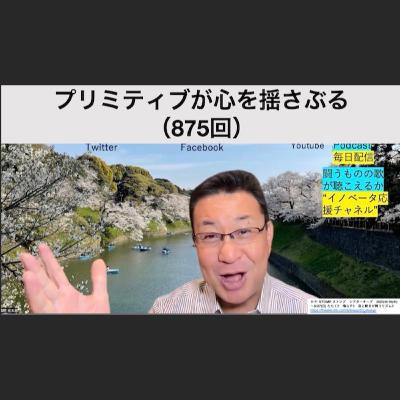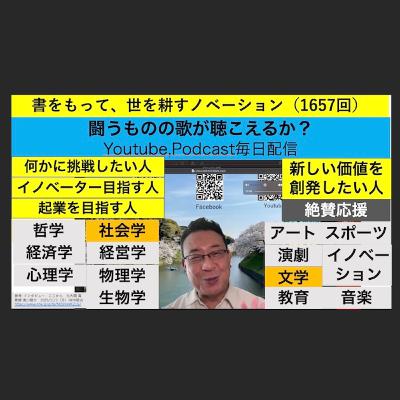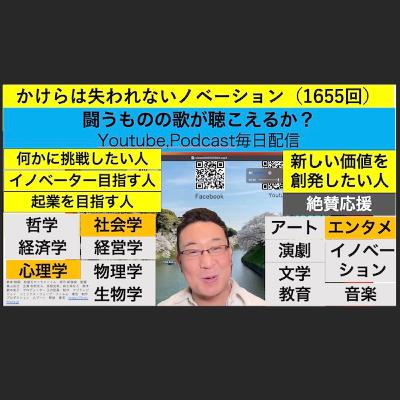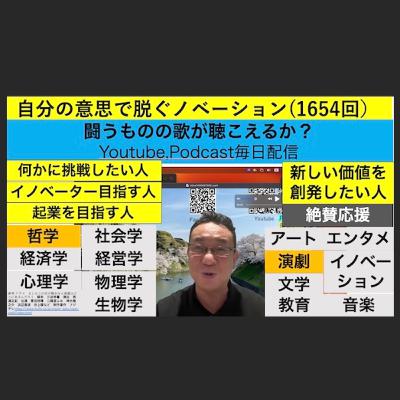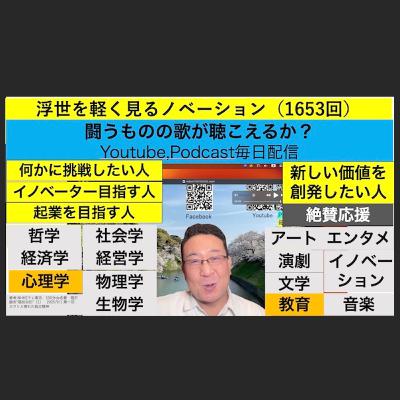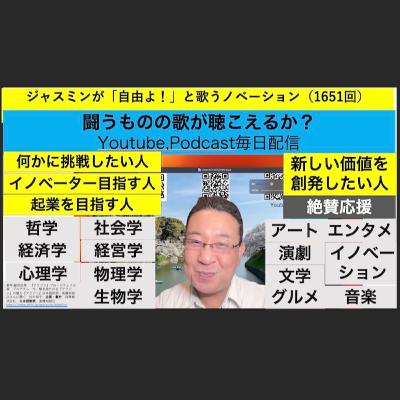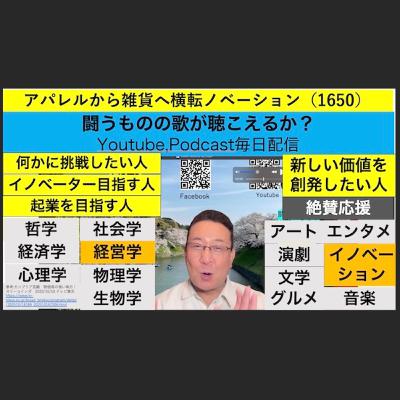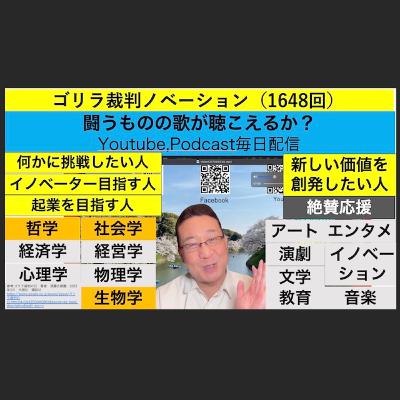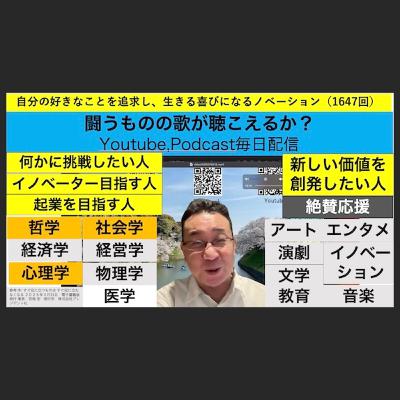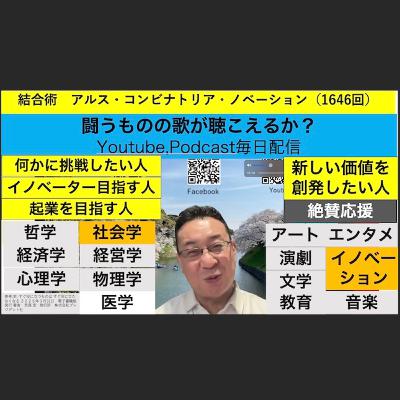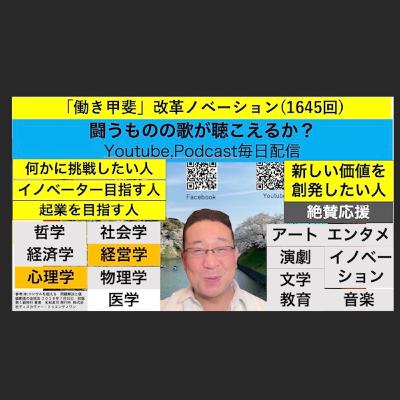論よりアイディア・ノベーション(1652回)
Description
日本の教育学者であり明治大学文学部教授の齋藤孝さんの言葉に深く共感と共に、新たな気づきを頂きました
曰く
"私は「論よりアイデア」という標語を掲げ、世の中に浸透させる活動を続けています"
"なぜ、そんな草の根運動をしているかというと、「論より証拠(=議論するよりも証拠を示すことが重要)」という言葉があまり好きになれないからです。
エビデンス(証拠)が大事というのは確かにその通りですが、それより大事なのは、何かアイデアを生み出すことです。"
"私は楽しい、面白いと思える時間が長い人生こそが、善い人生であると考えます。 楽しい、面白いと思える時間を作る上でのカギとなるのが「気づきの数」です。"
ここから私は思いました^ ^
1、自律性と有能感
2、快楽物質
3、リップルモデルで生き甲斐へ
1、自律性と有能感
何故気づきが起きると気持ちいいのか?ということについて、とても考えさせられると共に、めちゃくちゃ共感させて頂きました
自己決定論のデシ&ライアンさんのお話では、1、自律性、2、有能感、3、関係性が、人の幸せを形作るとの話がありましたが
気づきとは、1、自律性、2、有能感を刺激してくれるものなので、内発的動機を刺激してくれて、かつとても幸せな気持ちになれるのかなあと思いました
2、快楽物質
ジョン・クーニオスさんと マーク・ベアマンによると、2004年の研究で、「突然のひらめき(Insight)」が生じた瞬間、右側上側頭回が活性化し、同時に報酬系(側坐核)も反応することをfMRIで確認したとのことです
つまり、人は、気づきを得る際にも、快楽物質が出ているからこそ、気づきを得たいと思う活動をする、そんなことも言えるのかもこれないと思いました
それは、太刀川さんの進化思考的にいうと、変異と適応の、変異側の作用として、人間は進化するために、自らに変異をしようとする仕組みを入れ込んだのかもしれない、そんなことも思わせて頂きました
3、リップルモデルで生き甲斐へ
気づきは、自分自身の内部で生じるものですが、さそれを元に、仲間と共に、さらにたくさんの人たちにその気づきを得てもらう、というイノベーターリップルモデルを展開していくと
よりたくさんの人たちに、自分の気づきをわかってもらえて、もし喜んでもらえることが起きたら、それは小さなイノベーションの始まりだなあと思いました
リップモデルのループが回り始めたら、それは快楽から、生き甲斐に、育っていくのではないか、そんなことを思いました
と言えことで、一言で言えば
論よりアイディア・ノベーション
そんなことをお話ししてます^ ^
参考:本: 「気づき」の快感 令和6年11月発行 著者 齋藤孝 発行所 株式会社幻冬舎