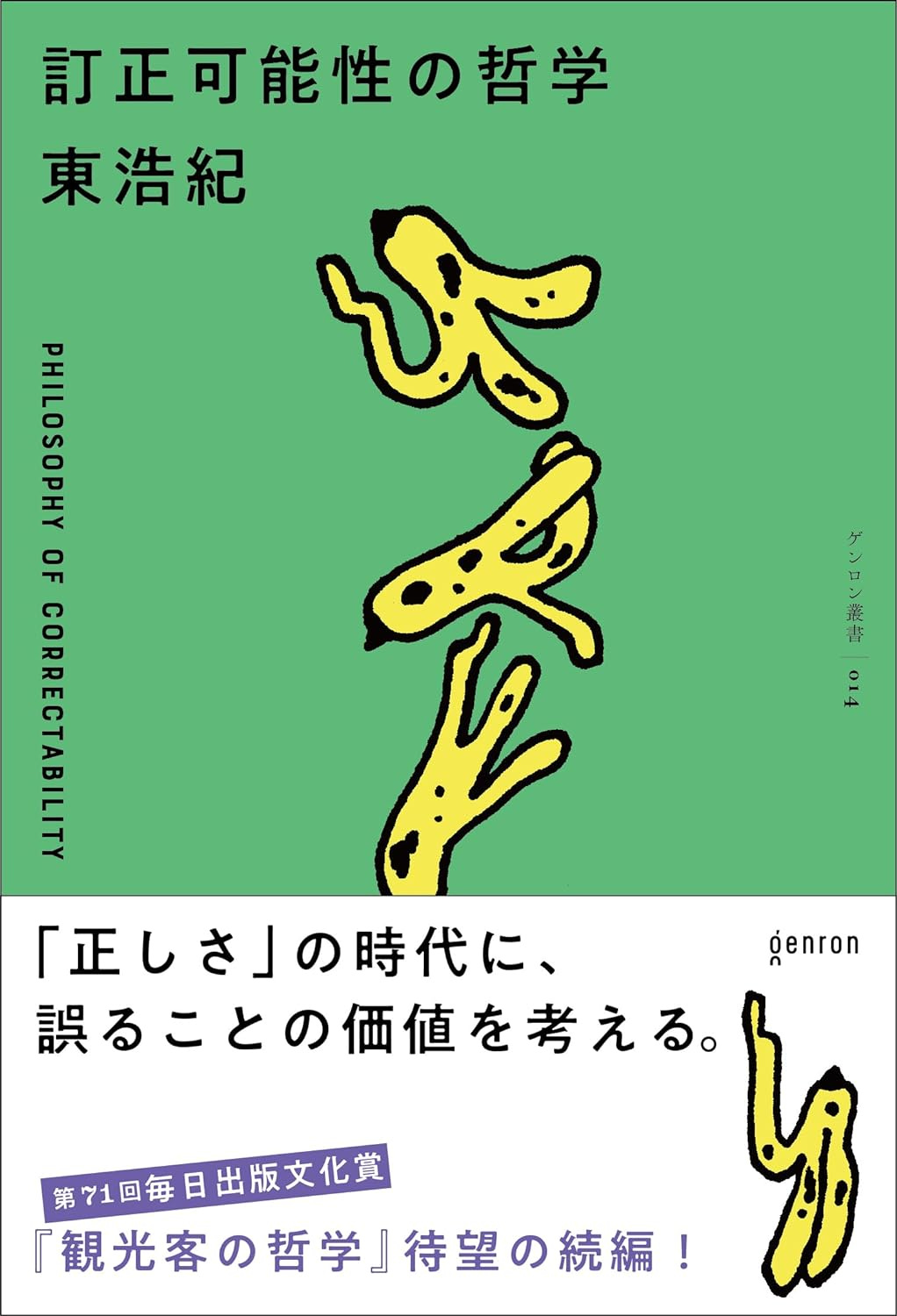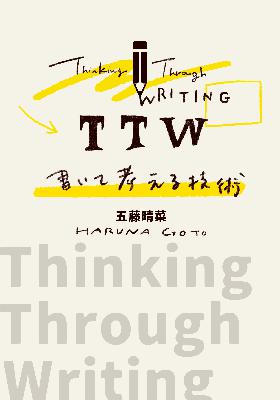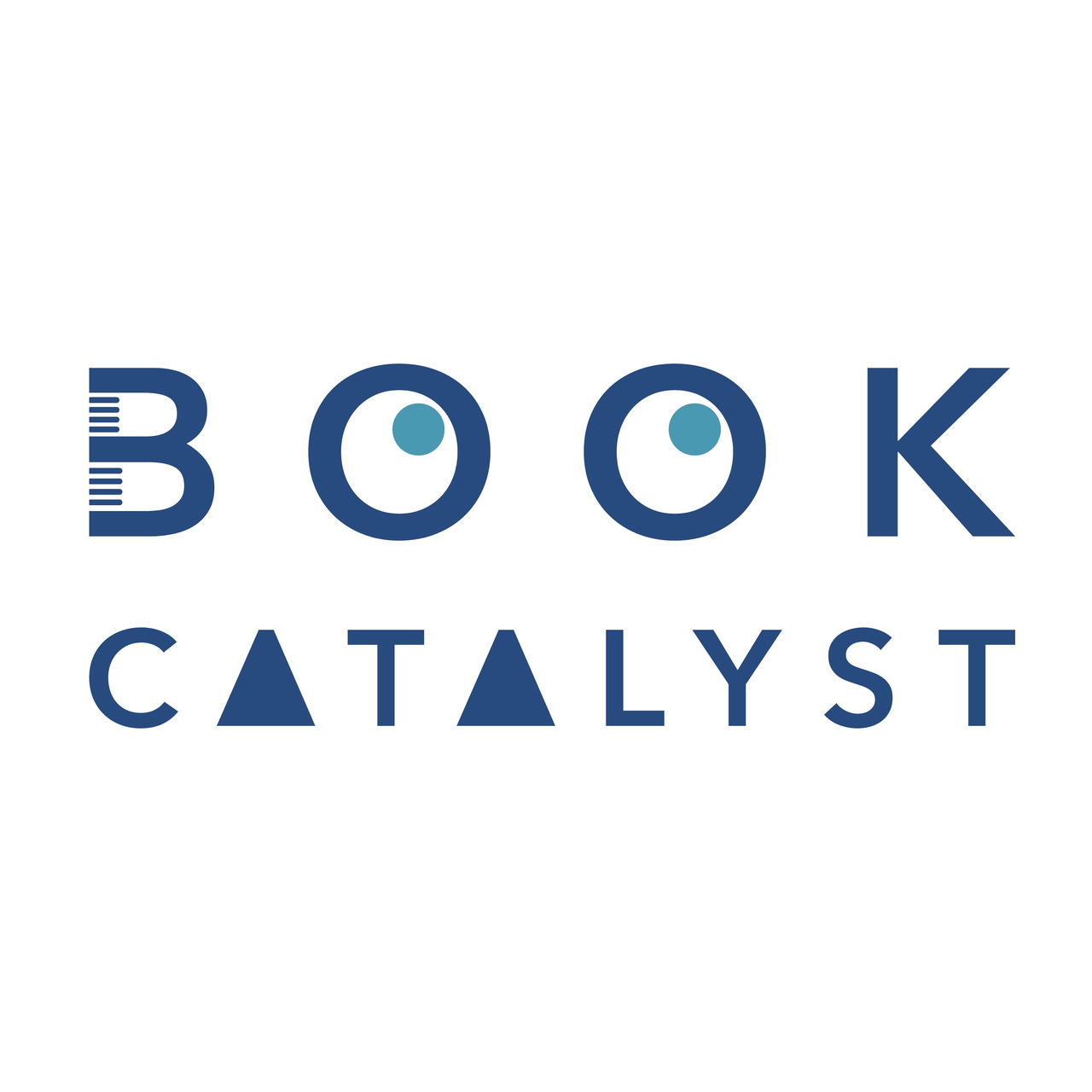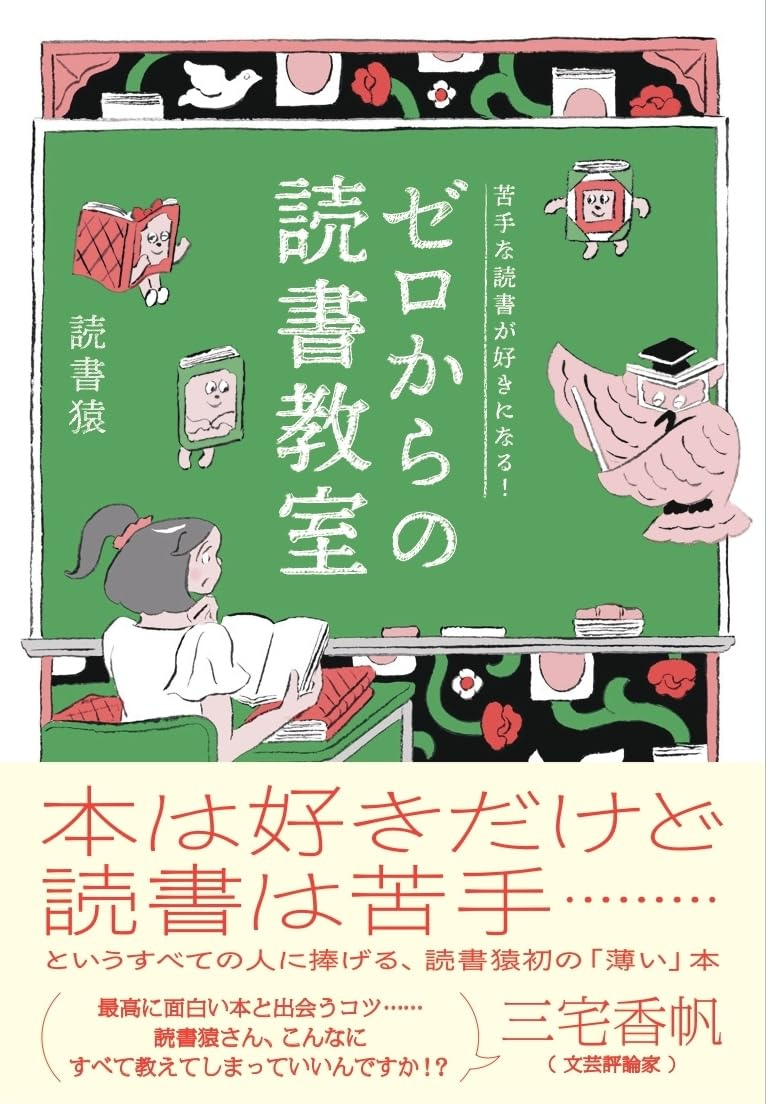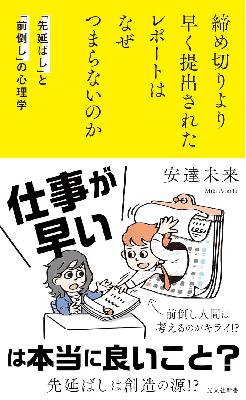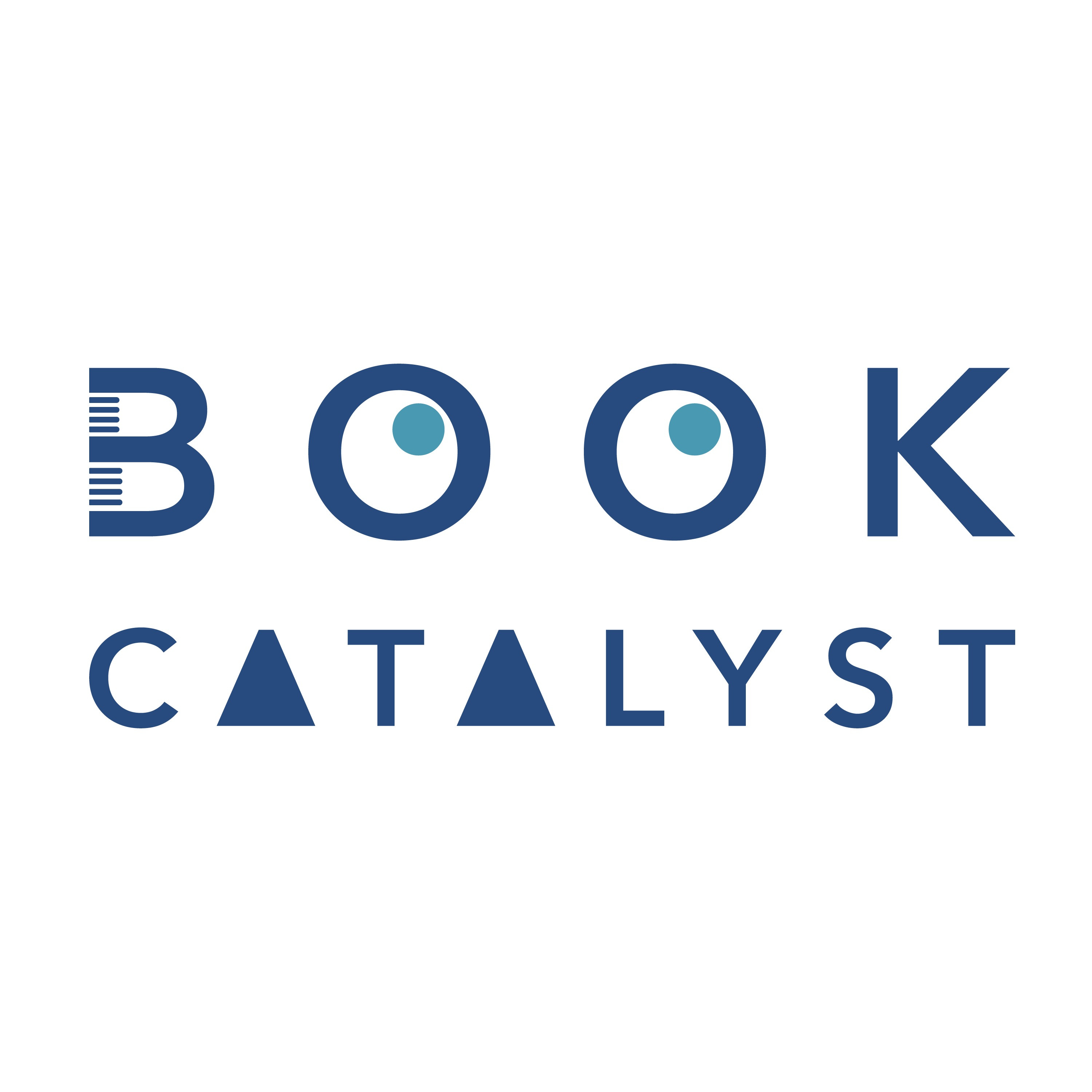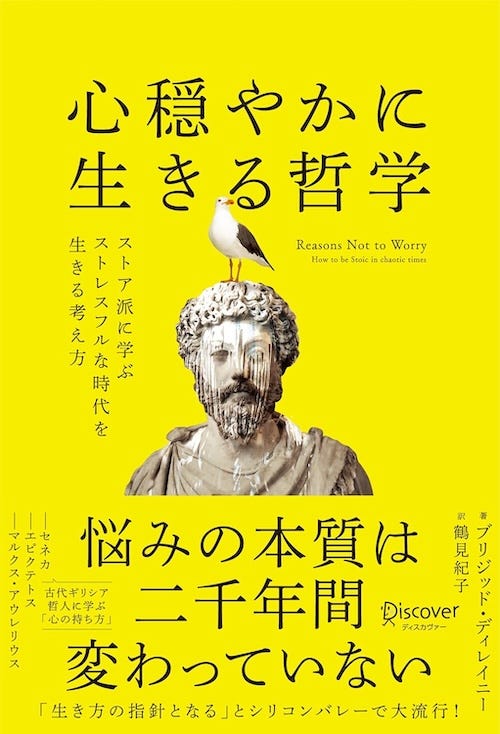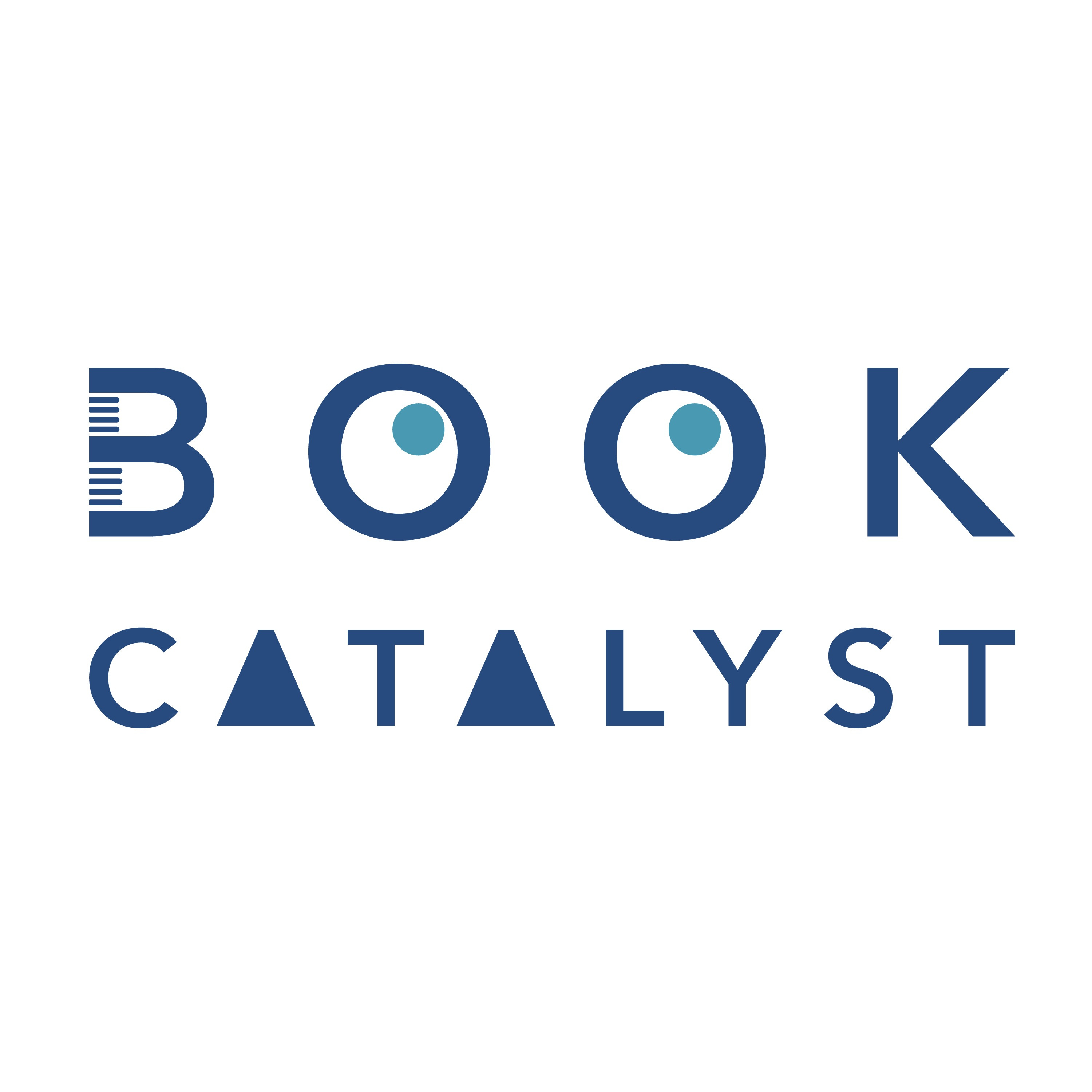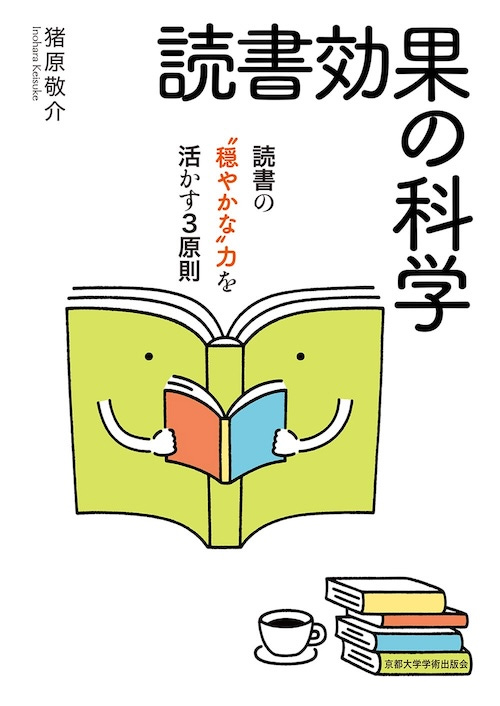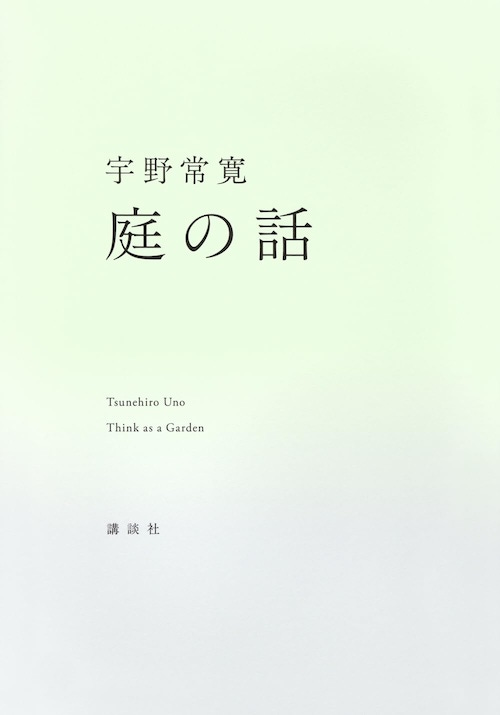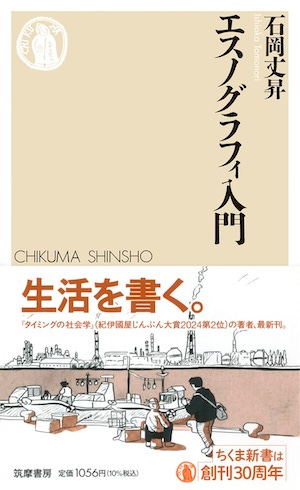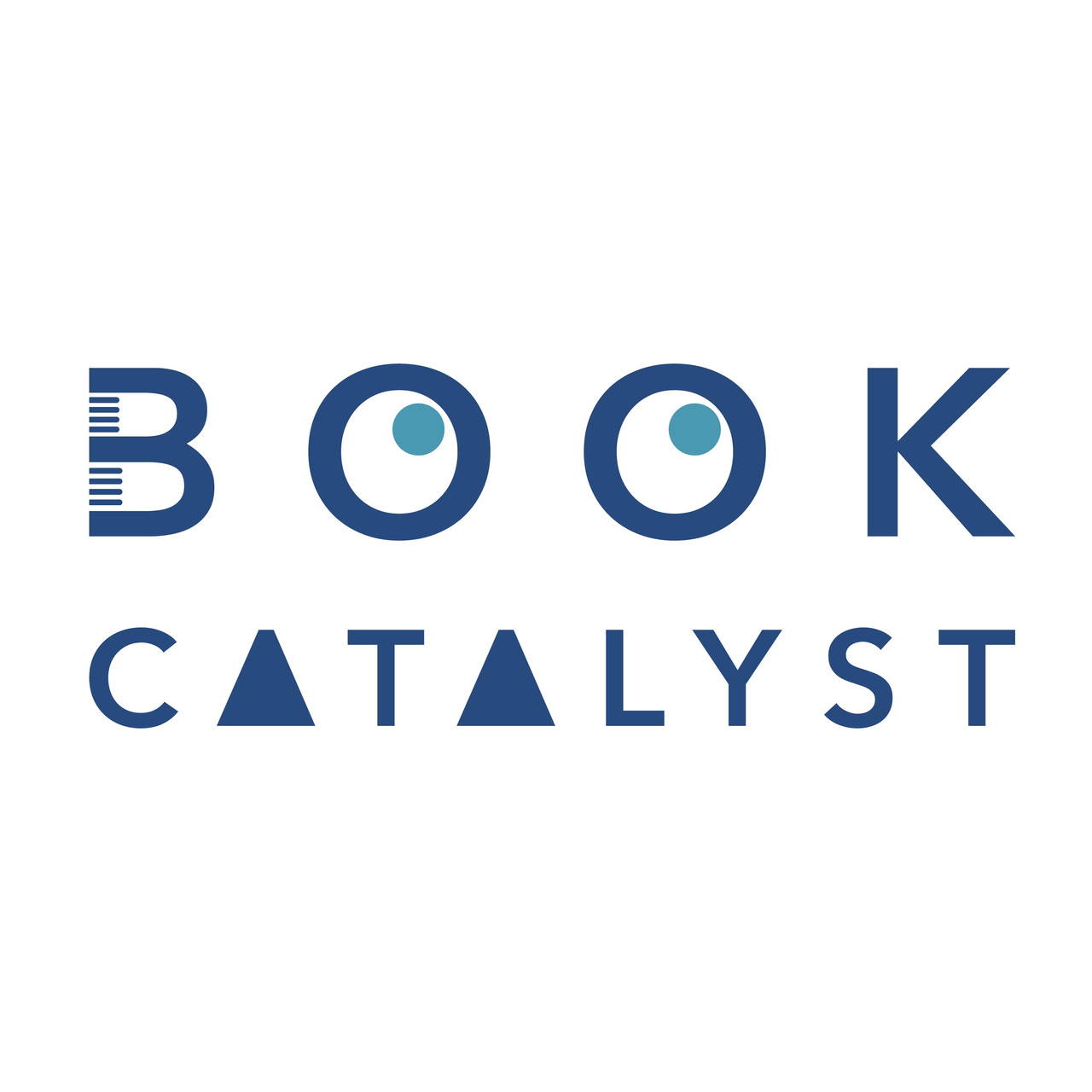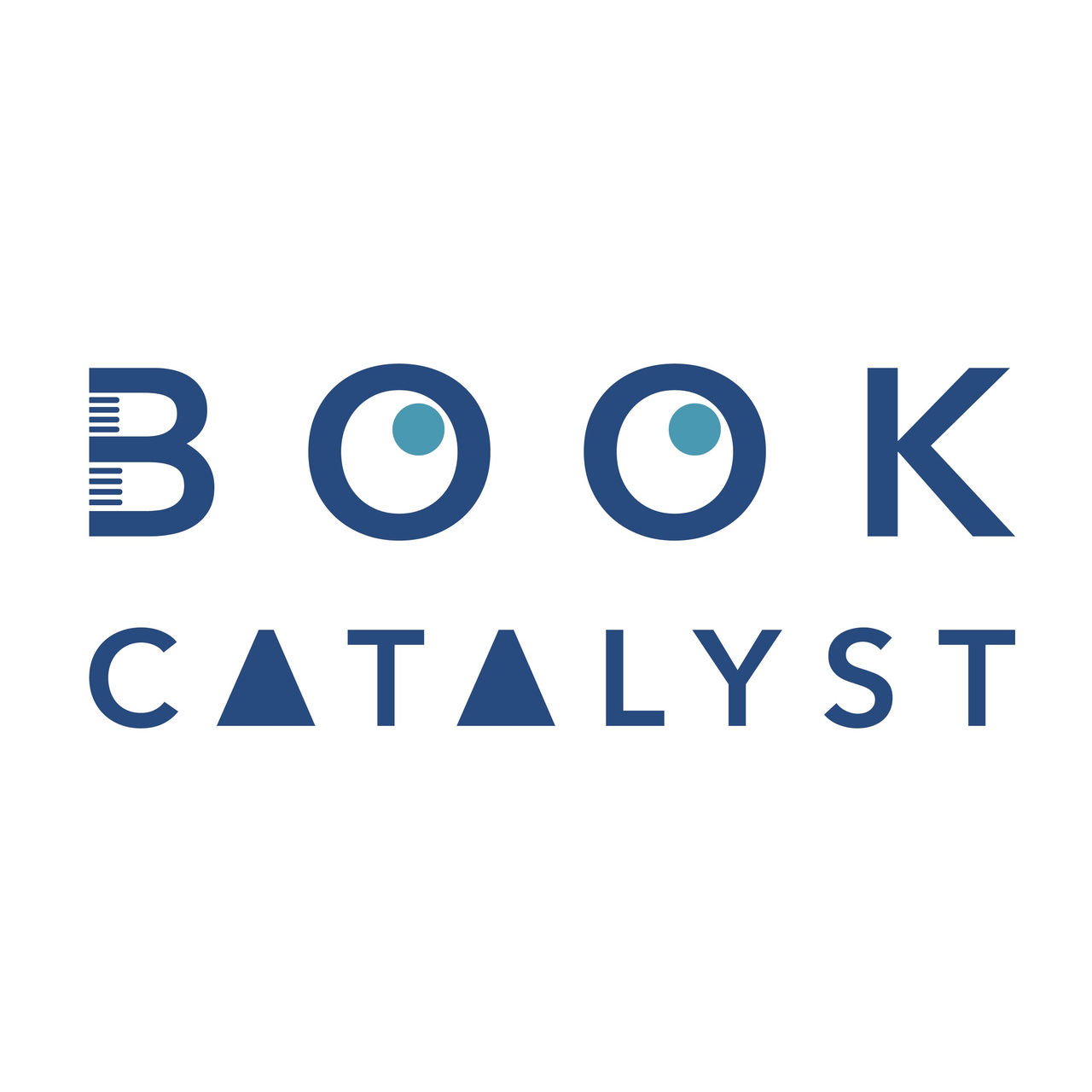BC106『訂正可能性の哲学』と自己啓発
Description
今回は『訂正可能性の哲学』を取り上げました。
主に紹介したのは第1部の内容で、最後に少し倉下の考え(自己啓発の課題)も提示してあります。
本編は 07:30 あたりからスタート。倉下の読書メモは以下のページで確認できます。
家族と思想
本書で一番ビビっときたのが、エマニュエル・トッドの家族と社会体制の関係を補助線にしながら、私たちは「家族」的なものの外側には出られないのではないか、と提示された部分です。
家族の外に出たと思ったら、そこにも家族があった。
フラクタルな構造としても面白いですし、私たちの思考・思想が生まれ育った環境に強く制約されているという点でも示唆に富む提示です。
その上で、です。
私たちたちが生まれ育つ環境そのものが動いている、という点も見逃せません。生活の実態として「家族」的なものが今後変化していくならば、私たちの共同体の思想もその土台から動いていくことが考えられます。おそらくそれは、希望を形作る可能性でしょう(もちろん、絶望に転じる可能性も同時にあるわけですが)。
たとえば、金田一蓮十郎の『ラララ』では、恋愛ではない形で結婚した夫婦が養子を迎え入れるという「家族」の形を提示していますが、そのようなさまざまな形態の家族が増えていけば、私たちの共同体思想も変わっていくのかもしれません。
訂正可能性
本書の中心となるのが「訂正可能性」であり、それは「閉じていながら、開いている」という二重の性質を持ちます。また、「訂正可能性」を持つためには、つまり「訂正される」という可能性を担保するためには、それが持続・継続していく必要があります。
開きと閉じの二重性、そして継続性・持続性。
そうした性質が大切だよ、ということを真理の追究や功利主義などとは違った立場から本書は提示してくれています。
ごく卑近な実感としてもその提示には頷けるものがあります。たとえばこの「ブックカタリスト」は、あるブックカタリストっぽさを維持して続けていくことが大切でしょう。ある日聴いたら「楽にめっちゃ儲けられる方法」などが語られていたら残念感が半端ありません。
一方で、そのブックカタリストっぽさは常に更新され続けていくことも必要です。同じでありながら、変化もすること。それがシンボル(ないしブランド)にとって重要な要素です。
それと共に、やっぱり配信を続けていくことも大切です。というよりも、同じでありながら、変化もすることは続けていくからこそ可能なのです。
単に続ければいいというものではないし、単に変化すればいいものでもないし、単に変わらなければいいものでもない。
これらの複合において、はじめて可能になるものがある。
そういう意味で、本書の提案は哲学的面白さ以上に、実践的活動において大切な話だと個人的には感じました。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe