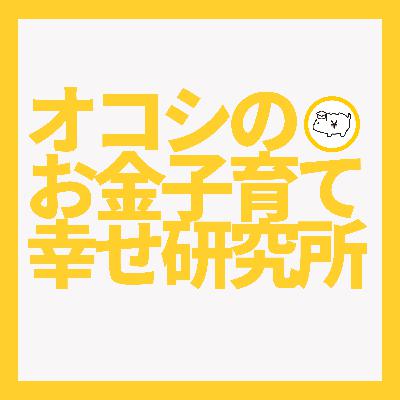【学力の経済学】科学的根拠あり。伸びる子どもの育て方とは?教育経済学者 中室牧子教授が示す非認知能力とは?勉強をさせる方法。テストの点数が上がる方法。やる気を引き出す方法
Description
#学力の経済学 #中室牧子
目次
01:50 1.ご褒美を与えてもよいのか
02:53 2.どんな時にご褒美が与えるのか
03:56 3.ご褒美が、勉強する楽しさを失わせるか
04:39 4.どんなご褒美がよいのか
05:19 5.褒めて育てるべきか
06:54 6.テレビやゲームの影響
08:54 7.子どもに勉強をさせる方法
09:40 8.友情の重要性
11:02 9.教育投資の時期
13:35 10.重要な非認知能力
15:43 11.教員の力
体験格差解消へ!体験活動の必要性。子どもの健やかな成長ののために!文部科学省の長年の調査から明らかになった、体験活動の効果とは。
https://youtu.be/2AJVQjjVum8
今回は「学力の経済学」をテーマに、教育における科学的なアプローチについて考えていきます。多くの教育論は、成功体験や特定の事例に基づいたものが多いですが、再現性に疑問が残ります。そこで「教育経済学」が役立ちます。この分野は、データ分析を通じて、教育の効果を科学的に検証し、多くの人に適用可能な教育方法を探求する学問です。
例えば、特定の家庭で成功した教育方法が、他の家庭でも同じように効果を発揮するかは分かりません。一方、何万人もの学生を対象にした研究から、規則性を持って学力向上に寄与する方法が明らかになると、より多くの人に参考になるのです。このような科学的なアプローチは「エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング(EBPM)」と呼ばれ、教育政策の基盤となっています。
また、子育てに関するよくある疑問についても、教育経済学を用いて検証します。たとえば「勉強のためにご褒美を与えるべきか?」という疑問に対して、データは短期的なモチベーションにはご褒美が有効であることを示しています。しかし、そのご褒美を与えるタイミングや種類も重要です。テストの成績よりも「努力したこと」に対してご褒美を与える方が効果的であり、また、トロフィーのような物理的なご褒美の方が子供のやる気を引き出す効果が高いことも分かっています。
さらに、子供を褒めることについても、学力が高まることで自尊心が育まれることが分かっており、ただ褒めるのではなく、具体的な行動や成果を褒めることが重要です。また、テレビやゲームの影響についても、1日1時間程度であればほとんど悪影響はないという結果が出ていますが、2時間を超えると学力や発達にマイナスの影響が現れます。
教育経済学はまた、子供に勉強させる方法や、どの時期に教育投資を行うのが最も効果的かについても示唆を与えます。就学前の教育が将来的な成功に大きな影響を与えることや、教員の質が子供の学力向上に大きく関与していることなどが、具体的な研究結果によって明らかにされています。
最後に、非認知能力、例えば「自制心」や「やり抜く力」、「勤勉性」などが、子供の将来の成功に大きな役割を果たすことが分かっています。これらは、学力だけでなく、人生のさまざまな場面で成功を収めるための重要なスキルです。
教育経済学を活用し、科学的根拠に基づいた子育てや教育を考えることが、現代社会において重要な課題となっているのです。