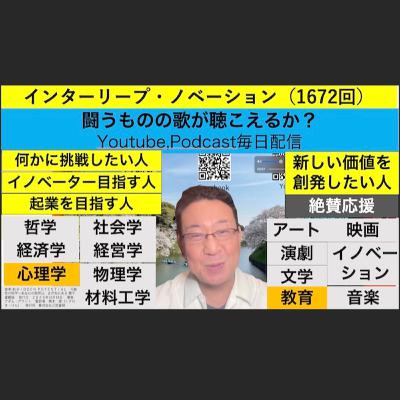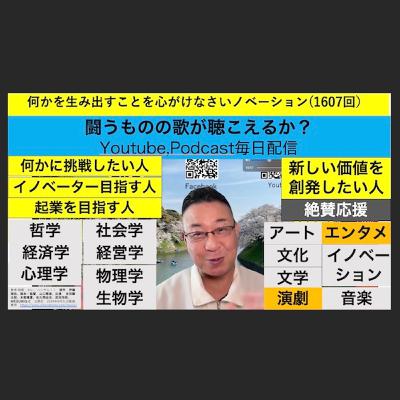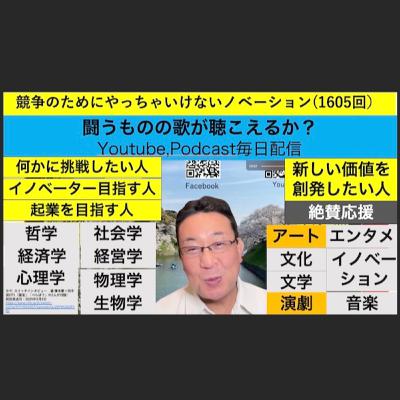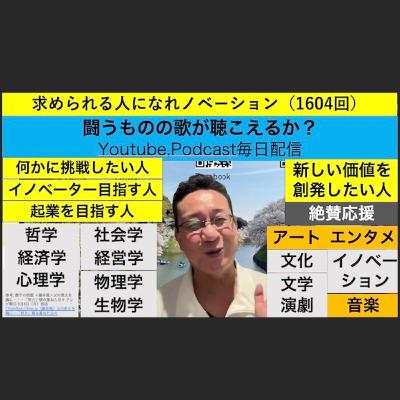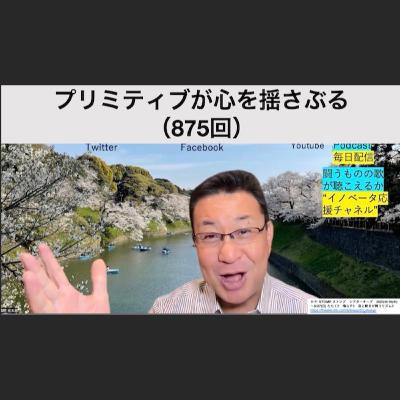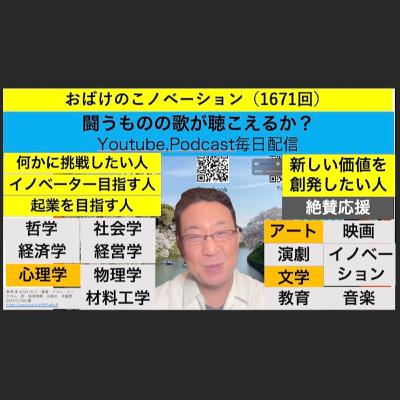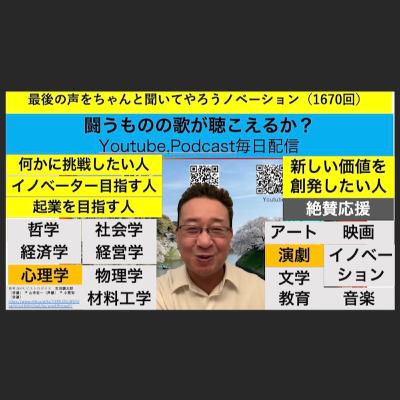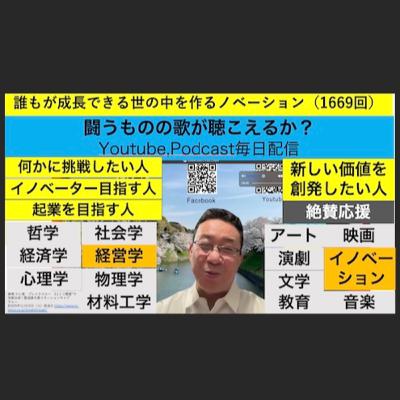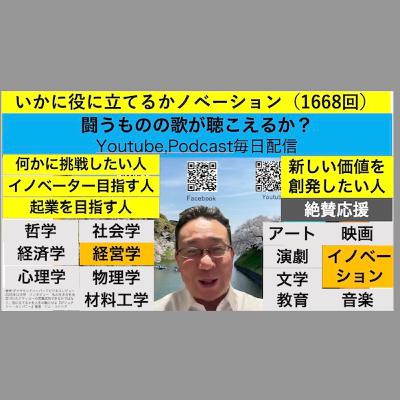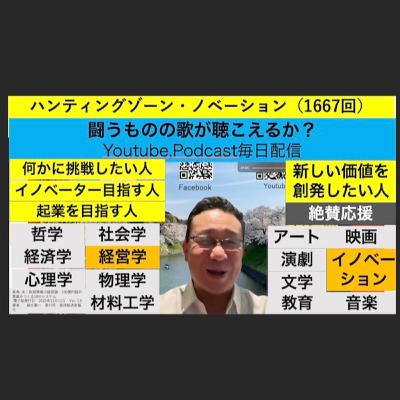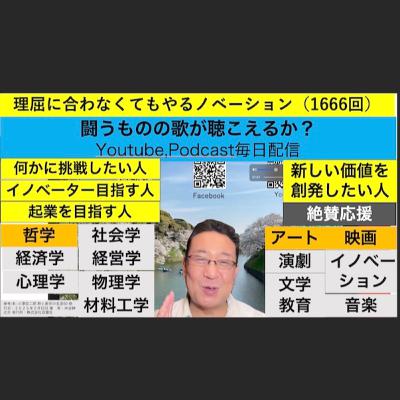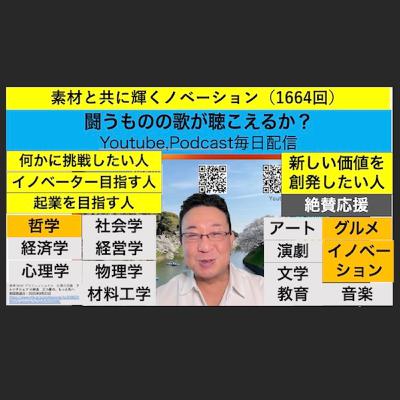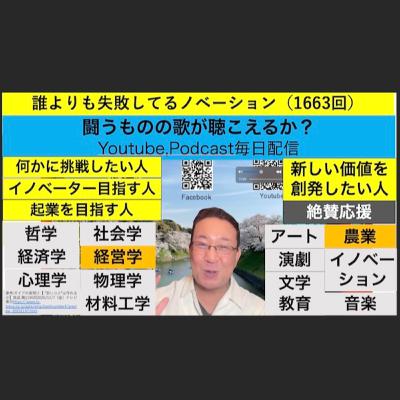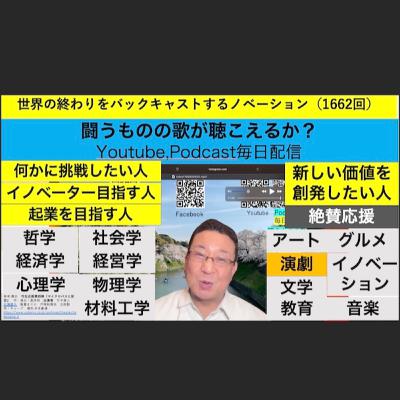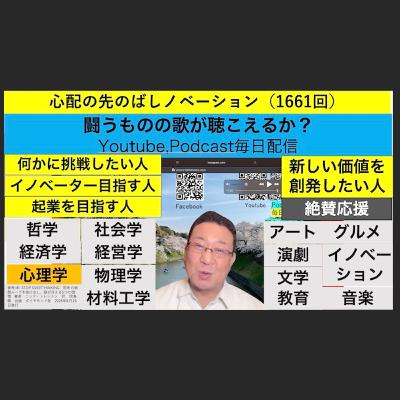インターリープ・ノベーション(1672回)
Description
ペンシルバニア大学ウォートン校教授のアダムグラントさんから、理想の練習方法を伺い、目から鱗が落ちる思いでした
曰く
"理想の練習法は、一つの技を進歩が見られるまで集中して徹底的に磨くことであると、私は思っていた。
だがブランドンは、同じ課題を延々と繰り返すのではなく、多様な要素を組み合わせる。カリーは二十分毎にシュートと瞬発力を鍛える演習から他の演習へと移行する。
変化を取り入れることは、モチベーションのみならず、学習の質も高める。数百もの実験が明らかにしているように、異なるスキルが交互に刺激される時、人は急速に進歩するのだ。
これは心理学で「インターリーブ(同時進行)法」と呼ばれ、絵画から数学に至るまで、あらゆる分野に応用可能である。"
ここから私は思いました
1、コンフォートゾーンの抜け方バイアス
2、インターリープは「混ぜると覚醒」
3、多刀流だからこそ、大谷翔平さんを創れる
1、コンフォートゾーンの抜け方バイアス
アンダースンさんの、超一流になるには努力か、才能か、という本が好きで良くお話ししてますが、そのポイントは1、最高の教師 2、コンフォートゾーンを抜ける 3、自分に自信を持つ これがコツと理解してまして
特に、2、コンフォートゾーンを抜けるには、できないことをやることだと、いうことで、筋トレであれば10回やれるところを更に20回、みたいなマッチョなやり方と思ってました
それがまさにバイアスに囚われていたということを知って、めちゃくちゃショックを受けました
つまり、そんなマッチョなやり方よりも、もっと優れたコンフォートゾーンを抜け出せる方法があるのである、ということに、ああ、本当に自分もバイアスに囚われて悔しいと思いました
2、インターリープは「混ぜると覚醒」
そのやり方が、インダーリープという、さまざまな課題を変えながらトレーニングをしていくという方法とのことでした
このインターリーブというのは、フロリダ大学のダグ・ロアーさんが唱えていて、複数のスキル・問題タイプを交互に練習する手法であり、“混ぜることで負荷が上がり、結果として長期学習が加速する”
さらには、単調な反復(ブロック練習)よりも 40〜70%学習効率が向上する ということを言われているとのことで、まさに何らかのトレーニングは、混ぜると危険、ならぬ、混ぜると覚醒、するという画期的な方法なのだと教えて頂きました
ミニマム学習法で、まずは5分から始めようというのもありますが、それはある意味正解で、そしてまた5分他のことをやってみる、というのを組み合わせてやるのが理にかなってる
ということを知って、私は早速、明日から、英語、作曲、リサーチ、読書、アカペラ練習、筋トレみたいに、もうやりたいことを、いくつも組み合わせてやることを、実践してみたいと思いました
3、多刀流だからこそ、大谷翔平さんを創れる
この話を考えてみると、実は、大谷翔平さんが、ここまで凄くなったのは、インターリーブ効果もあったのかもしれないなあと思いました
つまり、投手、打者、走者という、複数のものを同時に組み合わせて連射することで、インターリーブ効果として、各々のコンフォートゾーンを抜け出すことが更に深まっていったのではないか、そんな風にも考えさせられました
もしかしたら、これからの育成は
インターリーブとして、さまざまな学習を組み合わせる、それは、技術、芸術、哲学、科学、スポーツあらゆるものにまたがって活躍する人が現れる世の中になる
そんなことを想像してしまいました
一言で言うと
インターリーブ・ノベーション
そんな話をしています^ ^
参考:本:HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学―あなたの限界は、まだ先にある 電子書籍版 発行日 2025年10月14日 著者 アダム・グラント 監訳者 楠木 建(くすのき・けん) 発行所 株式会社三笠書房
動画で観たい方はこちら