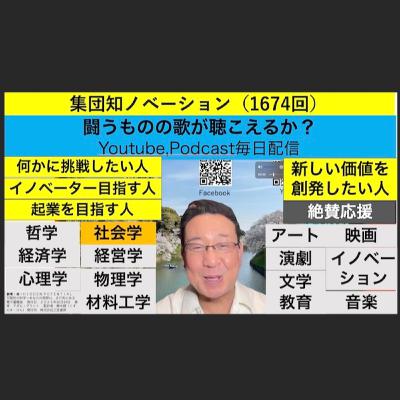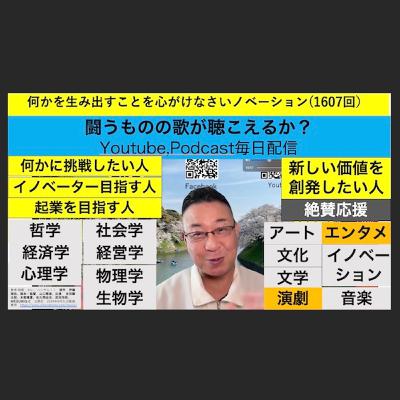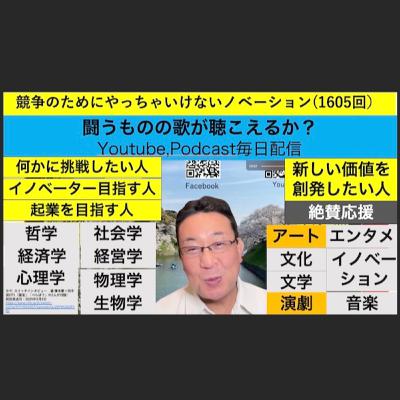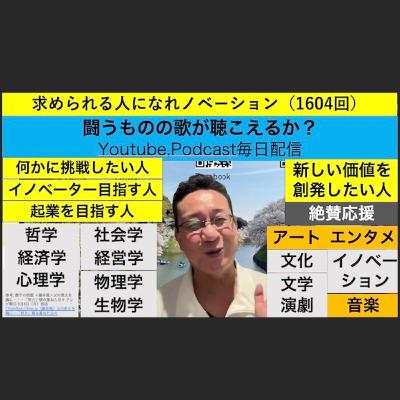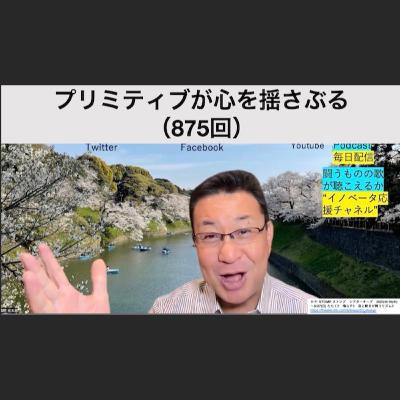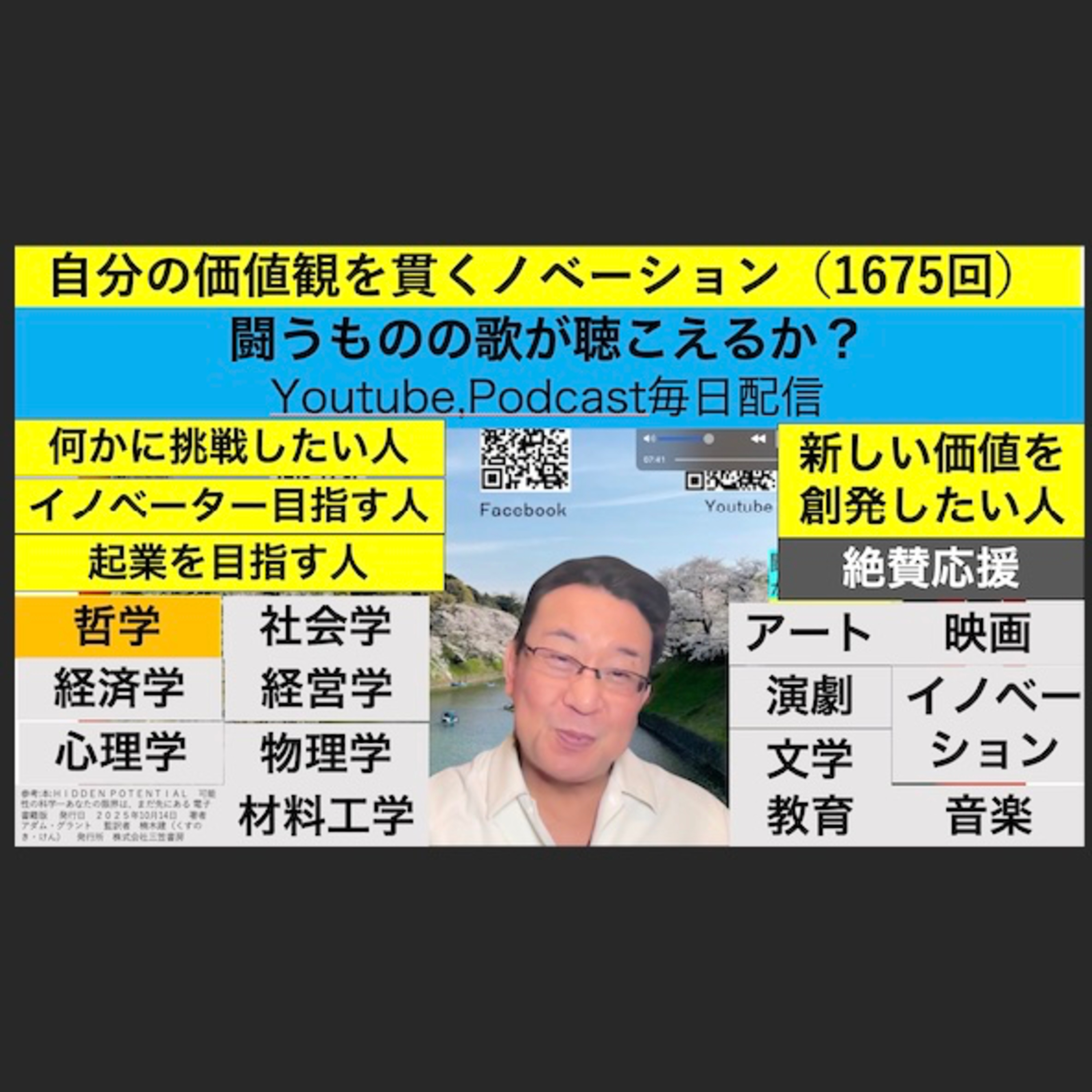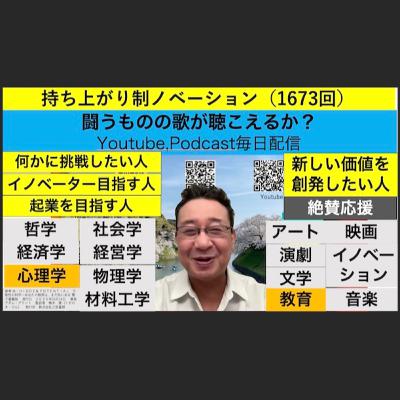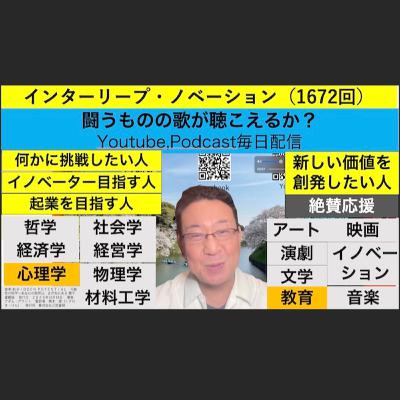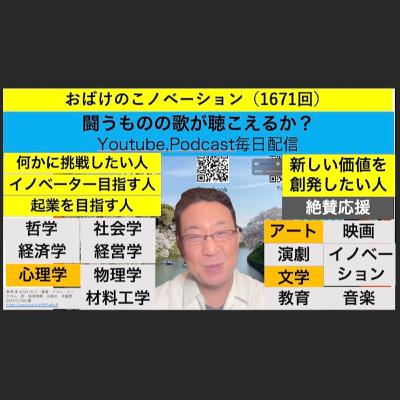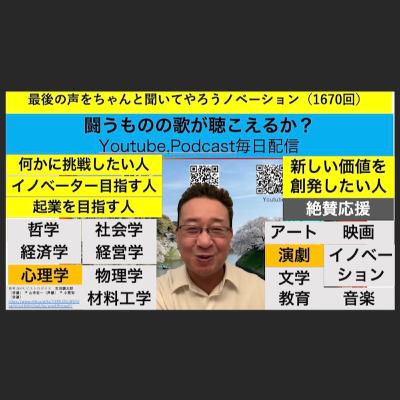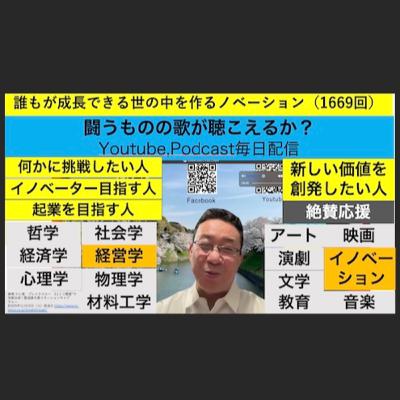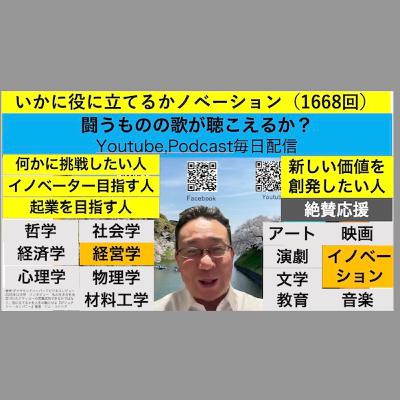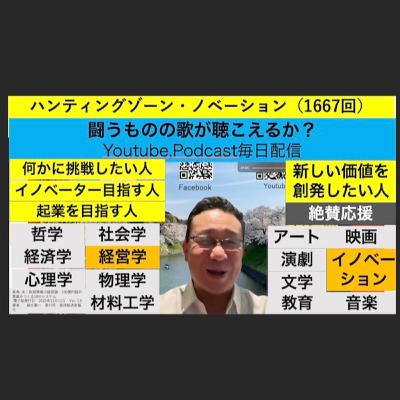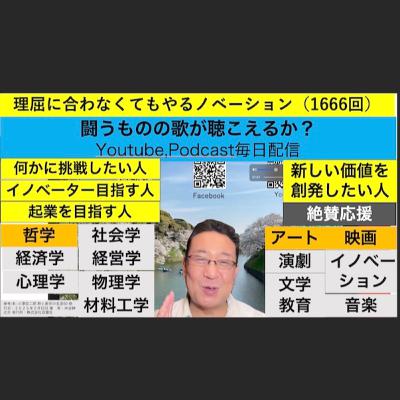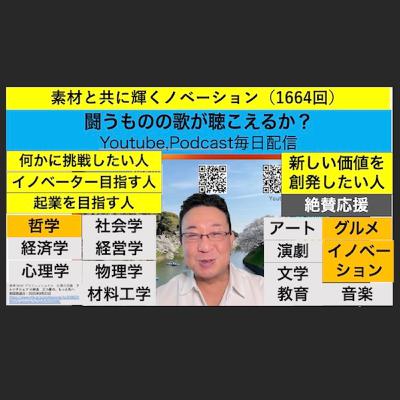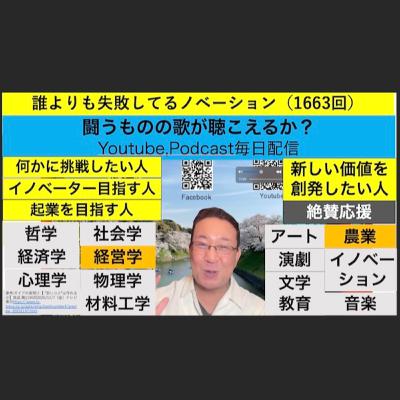集団知ノベーション(1674回)
Description
アダム・グラント さんから、仲間としてのチームプレイをする上での秘訣を教えて頂きました
曰く
"アニタと同僚研究者たちは、二十二の研究を対象としたメタ分析を行ない、集合知は個々の認知能力ではなく、むしろ向社会的なスキル(他者への配慮や協力する力)に大きく左右されることを発見した。
つまり、最高の成果を上げるチームとは、メンバー一人ひとりが優れているだけでなく、最も多くの「真のチームプレイヤー」を擁するチームなのである。
ここで言うチームプレイヤーとは、単に集団に属しているというだけでなく、互いの意見に真摯に耳を傾け、建設的な対話を重ね、仲間と協力して共通の目標達成に貢献できる、そんな協調性に優れた人材のことである。"
ここから私は思いました
1、 “孤高の天才”よりも“協奏する仲間”
2、協奏できる仲間を集めること
3、協奏できる場作りをすること
1、 “孤高の天才”よりも“協奏する仲間”
イノベーター3つのフレームとしての、リップルモデルでは、1、パッション、2、仲間、3、大義が揃うことの重要性を謳っていますが
2、仲間、に関するあり方を改めて教えて頂いた気がしました。
イノベーションにおいては、ピーターティールさんやジョブスさんのような、他の人が見えていない真実をみつける、目を持つ起業家のパッションとセンスがとても重要に思われている節もありますが
それも大切だけれども、実はそこからの2.仲間のあり方が、集合知、という巨大な価値をつくっていく上では、とても大切である。といえことは、私の心に刺さりました
2、協奏できる仲間を集めること
そういう意味では、起業家としてのパッションは必要かと思いますが、スーパーマンである必要はない、と言ってくれてる気がして、勇気を頂けました
それよりも、自分が思っているパッションや、大義に関して、共感してくれて、かつ、協奏できる仲間を集めることが、実は、とても大事な要素になるということを教えてくれてるような気がします
大谷翔平さんが、常日頃インタビューで話していることを聞いていると、常にチームのため、そしてチームが優勝することがとても大切、というようなことを言われているのを、思い出しました
サッカーでも、フォワードからオーバーラップをしながら、バックスで守りに入る人を、献身的なプレーをする、みたいなことも聞いたことがあります
BCGの秘伝のタレとして、貢献しようとする気持ちがあること、というのも以前お話ししましたが、様々な分野において、共創に重きを置く人材を集められるかが、実は鍵を握る、そういうことなのかもなあと思いました
3、協奏できる場作りをすること
プロジェクトアリストテレスの例が示す通り、心理的安全性を担保することはもちろんですが、私が思うのは、デシアンドライアンさんが言われる内発的動機づけに、いかに資する環境を作れるかということもある気がします
それは、まさに協奏をすることは、自分軸と他人軸の真ん中のベン図をより、高めていくことにつながると意識させることもあるのではないかと思います
それは、その人の情熱のポートフォリオの、利他パッションを満足することでもいいし、大好き、個性、成長パッションを、他の人や他の活動と協奏することによって、より高めていける
そんなベン図の真ん中を創発することができるんだ、という意識づけを、常日頃することができれば、それも、協奏を促す環境となる
そんなことも考えました
ということで一言で言えば
集団知ノベーション
そんな話をしています
参考:本:HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学―あなたの限界は、まだ先にある 電子書籍版 発行日 2025年10月14日 著 者 アダム・グラント 監訳者 楠木建(くすのき・けん) 発行所 株式会社三笠書房
動画で観たい方はこちら