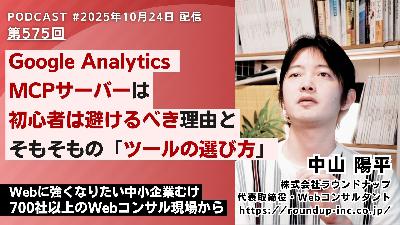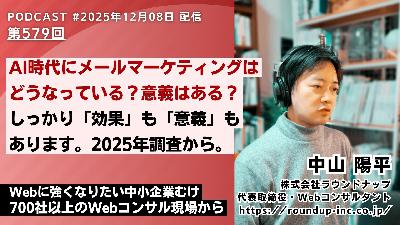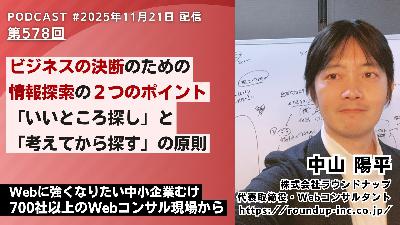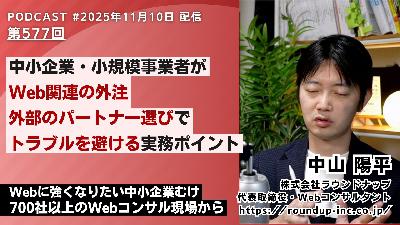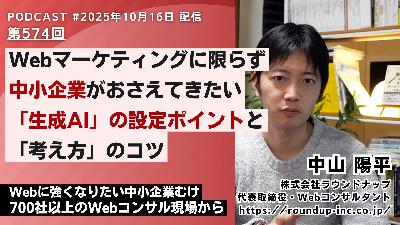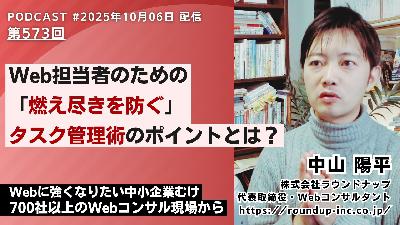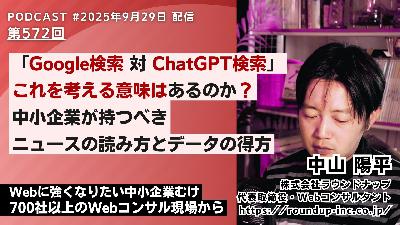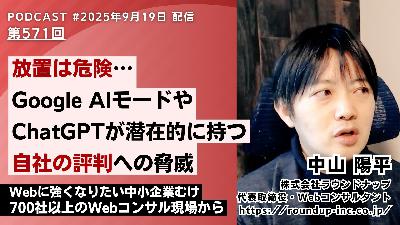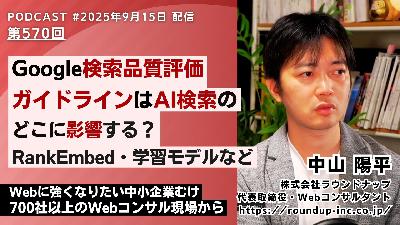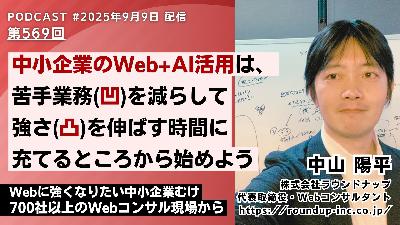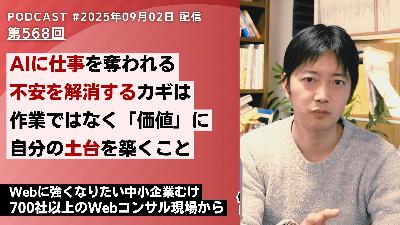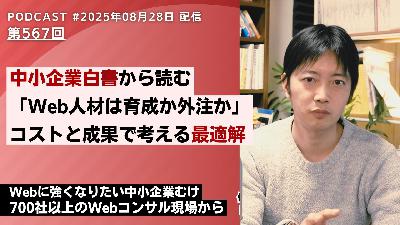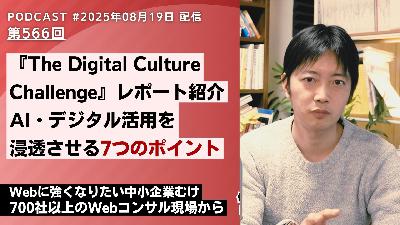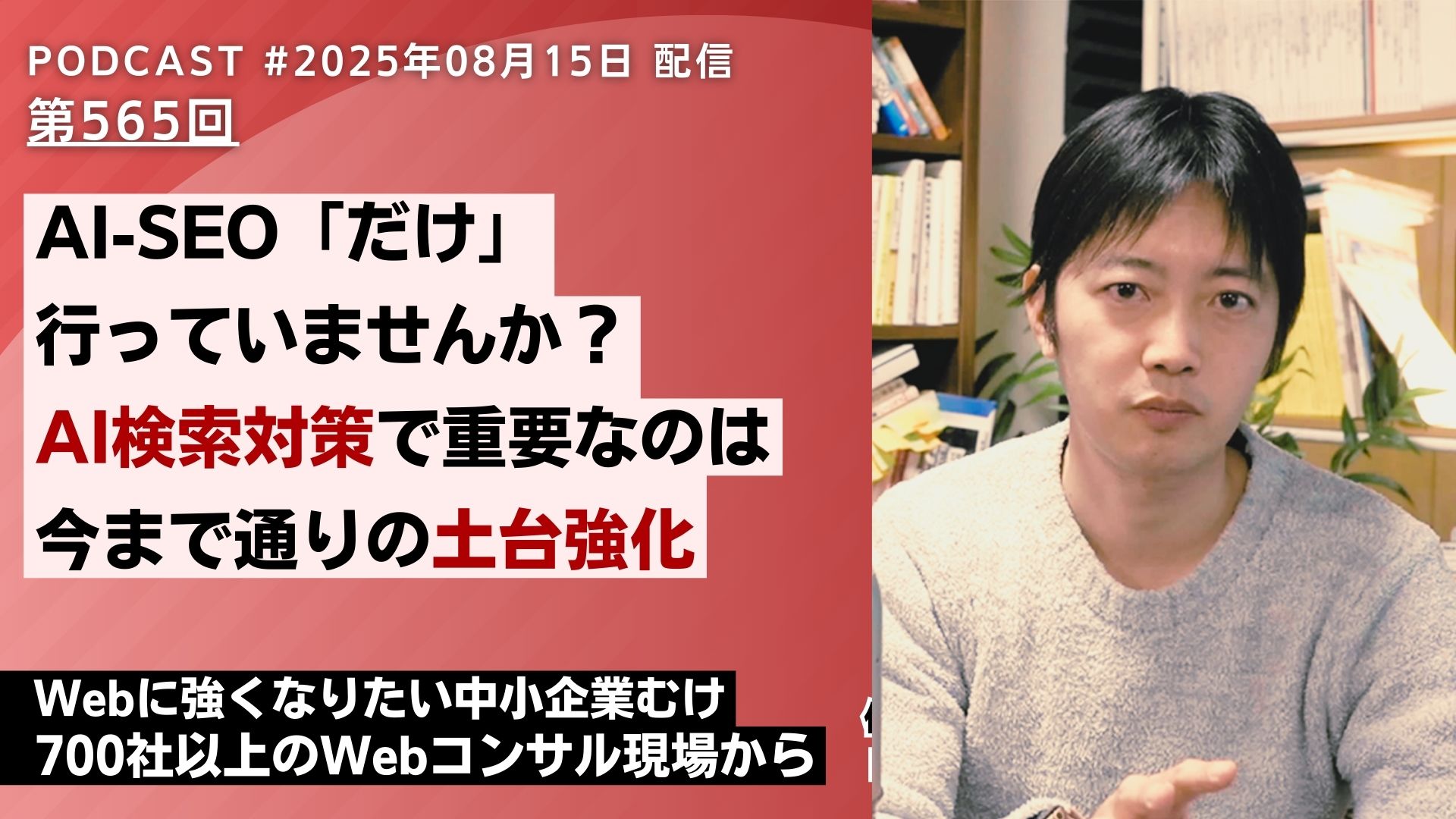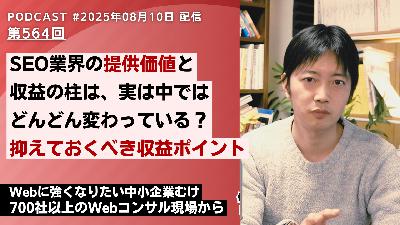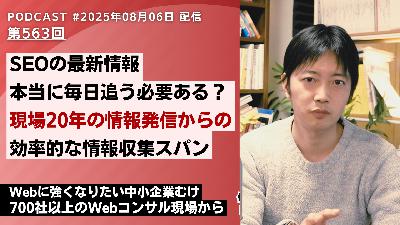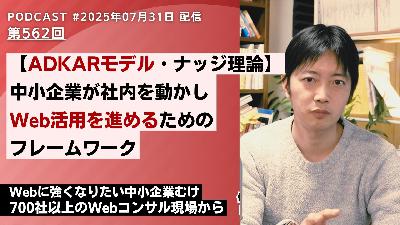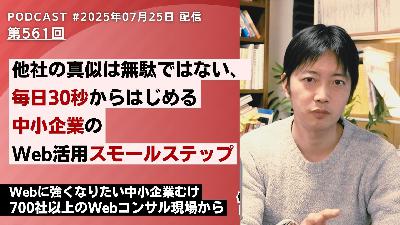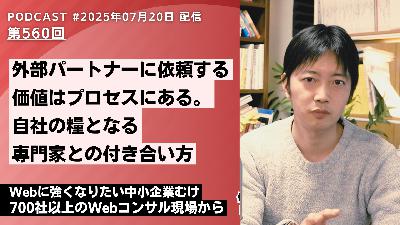第575回:Google Analytics MCPサーバーは初心者は避けるべき理由と、そもそもの「ツールの選び方」とは
Description
ポッドキャスト一部抜粋
Googleアナリティクスの「MCPサーバー」本当に誰にでも便利なツールか?
今回は、Googleアナリティクスの「MCPサーバー」とは?そしてそれは誰もが使うべき便利なものなのか…?結論から言えば違います。ある程度データ解析やGAが分かっている人でないとリスクが大きいです。
Google アナリティクスの MCP サーバーを試す | Google for Developers
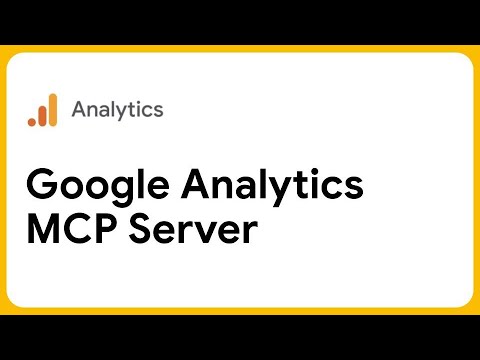
Google Analytics MCPサーバーは誰のため?ツールの本当の価値と選び方
今回は、以前からお話ししようと思っていた「Google Analytics MCPサーバー」についてです。ただ、このテーマ、どうお伝えしようか考えていたのですが、必ずしもポジティブな内容にはならないかもしれません。
というのも、このMCP機能は自然言語、つまり私たちが普段話す言葉でAIに指示を出せることから、「分析が簡単になる」「民主化される」といったイメージが先行しているように感じます。しかし、私自身が深く向き合えば向き合うほど、これは分析に慣れていない方が安易に手を出すべきではない、少し注意が必要なツールだな、と感じています。
そこで今回は、MCPが本当に役立つのはどういう人なのか、という話に加えて、そもそも業務で使うツールとどう向き合い、どう選ぶべきか、という本質的なテーマに繋げてお話しできればと思います。
「新しいツールを導入したけど、結局使わなくなってしまった」「便利になるはずが、逆に手間が増えてしまった」そんな経験がある方にとって、きっとヒントになることがあるはずです。
Google Analytics MCPサーバーは、本当に初心者向けなのか?
結論:分析に慣れていないなら、まだスルーで良い
まず、今回の話で一番お伝えしたい結論からお話しします。
もしあなたがWebサイト分析の初心者であるなら、「Google Analytics MCPサーバー」のことは、一旦忘れてしまって問題無いと思っています。
ここで言う「初心者」とは、例えば次のような方をイメージしています。
- Googleアナリティクスに出てくる「指標」や「ディメンション」といった言葉の意味が、まだ曖昧にしか分からない。
- それらのデータを組み合わせることで、どんな発見や気づきが得られるのか、具体的なイメージが持てない。
- 普段、アナリティクスの画面を見ても、なんとなくアクセス数を確認するくらいで、他のデータをどう活用すればいいか分からない。
もし少しでも当てはまるようであれば、現時点でMCPを無理に使う必要性は全くないでしょう。それよりも、まずはGoogleアナリティクスの画面に慣れ親しみ、そこにあるデータが何を意味しているのかを一つひとつご自身の言葉で理解していくこと。その上で、Looker Studioのようなツールを使って、自分の手でデータを可視化しながらレポートを組み立てていく経験を積む方が、はるかに実践的で有益です。
MCPが真価を発揮するのは「データと壁打ち」できる人
では、MCPはどのような人にとって強力な武器になるのでしょうか。
それは、一言でいえば「データと対話(壁打ち)ができる中級者以上の方」です。
具体的には、各指標の意味を正確に理解し、「このデータとこのデータを掛け合わせたら、こんなことが分かるはずだ」といった仮説をご自身の中に持てるスキルがある方です。
私自身がMCPをよく使うのは、例えば他のデータと組み合わせて、相関関係を探ったり回帰分析をするような場面です。そうした少し手間のかかる集計を、対話形式でスピーディに進められるのは大きな魅力です。
例えば、私のコンサルティングでは、毎月決まった数字を報告する定型レポートではなく、その時々の状況に応じてストーリーを組み立て、最適なご提案をすることを大切にしています。その場で「この角度から見たらどうだろう?」「このデータと組み合わせたら何が見える?」と、AIと壁打ちをしながら分析を深めていくような使い方には、MCPは非常によくマッチします。
逆に言えば、毎月決まった形式のレポートを作成することが主な業務であれば、MCPを使うメリットはあまり感じられないかもしれません。それならば、APIやBigQueryを使ってデータを確実に取得する仕組みを構築する方が、はるかに効率的でしょう。
MCPを使いこなすための注意点と、私の実践例
AIに「解釈」や「推論」をさせてはいけない
MCPをある程度使えるようになった方でも、一つ注意していただきたい点があります。それは、少なくとも最初はAIに「解釈」や「推論」を求めない、ということです。
データの「集計」をさせるのは非常に有効です。しかし、その結果を元に「このデータから改善点を提案してください」とか「課題に優先順位をつけてください」といった判断を委ねるのは避けるべきです。
なぜなら、現状のAIから返ってくるのは、きちんとした前提条件付けなどを行わない会議リ、当たり障りのない、どこかで聞いたことがあるような一般的な内容がほとんどだからです。
例えば、AIはデータの中で変化率が大きい箇所を機械的に指摘してはくれますが、それがビジネス全体にどれだけの影響を与えるか、という視点が抜け落ちがちです。
例えば、全体のアクセスが10万ある中で、ある1ページの直帰率が20ポイント悪化した、という報告をさも重要そうに回答することがあります。
しかしこれは、1ページ当たりの数字の変化としては大きいですが、全体へのインパクトはごく僅かですよね。また、もし全体の数字へのインパクトが多かったとしても、ビジネス的にはどうでもいい変化もあるわけです(見込み客以外のアクセスが季節的に増えるページなど)。
先に検証やデータの設計がないと…
この辺りは、何が大事で何が大事では無いのかというルール付けや、そもそもそのルールや重み付けを作れるように先に検証やデータの設計をしないといけないわけです。
それを行う前提であればいいのですが、それを「きっとAIはそこまで考えてくれる」と思ってMCPServerに関わらずAIに解釈や推論をさせると、「意味がない」ばかりか「適切ではない」方向に導かれる可能性すらあると感じています。
あくまで定量的な事実を集計・整理するためにツールを使い、そこからの解釈や判断は人間が行う。この線引きが非常に重要になります。これをしなければ、まだ使わない方がいいというのが私の考えなんですね。まずはWebUIから普通に使って覚えた方が良いです。
余談「数字を鵜呑みにしない」という言葉の本当の意味
ちなみに、時々、「AIが出した数字は鵜呑みにしてはいけない」というアドバイスを見かけますが、私はこの考え方に少し違和感があります。
なぜなら、そもそも信頼できないかもしれないデータを出してくるツールを使うこと自体が、時間の無駄に繋がる、と考えるべきでは?と思うからです。
ツールと向き合う上で本当に大切なのは、「どこまでの範囲で、どのような指示を出せば、出力された結果を100%信頼(鵜呑みに)できるか」という安全な領域を見極め、その仕組みを自分で作れるかどうかです。毎回「この数字は本当だろうか?」と疑っていては、効率化は望めません。
例えば、集計をさせる際に「どのカラムのどのデータを使って算出したか」を併せて出力させるように指示すれば、その結果が妥当かどうかを人間がすぐに判断でき、信頼性を担保することが可能になります。
ツール選びで失敗しないために、考えておきたいこと
ここからは、MCPの話から少し視野を広げて、業務ツール全般との向き合い方についてお話しします。
ツールはあなたの能力を増幅させる「掛け算」
まず大前提として、ツールは「魔法の杖」ではありません。あなたのスキルがゼロの状態を、ツールが1から10にしてくれることは基本的にないのです。
ツールとは、あなたが持っている能力や、やろうとしていることを、より速く、より効率的に実行するための「掛け算」の役割を果たすものだと考えてください。つまり、あなたの能力を何倍にも増幅させてくれる存在です。
その価値は、大きく「省力化」と「能力の拡張」の2つに分けられます。この基本を理解しておくと、ツール選びのミスマッチを大きく減らせるはず。
「ピンとくるか」を一つの判断基準に
新しいツールを検討する際、その機能一覧や紹介画面を見て、「この機能を使えば、自分のあの業務がこのように改善されそうだ」と具体的にイメージできるでしょうか。もし、その場で使い方がピンとこないのであれば、そのツールはあなたにとってまだ早いか、そもそも合っていない可能性が高いと言えます。
もちろん、「このツールを使いこなせるようになりたい」という強い意志がある場合は別です。ただしその場合は、ツールを「使う」というタスクとは別に、「ツールの使い方を学ぶ」という、もう一つのタスクが発生することを覚悟しておきましょう。「なんとなく使っていれば、そのうち分かるようになるだろう」という期待は、残念ながらあまり持たない方が賢明です。
まとめ:最初の失敗を避け、一歩ずつ着実に進むために
Google Analytics MCPサーバーは、データと対話できるスキルを持つ人にとっては、分析の幅を大きく広げてくれる、非常に可能性を秘めたツールです。私自身、API経由で取得したデータ複数と、それ以外でも例えば国勢調査のような公開データセットと組み合わせることで、これまで見えなかった新たな発見に繋がることがあり、その楽しさを実感しています。
しかし、その大きな可能性ゆえに、最初のステップでつまずいてほしくない、という強い思いがあります。特に組織の中で、一度「AIを使ってみたけどダメだった」という印象がついてしまうと、その後の新しい挑戦がしにくくなる空気が生まれてしまうかもしれません。それは、長い目で見れば会社にとって大きな損失です。
だからこそ、特にデータ分析のような専門領域においては、焦らず慎重に進めていただきたいのです。もしあなたが今、Webサイトの分析に課題を感じているなら、新しいツールに飛びつく前に、まずは分析の基礎を学び、目の前にあるデータを深く理解することから始めてみてはいかがでしょうか。
MCPは今、世間の話題としては少し落ち着いていますが、本当に使いこなしている人たちは、SNSなどで発信するのではなく、静かにその恩恵を受けています。皆さんも、そうした領域に到達するために、ぜひ一歩ずつ着実に歩みを進めてみて頂ければ幸いです。
参考情報
- Google Analytics Data API 概要 | Google for Developers
まずは公式のドキュメントです。このAPIで何ができるのか、どのような機能(メソッド)があるのかがまとめられています。技術的な内容も含まれますが、全体像を把握する上で最も正確な情報源 - Google for Developers
実際にAPIを試してみたい方向けの、公式クイックスタートガイド
Web活用の「最初の一歩」に関するよくあるご質問
- Q. GoogleアナリティクスMCPServerとは何ですか?私にも使えますか?
- A. 自然言語(ふだんの言葉)で各種生成AIツールを通じて、Googleアナリティクスのデータにアクセスできる機能です。しかし、データの指標やディメンションの意味を深く理解している中級者以上の方に向いており、初心者の方にはまだお勧めできません。
- Q. なぜ初心者はGoogleアナリティクスMCPを使うべきではないのですか?
- A. 各指標の意味やデータの組み合わせ方を理解していないと、かえって手間が増えたり、判断を誤ったりする可能性があるためです。まずは基本を理解することが重要です。
- Q. Web分析の初心者として、まず何から始めればよいですか?
- A. まずはWeb UI(通常のGoogleアナリティクスの画面)を通じて、各データが何を意味するのかを理解することから始めましょう。その後、Looker Studioなどでデータを可視化し、自分でレポートを組み立てる練習が有効です。
- Q. ツールを導入して失敗しないための選び方のポイントは何ですか?
- A. 「そのツールで何ができるか」という機能一覧を見るだけでなく、「自社がその機能をどう活用できるか」を具体的にイメージできるかが重要です。イメージが湧かなければ、まだ導入は早いか、自社に合っていない可能性があります。
- Q. AIにデータ分析から改善提案までさせるのは有効ですか?
- A. 現状ではおすすめできません、有用な応答を期待すべきではないです。AIの提案は一般的で当たり障りのない内容になりがちで、個別の事業状況に合わせた深い洞察は得られにくいからです。集計などの作業は任せても、解釈や判断は人が行うべきです。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN
- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj
- Amazon Music Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第575回:Google Analytics MCPサーバーは初心者は避けるべき理由と、そもそもの「ツールの選び方」とは は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。